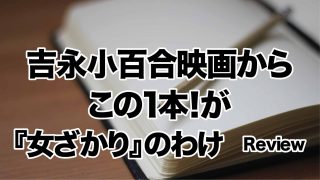吉永小百合さんの2018年の雑誌インタビュー記事の復刻です。主演作『北の桜守』が公開されるタイミングで轟夕起夫がお話を伺いました。

『北の桜守』は、主演作120作目となる映画でした。「主演」した映画が120本て! 驚愕です!!!

まだまだ主演作は続いています!『いのちの停車場』、2021年5月に公開予定です!!!

監督:成島出 出演:吉永小百合、松坂桃李、広瀬すず、南野陽子、柳葉敏郎、小池栄子、みなみらんぼう、泉谷しげる、石田ゆり子、田中泯、西田敏行、ほか。

現役でトップをひた走り続けるレジェンド、吉永小百合さんの、レジェンドたるかっこよさが詰まったインタビュー記事です!
吉永小百合 インタビュー
(取材・文 轟夕起夫)
『北の桜守』について
吉永小百合の通算120本目となる『北の桜守』(2018年)は、『北の零年』(2005年)、『北のカナリアたち』(2012年) に続いて“北の三部作”のファイナルを飾る一大巨篇だ。
太平洋戦争が終結したかと思いきや、旧ソ連軍の侵攻によりサハリン(旧樺太) を追われ、息子たちを連れて北海道・網走へとたどり着いた“江蓮てつ”の果てしなき大河のごとき人生。本作で彼女は、30代後半から60代後半までを演じ切っている。
『北の桜守』データ
2018年
監督:滝田洋二郎 脚本:那須真知子
出演:吉永小百合、堺雅人、篠原涼子、岸部一徳、高島礼子、永島敏行、笑福亭鶴瓶、中村雅俊、阿部寛、佐藤浩市

「可能な限り、このまま好きな仕事に身を投じていくほうが」
──まずは、完成した映画の手応えから聞かせていただけますか。
吉永 6カ月間かけて作りあげたのですが、観てくださる方々に何かを投げかけるような作品になったと思います。 戦争のこと、あの時代のこと、それから、生きていくということ……きっといろいろと感じていただけるのではないでしょうか。
──心境的に、120本目というのは節目ですか、それとも通過点ですか?
吉永 両方です。自分としては最初は、ただひたすらに「良い作品を!」って気持ちだったんですね。ところがクランクインの前あたりから、ひとつの区切りの意識が強くなりました。「ちょうど120本、これで終わりにしてもいいのではないか」とか、「もしかしたらこの映画が最後かもしれない」と。ただその消え方って難しくて、今、原節子さんのように姿を消し、伝説の中で生き続けることはできないですよね。特に私は原さんと違って、泳いだり、普段も積極的に外へ出たいタイプ。ならば可能な限り、このまま好きな仕事に身を投じていくほうがいい。しかもいざ撮影が終わってみたら、とても充実した時間を過ごせて、映画の世界をもっと歩いていきたいという気持ちが増したんです。どこまでやれるか分からないけれど、挑戦してみたいです。とは言っても120本ですから、金属疲労というのはすごくありますよ。本当に。
「終戦後の市井の人々の受難を記憶にとどめていただけたら」
──映画の舞台が、改めて北海道になったのは吉永さんの希望だそうですね。
吉永 製作に東映さんが名乗り出てくださって、できれば北海道で撮影していただけたら嬉しい、と私が申し上げました。『北のカナリアたち』を稚内で一緒に作った高橋一平さん……高橋さんは「最北シネマ」という映画館の社長で、今回もアソシエイトプロデューサーで参加なさっているんですけど、ある想いをずーっと持っていらしたんですね。「北のひめゆり事件」とも呼ばれる樺太の悲劇、ソ連軍の侵攻のさなか、9人の女性電話交換士が自決した真岡郵便電信局事件を映画で描けないかって。それでこのことを含めて終戦後の、南樺太の市井の人々の受難も皆さんの記憶にとどめていただけたらと、滝田 (洋二郎) 監督も私も思ったんです。
──そうした信条を軸に、個人の力を超えた、歴史に翻弄される人々の代表として吉永さん扮する江蓮てつとその家族の苛烈なドラマが綴られていきます。
吉永 もし戦争が起きていなかったら、この家族は樺太で、幸せに暮らしていたはず。けれども夫は戦地に向かい、てつは引き揚げ者として息子たちと網走に逃げざるを得なかった。そういう方々がたくさんいるんですよね。私は以前、対馬丸という沖縄の学童疎開の船がアメリカの潜水艦の攻撃を受け、多くのお子さんが亡くなった太平洋戦争中の史実を映画にできないかと考えたことがありましたが、南と北の違いはあっても、語るべき歴史の一端にアプローチできて良かったです。それも単にメッセージを打ち出すのではなく、映画的な潤いとともに大切な史実を物語に溶け込ませることができて。
「斬新で心に残る、素敵な試み」
──すでに話題になっていますが、演劇界の旗手ケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)による劇中劇、その舞台演出が一役買っていますね。 てつと子どもたちが樺太で空爆に襲われるシーン、それが大平炭鉱病院事件などと合わせて、大胆かつアブストラクトに表現されていました!
吉永 第1稿では、劇中劇は採用されていなかったんです。脚本の那須 (真知子) さんが樺太の悲劇を詳しく調べ、克明に書きこんでいたんですけど、これをもう少し重たくはなく、違う形で描けないか、というところから劇中劇にする話が出てきて、それで演劇プロデューサーの北村明子さんを介してKERAさんの舞台演出が実現しました。果たして実写と舞台がちゃんと融合するのか、繋げてみるまでは不安でしたが、斬新で心に残る、素敵な試みになったと思います。
──KERAさんの演出はいかがでしたか?
吉永 演劇の芝居っぽく動くようおっしゃられたらどうしよう、という恐れは事前にはありましたが、そんなことはなく、とてもナチュラルにやらせていただきました。都内のスタジオに舞台のステージが作られたのですが、発声だけは、「正面の200席ほどの客席に向かって話している感じでやってください」と。その一言の注文だけでしたね。てつの心象風景、目の前の悲惨な現実をちょっとファンタジックに構成した世界観だったんですけど、「こういう表現の仕方があるのか」と刺激的でしたし、経験できて楽しかったです。
描かれていないところを「想像して埋めていく」
──さて、網走に引き揚げてから小さな食堂を経営し、高度経済成長下、女手ひとつで子どもを育てていくてつ には、いくつかの人生の選択が訪れますがどう演じようと?
吉永 桜守を務めるてつはしっかりとした女性であり、また強い母親でもあると思ったので、前半はたくましさを前面に出しています。後半は獅子が子を谷底に落とすように、やむをえず息子の修二郎 (堺雅人)を網走から追い出すのですが、たくましかった彼女がひとりきりになると混乱し、ちょっと生きる目的を見失ってしまうんですね。そして修二郎が15年ぶりに網走に戻ってきて再会すると、今度はその15年の空白の時間がのしかかってくるわけです。てつがどんな想いで修二郎を待っていたのか……映画には具体的に描かれておらず、そこの部分を自分で考え、想像して埋めていくのが難しかったです。
「母さんのことは、今日限り忘れるの」。予告篇でも印象的な、てつが修二郎に放つ厳しい言葉だ。渡米してビジネスを学び、成功を収めて故郷に凱旋、1971年(昭和46年) に修二郎が外資系の社長として札幌に出店するのが、日本初のホットドッグストア・ミネソタ州 (現在のコンビニエンスストアのはしり) である。やがて修二郎の母の味、てつへの食堂の看板メニューであったおにぎりもホットドッグに並ぶ商品として売り出されることに。
この映画でおにぎりは、親子の絆、以上の多様な意味を与えられており、要所要所で物語を動かしていく。もちろんいつものごとく、吉永は事前に「おにぎり作り」の特訓をして撮影に挑んだ。
──三角型やボール型ではなく、当時主流だった太鼓型の大きなおにぎりを体得されたそうですね。
吉永 嬉しかったのは、堺さんがテストのときからパクパクと食べてくださって。何度テストを繰り返すか分からないから、普通はフリで済ますところをね……それは「母」として本当に至福でした。
『わたしは、ダニエル・ブレイク』に触発されて
──樺太から引き揚げた直後のシーンで、闇商売を仕切る菅原(佐藤浩市)と出会い、与えられたおにぎりを逡巡しつつも飢えには勝てず、てつが貪るように食べますが、臨場感があって心に残りました。
吉永 あれはね、昨年(2017年)、ケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイク』(2016年) を観まして、痛ましい境遇の若い母親が、空腹からフードバンクで思わず手づかみで食べてしまう場面に触発されて、やってみたんです。


『わたしは、ダニエル・ブレイク』については、こちらのレビューをどうぞ。
──そうだったんですか! 話は逸れますが確か昨年(2017年)の日本映画では、石井裕也監督の『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(2017年) が「素晴らしかった」と、ラジオ番組(『今晩は 吉永小百合です』)でおっしゃっていましたね。


『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』については、こちらのレビューをどうぞ!
吉永 和製ダニエル・ブレイクだと思いました。社会の片隅で懸命に生きている若者への、監督の温かな目をとても感じました。
「偉人よりも市井の人を演じていきたい」
──社会の片隅で懸命に生きる人たちに光を当ててきたのは、吉永さんこそじゃないですか。
吉永 そうですねえ……偉人よりも、市井の人を演じていきたいです。
──作品に話を戻しまして、ご自身で何かアイディアを出されたりは?
吉永 老いによって記憶が錯乱したてついが自分の靴を間違えるシーンがありましたでしょ。あれは私のラジオのリスナーの方からお葉書をいただいたんです。ご自分のお母さまの体験談として。ちょうどこの映画の台本作りが進行している頃で、提案してみました。 だから私のアイディアではないですね(笑)。リスナーの方の体験を取り入れさせてもらいました。ただし、少しアレンジはさせていただきましたが。あとは「流氷のシーンをぜひ入れてください」って。3年前に全くプライベートでオホーツクの流氷を見に行きまして、その美しさに圧倒されたんです。流氷は気まぐれで、撮影するのは至難の技だったのですけれど、幸運にも。映画の神様に感謝です。
「往年の撮影所のように…」
──初めて組まれた滝田監督の印象も聞かせてください。
吉永 最初は「こんな難しい役、できるかな?」と思っていたんですけど、滝田監督が陽性の方で、リハーサルから現場でみんなで常にワイワイと作っていかれるので、どんどん気持ちを乗せることができたんです。それと今回、デジタルで撮られたのですけれど、必ずカメラのそばにいてくださったんですよね。往年の撮影所のように監督とアイコンタクトで会話ができて、安心しました。
──終盤、記憶が錯乱したてつがひとり、鏡を見るシーンも忘れがたいです。滝田監督からはどういう指示が?
吉永 鏡に向かってね、本当に嬉しそうにニコニコと語ってほしいと。現実から違う世界へ飛び、また戻ってくるところを、監督は丁寧に撮ってくださいました。意識が混濁してはいましたけど、てつは幸せだったのかもしれないですね、そんなふうにして自分の世界の中で人と出会ったり、ある種、時空を超えた経験ができたのですから。
──何だか一緒に、吉永さんの長い映画人生も振り返っているような、そんな感触が一瞬ありました。あと特筆すべきは、体を酷使するシチュエーションが多い!
「できません」と言わないで済むよう用意して
吉永 そうでしたね。ひとつ心残りなのは雪の中で倒れるシーン、本当は「子どもをおぶって歩く」とシナリオにあったんです。これはおぶれるのかなと、家で30キロくらいのリュックを作って、それを背負って歩いたり、私の仕事のパートナーが45キロくらいなんですけど、彼女をおぶってみたりして、「できません」と言わないで済むよう用意していたんですけど、雪の中で倒れているのを起こし、それからおぶると時間がかかってしまうんですよね。かえって不自然だからということで、リハーサルの結果、雪上を引きずっていくアクションに変わったんです。
──なるほど、広義の意味での“アクション女優”なんですね。肉体言語と言いますか、エモーションを全身のモーションで伝えていくという意味で。
吉永 映画って基本的に、まったくセリフがなくても成立するものですよね。チャップリンの『街の灯』(1931年) や田中絹代さんの『恋の花咲く 伊豆の踊子』(1933年) など、私はサイレント映画が大好きです。演じる上でもセリフが少なければ少ないほどよく、それで表現できたら最高なんです。


チャップリン映画については、こちらをどうぞ
──肉体的には映画を撮るたびに、強靭になっていく感じはしませんか?
「映画をやりたいと願い、トレーニングをし、やり遂げた先に計り知れない喜びがある」
吉永 いえいえ、体力はどんどん落ちてますよ。確実に衰退しています。でも映画をやりたいと願い、トレーニングをし、やり遂げた先に計り知れない喜びがある。どちらかというと私は、演技者というよりはアスリート気質に近いのかも。今回は冷たい海に放り出され、泳がずに、必死に犬かきをして進むシーンも撮りましたけど、苦しくても楽しいんです。もちろん根本は、「変わらずに映画が大好き」ということに尽きます。不安だらけでも、やれる限りは1本でも2本でもこの後も続けていこうと今は思っています。
──では最後に。この映画の中の桜の樹はとてもシンボリックに描かれていますが、吉永さんにとって桜から思い浮かべるものとは何でしょう。
吉永 子どもの頃は、家に桜の樹が一本だけあって、その下で妹とおままごとをしたり、家族と食事をした思い出があります。そうですね、歳を重ねていくと桜は、命の象徴のような気がしますね。西行法師の和歌のように桜を愛でながら、「また今年の桜が見られた!」というのが、自分にとって生きている証しなのかもしれません。
いみじくも共演者の堺雅人は、こう語った。
「桜を見るとき、人はいろいろなものを投影して見る。吉永さんも人を過去やどこか違うところに持っていってくれる」と。
吉永小百合という「桜」の化身はわれわれに、人生の情趣「もののあはれ」を感じさせてやまぬ。

キネマ旬報2018年3月下旬号掲載記事を再録です!
吉永小百合 プロフィール
よしなが・さゆり
東京都出身。1959年『朝を呼ぶ口笛』で映画デビュー。
1962年の『キューポラのある街』で一躍注目を集める。主な作品に、『愛と死をみつめて』(1964年)、『愛と死の記録』(1966年)、『男はつらいよ 柴又慕情』(1972年)、『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』(1974年)、『動乱』(1980年)、『細雪』(1983年)、『おはん』(1984年、キネマ旬報主演女優賞受賞)、『華の乱』(1988年)、『女ざかり』(1994年)、『北の零年』(2005年)、『母べえ』(2008年)、『おとうと』(2010年)、『北のカナリアたち』(2012年)、『ふしぎな岬の物語』(2014年、プロデュースも)、『母と暮せば』(2015年)、主演作120本目の『北の桜守』、『最高の人生の見つけ方』(2019年)など。


















吉永小百合映画『女ざかり』のレビュー記事もどうぞ!

邦画も豊富なU-NEXTでは、吉永小百合「映画」は32本、ラインナップされています(2021年1月現在)