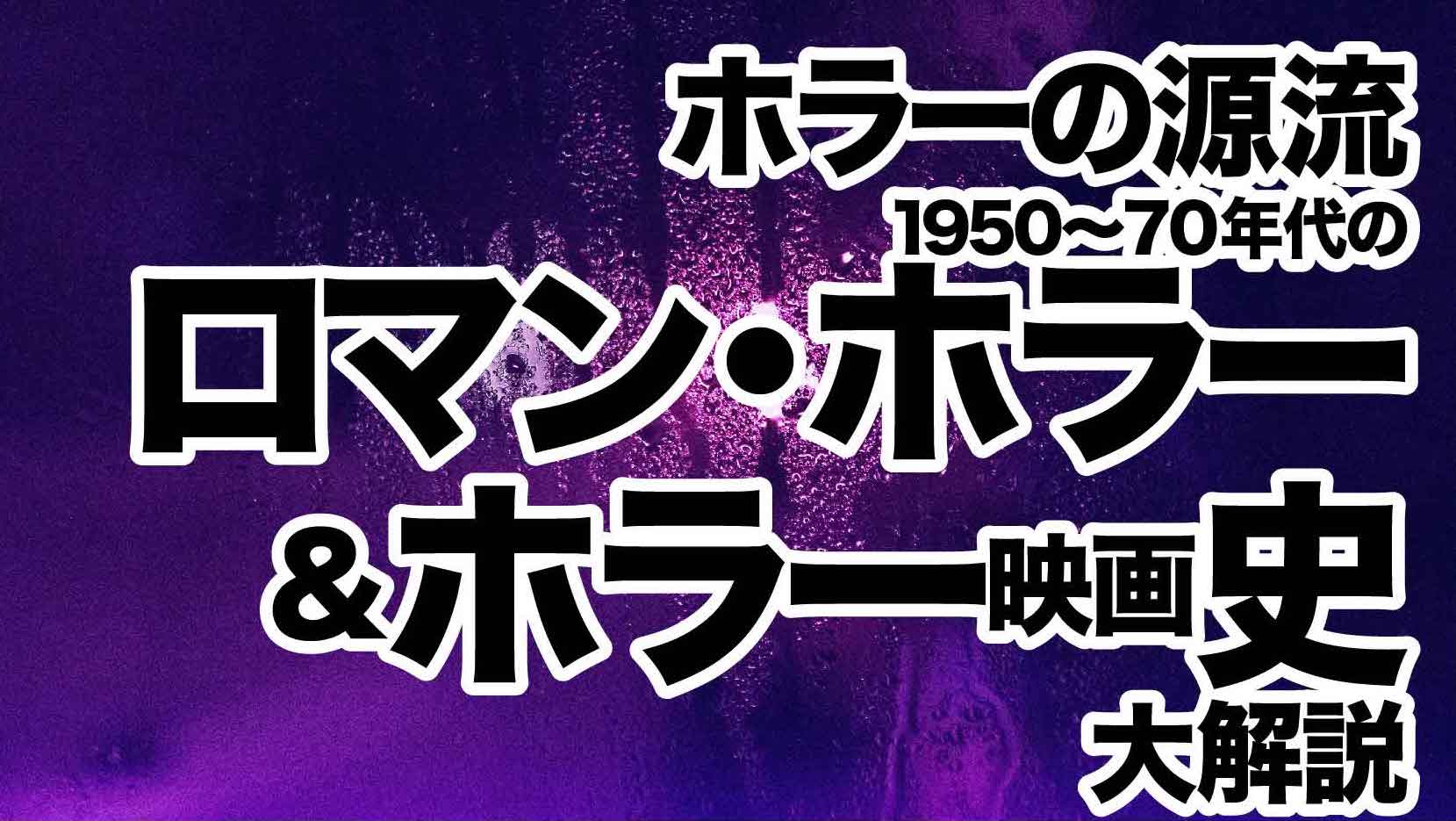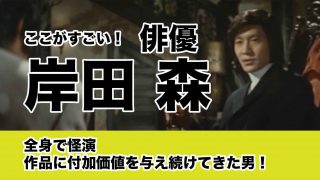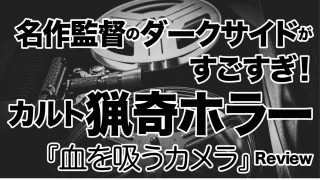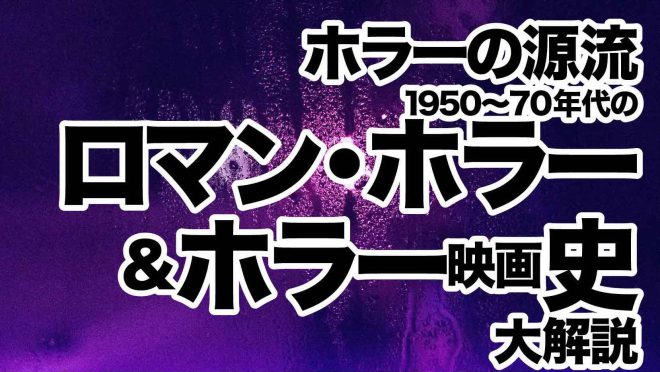

ホラーの源流ともいうべき1950年代〜70年代の怪奇・恐怖映画に注目し紹介するレビューです。今見るとそんなに怖くはないかもしれませんが、めくるめく耽美、幻想が堪能できる作品群は、その後のホラー映画に多大なる影響を与えました。

Netflixでは、オリジナルシリーズとして『呪怨:呪いの家』を製作、配信がスタートしました! ホラー、熱いです!
ちなみにこちらは初期の『呪怨』の監修・高橋洋さんが共同脚本で参加しています。

ホラーの源流を「ロマン・ホラー」とくくって、ホラー映画の歴史を解説です! 先の高橋さんについても文中で触れていますヨ!
ティム・バートン監督とロマン・ホラー
ティム・バートン監督の『スリーピー・ホロウ』は、伝説の“首なし幽霊騎士”の仕業とされる連続首斬り殺人事件に、若き警官が挑むゴシック・ホラーだった。


『スリーピー・ホロウ』は、ティム・バートンの世界をたっぷり堪能できるミステリー仕立てのゴシック・ホラー。ジョニー・デップに加えて怪奇映画の大スター、クリストファー・リーが特別出演しているのも見どころ!
怪奇にして幻想的なタッチ、18世紀のムードを立体化する凝りまくった美術と小道具……いつもながらの趣味性が全編に爆発していたのは云うまでない。
恐怖と甘美さが入り交じった“いつか見た光景”の記憶。人は自らが洗礼を受けたものに永久に囚われてゆく。それは古今東西変わらないひとつの真理だ。
ところで1958年生まれのバートンの趣味性(の一端)を探っていくと、海を越え、ネットサーフするかのように現在のジャパニーズ・ホラーの旗手たちへとリンクしてしまうことがわかる。
同世代の間を貫く、共通の土壌ともいうべき何かがそこにはあるのだ。ここに綴られる一文は、その顛末をめぐる事実の羅列をめざすものである。
名優ヴィンセント・プライスと、監督ロジャー・コーマン
というわけで、まずはバートンの洗礼について。例えばこれだ。「ハマーフィルム、ヴィンセント・プライスやロジャー・コーマン……etc、彼らが幼い僕の精神科医の役目を果たしてくれたんだ」(「キネマ旬報No.1305)
この言葉の意味を知るには彼の処女作に当たればよいだろう。7才の少年が、タイトルと同じ名前の、憧れの男になろうと夢想する人形アニメ 『ヴィンセント』(1982年)。
1950年代怪奇映画の常連、さらには1960年代の前半に、『アッシャー家の惨劇』『恐怖の振子』『黒猫の怨霊』『大鴉』『赤死病の仮面』といった工ドガー・アラン・ポー原作の(安手の)怪奇幻想映画に出演した名優ヴィンセント・プライスを指す。




一方ロジャー・コーマンは、配給会社アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ (AIP)を立ち上げ、それらを作っていたB級ムービーの帝王だ。

ちなみにロジャー・コーマンを描いた映画があります。レビューはこちら。
つまり子供時代の内気なバートンは、彼らの映画の世界に没入し、負性をともなった登場人物たちと同化してある種の解放感を得ていたのである。
ちなみにヴィンセント・プライスは『ヴィンセント』のナレーションを引き受け、遺作はバートンの『シザーハンズ』(1990年)になった。映画が取り持った不思議な縁である。


『シザーハンズ』の主人公、人間の心を持った人造人間(ジョニー・デップ)は、取り替えてもらえるはずだったハサミの手が、博士の死によりそのままで生きていくことに。恋した相手を抱きしめることができない切なさが泣けます。
英国ホラー配給会社・ハマーフィルム
さて、いまひとつのハマーフィルムだが、これは『フランケンシュタインの逆襲』(1957年)、『吸血鬼ドラキュラ』(1958年)を皮切りに、バートンの子供時代、1960〜70年代にホラー王国として狂い咲きした英国の製作配給会社のこと。


そしてそこで、ドラキュラ役者として名を馳せたのが、今回『スリーピー・ホロウ』でNY市長役として登場したクリストファ・リーなのだった。
バートンは語る。
「ハマー・ホラーは、他と全然違う強烈さを持っていた。彼らこそが、ホラー映画に、生臭さ、ケバケバしさ、セックス、そしてドラマも(笑)持ち込んだんだよ。それに彼らのセットの中には、結構美しいものがある。つまり、それまでのホラー映画に欠けていたものを、ハマーが取り入れてくれたのさ。今回は直接的なインスピレーションをどんどんもらった、と言っていいだろうな」(「キネマ旬報」同号)。
──以上。ようやく用意ができた。ここからがリンクの始まりだ。
監督・鶴田法男、高橋洋とジャパニーズホラー
『リング0〜バースデイ』(2000年)の鶴田法男監督(1960年生まれ)は、「絶対ホラー狂時代」(ミリオン出版)の中でハマーの『吸血鬼ドラキュラ』が好きだと明かしている。

その『リング』シリーズの脚本家、というよりか今日のジャパニーズ・ホラーの原動力ともいえる高橋洋(1959年生まれ)は、今まで観た映画で怖いと思ったものに、ロバート・ワイズ監督の『たたり』(1963年)とジャック・クレイトン監督の『回転』(1961年)を挙げている(「リング2 恐怖増幅マガジン」角川書店)。


どちらも心霊モノの古典で、前者はシャーリー・ジャクソン原作の「山荘奇譚」の映画化。幽霊は一切登場せず、音響効果と不気味な気配を漂わせる演出だけで怖がらせる。
後者の原作はヘンリー・ジェイムズの「ねじの回転」で、幽霊は画面の奥にチラリと登場するだけ。これが格別な恐怖感を生んだ。直接的な視覚効果ではなく、観る者の第六感(シックス・センス)を刺激するホラーのマスターピース!
このセンスはバートンの『スリーピー・ホロウ』にも継承されているのだが、鶴田監督にとってもまたこの2作はフェイバリット・ムービーである。
何しろ「このビデオを見ろ!第4集〈ファンタジー・SF・ホラー篇〉」(JIC)では、ペンネームの春出真名義(並べ替えればデ・パルマ!)で『たたり』について喜々と論じているのだから。
彼が高橋氏に、「何でもない空気に怖い空気を漂わせることができる」と絶賛されているのもムべなるかな、だ。
監督・山本迪夫と和製ドラキュラ・岸田森
ここで先の記事(「絶対ホラー狂時代」)に戻るなら、鶴田監督、ハマーの『吸血鬼ドラキュラ』と並べて、東宝の『血を吸う』シリーズも好きだったと告白している。
1970年の『幽霊屋敷の恐怖 血を吸う人形』と『呪いの館 血を吸う眼』、1974年の『血を吸う薔薇』のことで、監督はいずれも山本迪夫。



ハマーフィルムの日本的再生ともいうべきタッチが冴え、ジャパニーズ・ホラー史に大きな足跡を残した。
で、ここで2、3作目でドラキュラに扮していたのが岸田森である。TVシリーズ『傷だらけの天使』では従姉の岸田今日子との名コンビぶりを見せているが、『スリーピー・ホロウ』で幽霊騎士の生前の姿を演じたクリストファー・ウォーケンにも匹敵する、いや、それ以上の怪優だ。

俳優・岸田森についてはこちらの記事に詳しいです!

1982年に惜しくも43才の若さで逝去。ちなみに高橋洋が、子供の頃に観ていて一番好きだったのが円谷プロ製作のTVシリーズ『怪奇大作戦』(1968〜69年)。科学捜査研究所SRIの一員で彼が出ている。

亡くなってから出版された「不死蝶・岸田森」(ワイズ出版/実生活で蝶のコレクターでもあった!)では、発言集、エッセイ、脚本、関係者のインタビューがまとめられた。

余談ついでに『リング0〜バースデイ』で、鶴田監督が参考のためスタッフに見せた映画があって、それがロマン・ポランスキーの『反撥』(1964年)とジョルジュ・フランジュの『顔のない眼』(1960年)。


『反撥』はカトリーヌ・ドヌーヴが、セックスの妄想に取り憑かれた思春期の少女を演じた“引きこもり”ムービー。
『顔のない眼』は事故で顔をつぶした娘のために、外科医である両親が娘を次々とさらってきては顔の皮をはぎ、移植するという異常犯罪モノだ。
ポランスキーは、のちに妻となるシャロン・テートを起用して『吸血鬼』(1967年)を撮るが、彼女はこのあとチャールズ・マンソン率いる“ファミリー”に殺された。

が、何と『呪いの館 血を吸う眼』のヒロインであった江美早苗も、その作品を最後に引退し作詞家に転身したのだが(中里綴の名で南沙織のヒット曲「人恋しくて」などを出す)、1988年、ストーカー化していた元夫の音楽プロデューサーに刺殺されてしまったのだ。『吸血鬼』映画のヒロインに訪れた数奇な末路である。

リンクを続けよう。
オカルトホラーの金字塔と、監督・鶴田法男、脚本・小中千昭
鶴田監督とのコンビで、1991〜92年にかけてビデオ作品『ほんとにあった怖い話』シリーズ(全3巻)の脚本を担当したのが小中千昭 (1961年生まれ)なのだが、幻の雑誌「映画宝島」のコラムのコーナー名が「リチャード・マシスンになりたい」。そして「映画秘宝・エド・ウッドとサイテー映画の世界」(洋泉社)でもやはりマシスンの稿を書いていた!
とりもなおさずマシスンとは、先のAIPのエドガー・アラン・ポーものの脚色をし、さらにはスピルバーグの『激突!』(1972年)の原作、脚本を手がけ、数々のSF、ホラー、ファンタジー作品で先鞭をつけてきた異才だ。

その白眉が幽霊屋敷小説「地獄の家」で、自ら脚本化し、鬼才ジョン・ハフが映画化した『ヘルハウス』(1974年)は『エクソシスト』と並ぶオカルト・ホラーの金字塔となった。


ゴシック調の見事なセット、仰角、俯瞰、広角レンズを駆使した英国ホラーの麗しき伝統……だがここにも不幸が起こった。撮影中にこの製作者、AIPの生みの親でもあるジェームズ・H・ニコルソンが急死したのだった。
監督・黒沢清とホラー
ここで、満を持して登場するのが小中や高橋とも組んでいる、『CURE/キュア』(1997年)の黒沢清監督(1955年生まれ)である。

彼にはインディーズ時代、8 ㎜の『白い肌に狂う牙』(1977年)というタイトルの映画があった。これはイタリア=フランス合作、マリオ・バーヴァ監督の『白い肌に狂う鞭』(1963年)にインスパイアされ付けられたもので、本作での名義はジョン・M・オールド(ちなみに、ダリオ・アルジェントはバーヴァの弟子筋に当たる)。
ヒロインのダリア・ラヴィとサディスト役のクリストファー・リー(!)とが織りなす傑作官能ホラーだったが、ティム・バートンはといえばバーヴァのもう1本の代表作、拷問具“鉄の処女”が登場する『血塗られた墓標』のビデオを当時の妻、つまり『スリーピー・ホロウ』で魔女に疑われ、その拷問具で処刑される役のリサ・マリーに観せたという。

まったく、この世代たちの趣味性のシンクロ具合といったら何なのだろうか。
ところで彼らに先駆けて、マリオ・バーヴァの熱狂的ファンであることを標榜していた男がいた。当初“馬場毬夫”なる変名で『HOUSE ハウス』(1977年)を作って、劇場デビューしようとした大林宣彦監督 (1938年生まれ)だ。

監督・大林宣彦とホラー
『HOUSE ハウス』は、夏休みに田舎を訪ねた美少女たちが奇怪な家に喰われてしまうというホラーなのだが、爆笑ポイントも満載のポップ・エンターテインメント(なのにたしか、ジイさんだかバアさんが劇場でショック死するという事故が起きたはず!)。キテレツでおどろおどろしくも楽しい仕掛けいっぱいの映画だった。
そんな大林監督のインディーズ時代の短編『EMOTION=伝説の午後=いつか見たドラキュラ』(1967年)には、冒頭、ナレーションでこんな献辞が ──。
「ロジェ・ヴァディムと彼の『血とバラ』に捧げる。その青春と、青春の終わりの故に」
そう、ブリジット・バルドー、カトリーヌ・ドヌーヴ、ジェーン・フォンダらを筆頭に、華麗なる女性遍歴を誇り、2000年2月1日に癌のために72才で死去した監督ロジェ・ヴァディム。
彼にはルイ・マル、フェデリコ・フェリーニとともに参加した豪華ホラー・オムニバス『世にも怪奇な物語』(1968年)もあるが、『血とバラ』(1965年)こそは耽美派の面目躍如たる最高傑作だ。

クライマックスで、血の赤が画面に部分着色されてゆくビジュアルの冒険は、大林作品のみならず、無数の映画に影響を与えた(先述の『血を吸う薔薇』などタイトルからしてそう)。
監督・中川信夫とホラー
だが、ビジュアルの冒険、ということであれば、この人のことを忘れてはいけない。中川信夫。『HOUSE ハウス』から大林作品の重要な一員となった脚本家・桂千穂(1929年生まれ。念のため男性です)も敬愛する監督のひとりが彼である。
桂氏だけではない。高橋洋とのコンビで『女優霊』(1969年)や『リング』シリーズ2作を放った中田秀夫監督(1961年生まれ)が、やはり中川監督の代表作『東海道四谷怪談』(1960年)と遺作『怪異談 生きてゐる小平次』(1982年)を絶賛している。





さらに高橋氏などは「ホラーをやる以上はどうしてもメロドラマの部分を探求したいという欲望があるんです。理想はあくまでも高く、中川信夫の『東海道四谷怪談』に迫りたい」(前掲書の「リング2 恐怖増幅マガジン」)とまで熱く述べている。
真打ち登場である。日本のハマー・プロともいうべき新東宝であらゆるジャンルの作品を撮り、中でも怪談・恐怖映画の巨匠として語り継がれる中川信夫。今日のジャパニーズ・ホラーの旗手たちの精神的支柱も、ここにあるといっても過言ではない。
怪奇映画(ロマン・ホラー)ベスト10
最後に、ある雑誌の「怪奇映画ベスト10」を載せて締め括ろう。「映画評論」1973年10月号から──
①『東海道四谷怪談』
②『血とバラ』
③『吸血鬼ドラキュラ』
④『地獄』
⑤『吸血鬼』
⑥『反撥』
⑦『エクソシスト』
⑧『悪魔の首飾り』(世にも怪奇な物語)
⑨『白い肌に狂う鞭』
⑩『顔のない眼』
な、何と、本文に登場したほぼすべての作品が並んでいるではないか。ん? あらかじめこのベスト10を参照して「謀ったな」ってか? いやいや目指したのは事事の羅列だ。
恐怖と甘美さが入り交じったいつか見た光景──人は自らが洗礼を受けたものに、永久に囚われてゆく。
(轟夕起夫)

ではでは、ダダダと作品群をチェック!
ロマン・ホラーな洋画たち!8選
『吸血鬼ドラキュラ』(1958年)

ハマー・プロが手がけたクリストファー・リー主演のドラキュラ映画第1作目。監督はホラー映画の鬼才テレンス・フィッシャー。1930年代に米・ユニバーサル映画が製作した「ドラキュラもの」を、初めてカラーで映画化した。当シリーズは続編『凶人ドラキュラ』含め1973年までに計7作が作られた。
『血とバラ』(1960年)
監督ロジェ・ヴァディムが幻想怪奇小説の祖レ・ファニュの小説「吸血鬼カーミラ」を下敷きに映画化したもの。耽美的な映像が繰り広げられる名作で、とりわけ終盤、モノクロ映像が部分的に真っ赤に染められる様が恐ろしくもあり、美しくもある。
『たたり』(1963年)

超常現象の研究家とその助手が、呪われた幽霊屋敷に乗り込むというストーリー。技巧を凝らした“間接的な怪異表現”は様々な作品に影響を与えた。『ウエスト・サイド物語』『サウンド・オブ・ミュージック』だけではない、監督ロバート・ワイズの懐の広さにビックリ。
『吸血鬼』(1967年)

ロマン・ポランスキー監督が名作『ローズマリーの赤ちゃん』を撮る前年に発表した吸血鬼のパロディ映画。ポランスキーはコメディリリーフ的な役回り(バンパイアハンターの教授の助手)で出演も。彼が惚れる宿屋の娘を演じたのが、妻となるシャロン・テートである。
『世にも怪奇な物語』(1967年)

エドガー・アラン・ポーの原作をルイ・マル、ロジェ・ヴァディム、フェデリコ・フェリーニという3監督が映画化したオムニバス。怪奇と幻想の世界がそれぞれの個性によって、見事に綴られている。出演もジェーン・フォンダ、アラン・ドロン、ブリジッド・バルドー、テレンス・スタンプと超豪華。
『ヘルハウス』(1973年)

舞台は悪霊の棲む古びた館。そこで起こる超常現象に対し、物理学者夫妻、女性霊能力者、そしてかつてこの館に挑んだことのある霊媒師(名優ロディ・マクドウォール!)たちが科学の力で立ち向かう姿を描く。寡作だが敏腕、ジョン・ハフ監督による1970年代オカルト映画の傑作。
ロマン・ホラーな邦画たち!5選
『東海道四谷怪談』(1959年・新東宝)

日本の怪談&恐怖映画の巨匠、中川信夫の代表作。鶴屋南北の有名な原作を基にした、色悪の田宮伊右衛門と妻・お岩の亡霊リベンジ物語。冒頭シーン、歌舞伎の様式美を採り入れつつ長回しで見せる撮影手法や、闇と色彩のコントラストを生かした映像が強烈!
『地獄』(1960年)

『東海道四谷怪談』と並ぶ中川信夫監督の代表作で、ゲーテの「ファウスト」から着想を得た作品。“魂の救済”という難しいテーマを扱いながら、針山や血の池など地獄絵図を再現した美術(名手・黒沢治安!)と映像が、見世物的な面白さを生み出している。

スマート2000年5月1日号掲載記事を改訂!

こちら関連記事もどうぞ!