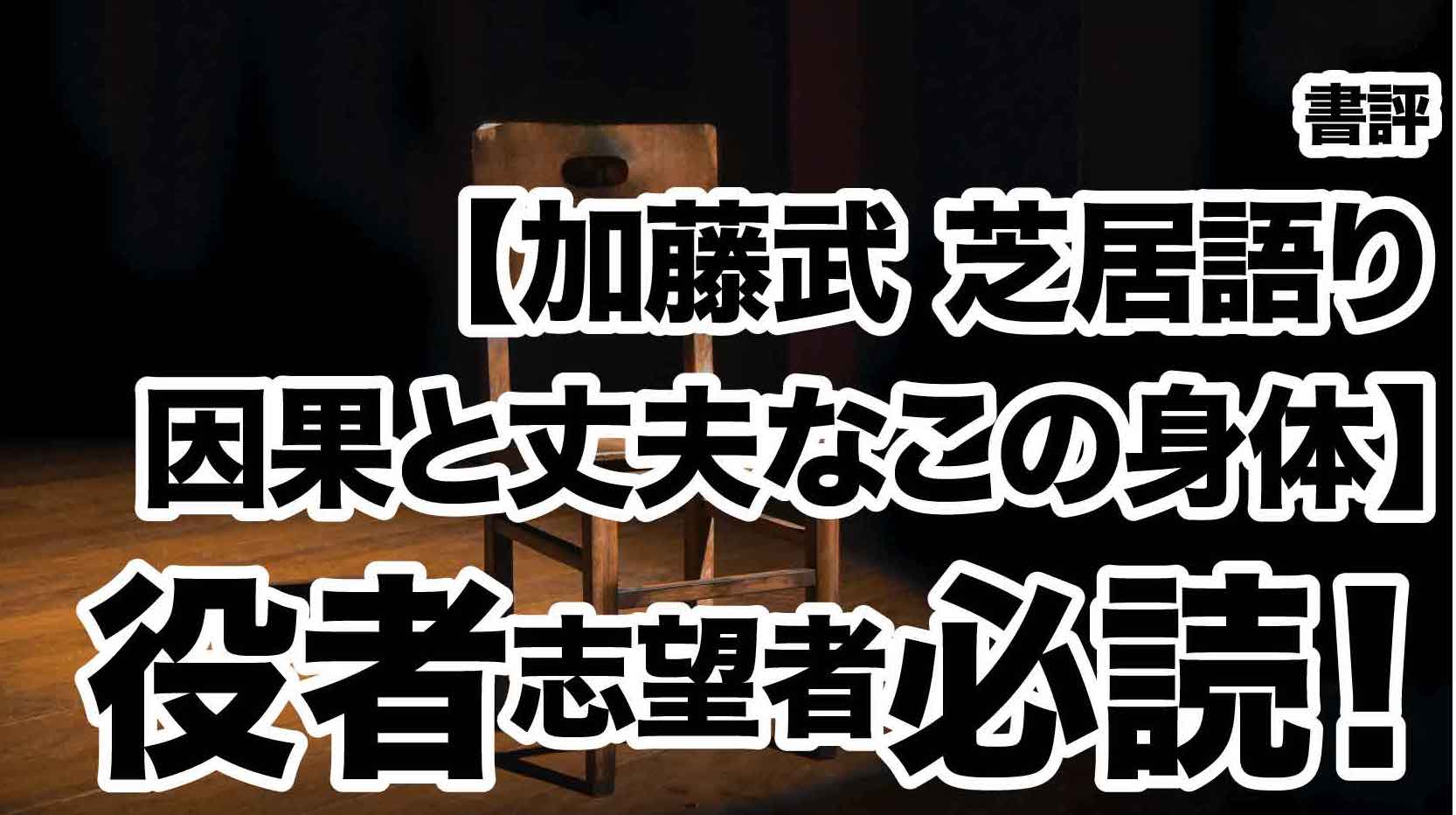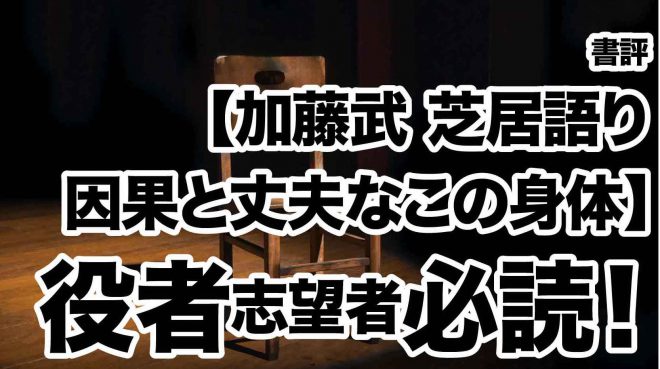


俳優・加藤武の書籍、レビューをどうぞ!
“大現役”の活力みなぎる言葉の数々
すでに各所で絶賛、称揚されているとおり、素晴らしい読み物である。「加藤武 芝居語り 因果と丈夫なこの身体」。戦後日本演劇界、そして映画、TVドラマ界を駆け抜けた名アクターの、まさに絶品の“語り芸”による一代記だ。
善人悪人変人なんでもござれ。ホームグラウンドの「文学座」の舞台では時に主役も演じたが、映画やドラマにおいてはバイプレーヤーとして活躍、どんな役柄であろうと観客の目を引きつけた。
本書では黒澤明、市川崑、深作欣二らの作品については無論のこと、帯にも記されているようにフランキー堺、小沢昭一、北村和夫との友情話に、監督川島雄三や今村昌平の現場、杉村春子の教え、太地喜和子の最期──なども自身の歩みと共にキレのいい江戸弁の“加藤節”で語られ、しっかり読み手の脳裏へと焼き付けられてゆく。
この一代記、本当はもっともっと続くはずであった。加藤さんが享年86で急逝されたのは2015年7月31日のこと。
当時は元気に文学座の代表を務め、『夏の盛りの蝉のように』(14)では葛飾北斎を演じて第49回紀伊國屋演劇賞個人賞、さらに第22回読売演劇大賞優秀男優賞と芸術栄誉賞に輝き、すでに翌年の主演舞台『すててこてこてこ』の全国公演も決まっていた。
つまり単なる回顧録ではなく、長いキャリア何度目かの黄金期の中、“大現役”の活力みなぎる言葉の数々がここには収められているのである。
ところで加藤さんのような戦後の新劇俳優は、1953年に結ばれた五社協定の縛りを受けなかった。本書の記述をまんま借りれば「映画会社を横断してさまざまな監督の作品に出演し、娯楽映画から文芸大作まで、日本映画の屋台骨を支えていた」のだ。
文学座の大看板・杉村春子はまさしくそのパイオニアで、映画界でも早くから地位を築き上げ、あらゆる意味で“師”であった。そんな彼女をめぐる芸談は、とても含蓄深く貴重だ。
また、(今期のNHK朝ドラ『なつぞら』の劇団分裂騒動エピソードのモデルとおぼしき)歴史的な文学座の分裂事件(2度目の『喜びの琴』事件のキーパーソンは座付作者・三島由紀夫である)についてもつまびらかにしていて、朝ドラ以上に人間臭く、生々しい“役者の世界”を感じさせてくれる。
そう! この本は、役者という生き物の不可思議さというか、“業(ごう)” を焙り出しているのだった。
例えば1974年──意を決して文学座をいったん離れ、麻布中学校時代からの盟友・小沢昭一が主宰する「芸能座」の旗揚げに参加したときのこと(5年間、期間限定の劇団で、活動終了後には復帰)。
第一回公演は永六輔作の『清水次郎長伝・伝』(75)である。で、加藤さん曰く、「一緒に小沢と芝居やっても、全然イキが合わないんだ。ハハハハ、びっくりでしょ? 普段はなんでもツーカーなのに」と。そしてこんなふうに分析を続ける。
「小沢は一人で汗かいて燃えてる。こっちはどんどん冷めていく。小沢の芝居って当意即妙で軽くて、(古今亭)志ん生みたいに見えるでしょ。ところが実際は、ものすごく一生懸命やってるんだよ。そういう芸なの、あの人は。だから稽古が好きなの。本番よりも稽古が好き」
さらにここから鋭い観察眼が披露されるのだが、それはぜひ現物に当たってみてほしい。特に男優、女優にかかわらず、役者を志している方ならば必読の本でもあると思う。
こうした珠玉の言葉を加藤さんから引き出しつつ、あいだに挟んでいく“地の文”も内容、リズム合わせてすこぶる良い。
これが初の著書となるのは市川安紀。市川さんは演劇誌「シアターガイド」の元編集長で、劇場公報誌、演劇プログラムの編集・執筆や、各媒体での俳優、クリエイターへの取材、インタビューを手がけている人。実は2011年から自主的に加藤さんへの取材を始めていた。見事に相手の懐の奥へと潜り込んでいるのだが、きっと「市川」姓の時点から縁があったのだ。加藤さんが大好きだった歌舞伎役者が二代目市川左團次だったのだから!
いやいや失礼、それは冗談。この仕事、演劇と映画、両方に精通していないと絶対に不可能で、市川さんは確かな知見を持っている。一例だが、高峰秀子主演、成瀬巳喜男監督の『放浪記』(62)を紹介する箇所で、映画に先立つ森光子の舞台版のことにもさらりと触れ、「貪欲な懸命さで観客の共感を呼ぶ芙美子像をつくり上げた森とは異なり、高峰は人間の醜さもあざとさもむき出しのまま、貧乏のどん底から流行作家にのし上がる“嫌な女”として演じた」と書く。一事が万事、彼女のナビゲーションは信用できる。ゆえに名アクターは心を開いたのだ。

この『放浪記』は加藤武初の成瀬映画。そこから高峰秀子との共演エピソードにつながり、あれよとカトウ違い、加東大介の話題へとスライドしてみせる。そんな構成もいい。本を読んで、久々に吹き出し、涙ぐみ、そして余韻に耽ってしまった。(轟夕起夫)

キネマ旬報2015年掲載記事を改訂!

関連記事のご紹介!蔵出し加藤武インタビュー、こちらにあります!

関連記事のご紹介。舞台好き、小劇団ファン、役者志望、演劇人志望の人に! 小劇場の演目がスマホで見られる動画配信サービス「演劇三昧」については、こちらで紹介しています。