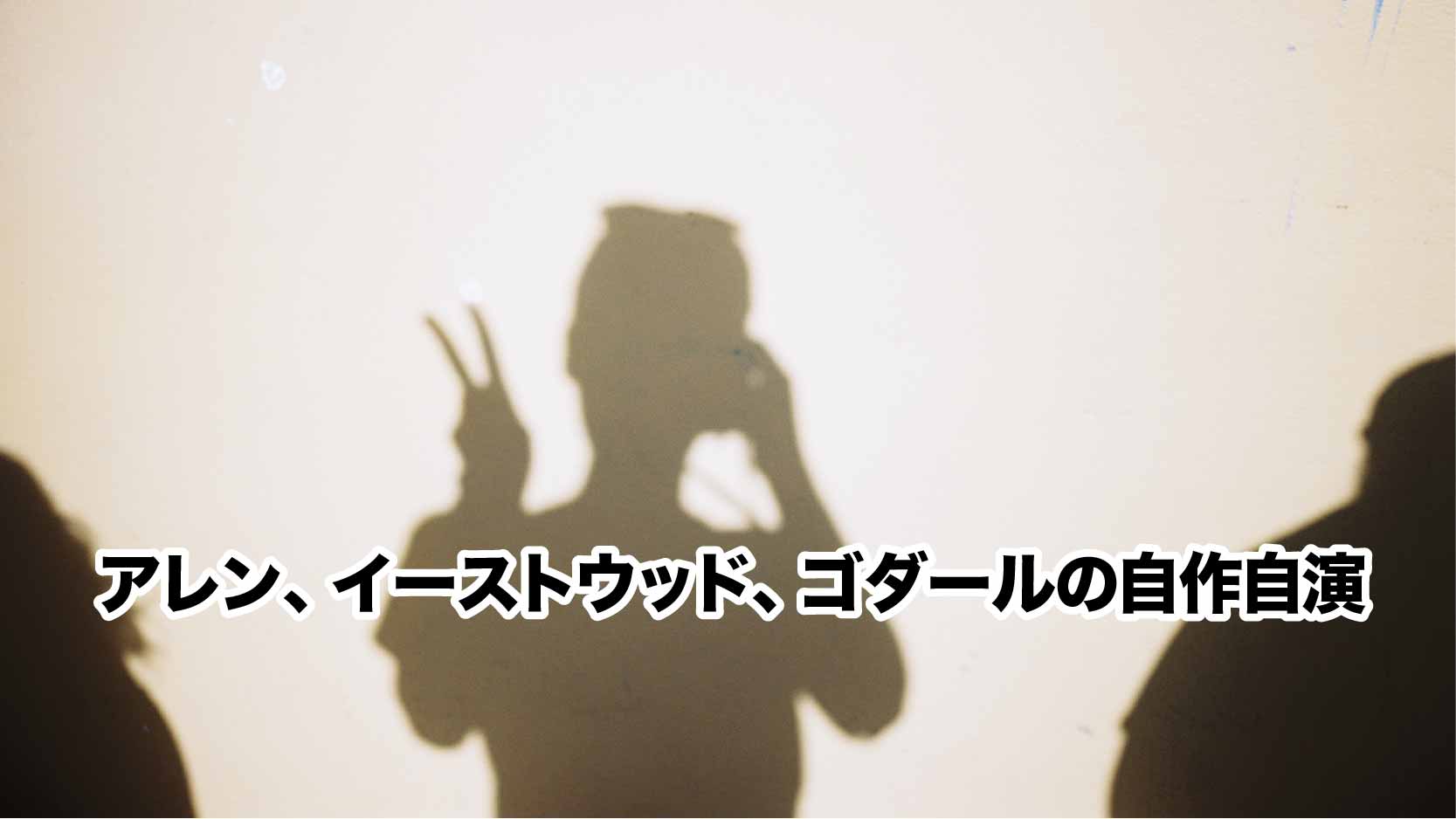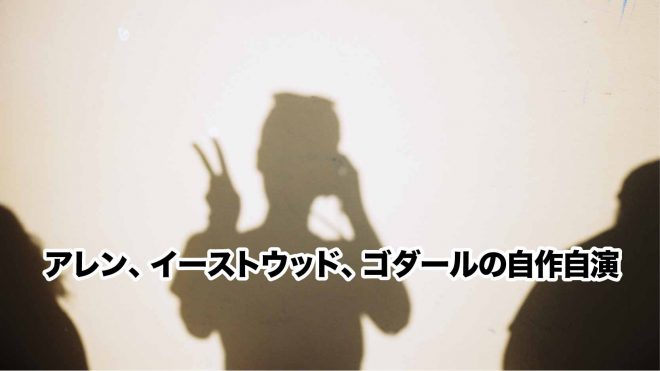

まったく個性の違う映画を数々創造している3監督。自作自演が多いことが共通項。

並べて考察してみれば、監督自身のキャラの違いも見えてきて面白いです。

そんな、轟のコラムの復刻です。
俳優として演じ、監督してまとめ上げるエキスパート3人を比較してみた
ウディ・アレン。クリント・イーストウッド。ジャン=リュック・ゴダール。
さて簡単なクイズを。この3人の共通点は一体何でしょう?
答え。――自分で監督を務めた作品のなかで役を演じてみせる――つまり、“自作自演”の名手である。
いや待て。名手ではあるが、ちとニュアンスが違うか。正確には熟練者、エキスパート、スペシャリスト……こっちのほうがより相応しいと思う。
ウディ・アレン
他人の映画で遊び倒した『What’s Up, Tiger Lily?』はおいといて、ウディ・アレンは実質的な監督デビュー作『泥棒野郎』(1969年)からもう“自作自演”を始めていた。

もともとギャグライターで、スタンダップ・コメディアンでもあったから、そうなったのも自然の流れと言えるが、黒縁メガネ(タートオプティカル社のヴィンテージ品)とニューヨーカー王道のファッション(ほとんどがラルフ・ローレンのもの)に身を包んだ普段着のスタイルがかくも長く、役者としても彼の公式的なイメージとして続くとは!
合わせて、早口で皮肉屋で饒舌、ユダヤ人コンプレックスを抱え、自意識過剰でやや神経質な、でも女性にはけっこう好かれ、若いコには目が無い、煩悩だらけのインテリキャラもずーっと変わらない。それからデビュー当時から薄くて、案外しぶとい頭髪も!!
ウディ・アレンは「ウディ・アレン」のままでいる。歳を重ねても。初期にはチャップリンやキートン、ボブ・ホープといった喜劇人のレジェンドを意識したこともあったが、ウディ・アレン本人にそっくりな公式的なイメージのほうが広く強く、定着していった。
そんな男はかつて発表した『誘惑のアフロディーテ』(1995年)で演じたスポーツライターのために、「クリント・イーストウッドは美容師を演じない」という台詞を書いた。
養子として迎え、育てた優秀な息子の実の母親を探しだすのだが、彼女はポルノ女優で娼婦という身。そんなヒロイン(ミラ・ソルヴィノ)を改心させようとやんわりと、そう説得したのだった。

「ウディ・アレン 映画の中の人生」(エスクァイア マガジン ジャパン刊)ではインタビューに答え、アレンはこう言っている。
「一般に観客はスクリーンの人物には、それを演じる人間に似たところがあると考えるか、少なくとも考えたがっていると思う。もしジョン・ウェインが、例えば臆病者で意気地なしで女々しくて、スクリーンのイメージとは正反対だったら、みんな憤慨するだろう。同じことが、クリント・イーストウッドについても言える」

クリント・イーストウッド
たしかにイーストウッドは一度も、美容師を演じていない。今後も十中八九、演じないだろう。だが、アレンの指摘は100%正しいわけではない。
イーストウッドは常に自覚的にキャリアを積み上げ、加齢とともにマチズモが際立っていた過去のキャラを大胆に解体、再編成し、『許されざる者』(1992年)でそれを極めたあとも、自作自演で『ミリオンダラー・ベイビー』(2004年)、『グラン・トリノ』(2008年)とセルフイメージを更新し続けているのはご存知の通りだ。

書き忘れたが、先のアレンのインタビュー、2001年に行われたことを差し引かなければフェアではないだろう。そして、ああいう発言になったのは、自身お気に入りの作品『スターダスト・メモリー』(1980年)でエラい目に遭ったからに違いない。

扮したのは人気コメディ監督。そろそろシリアスな映画作りに舵を切ろうとしているが、映画祭で自分の回顧上映に参加し、会場の質疑応答で「初期の楽しい作品」が好きな多くの熱狂的ファンから厳しい言葉を浴びせられる。
実際、ウディ・アレンは『スターダスト・メモリー』の公開時、批評家や観客からひどく非難された。まるまる主人公と同一視されてしまったのだ。
それでは“被害者”の弁明を聞こう。
「僕にはダスティン・ホフマンやロバート・デ・ニーロのようなことはできない。彼らのような才能はないんだ。僕が演じるのはニューヨークに住んでいる男とか、ニューヨークに住んでいるように見える男であって、警察署長には見えない男だ。ある種の人物には見えるけれど、その範囲は限られている。そうした人物なら僕には演じられるし、きちんとうまく演じることができる。でも、それ以外のことはできない。自分の服を着るから僕のように見えるし、この眼鏡をかけるから僕みたいに見える」(前掲書より)
笑える。さすがウディ・アレン歴が長い人の告白。自分の服を着て、眼鏡をかけるように彼はアレン映画に数多く出てきた。謙遜してはいるが見え方を、ちゃんと計算している。
この男(カメレオン)を招聘し、『ゴダールのリア王』(1987年)のオチを任せたのがジャン=リュック・ゴダールだ。

ジャン=リュック・ゴダール
編集機の前に座り、35㎜フィルムを針と糸で縫い合わせ、繋げる“ミスター・エイリアン”役。そのゴダールはといえば、“プラギー教授”として登場、頭に無数の電気コードをかぶり、旧友の写真に「フランソワ(・トリュフォー)、僕は一体どうしたらいい?」とボヤく。
いやいや、こっちが「あなた、何やってんの!」とツッコミたい。
『カルメンという名の女』(1983年)では精神病院にいる“失業中の映画監督”、『右側に気をつけろ』(1987年)では“白痴公爵殿下”と、こちらも自虐ギャグ路線をひた走り(1995年のドキュメンタリー「JLG/自画像」もそうか……)、しかし『アワーミュージック』(2004年)では、戦争と内紛の歴史の街、サラエボを訪れた“監督ゴダール”役で映画をキリリと引き締める。
まったく曲者すぎる自作自演のプロである。

叶うことならアレン、イーストウッド、ゴダールが、共演した映画ができないものか。夢のまた夢だが、観客との“暗黙の契約”と戯れ、それを維持してきたトリオの新たな姿を激しく夢想する。

キネマ旬報2015年4月上旬号掲載記事を改訂!

関連記事として、イーストウッドとゴダールの記事をご紹介。

日本の自作自演といえばこの監督!北野武についての記事もついでにご紹介です。

ついでにこちらも!