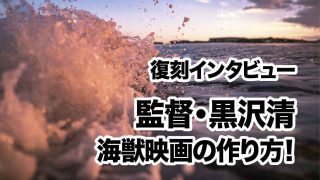女優・香川京子さんのロングインタビュー記事を復刻掲載です! 2008年、76歳の時の記事となります。2021年も出演作2作の公開を控える現役大女優!!
女優・香川京子について
(文 轟夕起夫)
「女優らしくない女優」というイメージだったと香川京子さんは自身のことを語る。演技者としてはマイナスの言葉なのかもしれないが、香川さんの魅力は名演技とともにその「女優らしくない」ところにあるのだろう。
その大きな魅力は、成瀬巳喜男、溝口健二、小津安二郎、黒澤明ら巨匠をはじめ多くの監督たちに活かされ、120本を超える映画に出演してきた。
このインタビューは、1949年から現在に至るまで、映画を愛し、映画の仕事を愛し、映画の歴史とともに歩みつづける映画女優・香川京子さんの魅力に、敬意と感謝をもって、迫るものである。

こちらのインタビューは雑誌記事のため、2008年に行われました。2008年の出演映画『東南角部屋二階の女』公開のタイミングでしたので、この映画を導入に、キャリア全般についてのお話を伺う展開になっています。

ちなみにこのインタビュー後も出演映画は増え続けています。2021年には出演映画が2本、夏以降に公開となります。『峠 最後のサムライ』(監督:小泉堯史、出演:役所広司ほか、2021年7月1日公開)、『島守の塔』(監督:五十嵐匠、出演:萩原聖人ほか、2021年夏公開)。
香川京子 プロフィール
かがわ・きょうこ
1950年『窓から飛び出せ』で本格的に映画デビュー。
以後、成瀬巳喜男、溝口健二、小津安二郎、黒澤明、今井正、豊田四郎、吉村公三郎、山本薩夫、堀川弘通、山田洋次、熊井啓、小泉堯史ら様々な監督たちの映画に出演、出演数は100本を超える。1990年『式部物語』でキネマ旬報助演女優賞を、1993年『まあだだよ』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、田中絹代賞を受賞。著書に『ひめゆりたちの祈り』『愛すればこそ』がある。



香川京子 インタビュー
(取材・文 轟夕起夫)
若い世代のアクターから溝口組や黒澤組のことを聞かれて
香川 現実って厳しいものだけど、この映画、どこか夢があってね、全体的に柔らかな、いい作品になりました。
優しく、しかし、確かな意志を込めて、語りかけてくる。映画『東南角部屋二階の女』について、そう感想を述べられた香川京子さん。監督の池田千尋は、東京藝術大学大学院映像研究科の第一期生で、黒沢清、北野武に師事した俊英。2007年に卒業し、本作に取りかかり、臆することなく大女優に出演依頼し、夢を実現させた。
香川 最初、キャスティングプロデューサーの城戸(史朗)さんからお電話がありまして、映画の話をお聞きしました。それから池田監督と脚本の大石(三知子)さんと城戸さんの3人から、とても丁寧なお手紙をいただいたんですね。
私は、内容的にちょっと自分には合わないかなと思ったときは、失礼にならないようお会いする前に御辞退するんですけど、3通ものお手紙いただいて、これは一度お会いしないと申し訳ないと思いまして。
池田さんは27歳の若い女性で、とてもしっかりしていて、落ち着いた印象で、この方なら大丈夫、きっといいお仕事ができるはず。と、それでお引き受けしたんです。
取り壊し寸前の古アパートに集った若者たち (西島秀俊、加瀬亮、竹花梓)の、人生の休憩所の物語。香川さんが扮するのは、そのアパートのオーナー・夏見藤子。近くの小さな居酒屋で女将をやっており、戦死した婚約者の兄、友次郎に秘かな想いを寄せている。
香川 藤子は、許嫁を戦争で失った後、ずっとひとりで生きてきた人だから、かなり強い女性ではないかと。私は脚本を読んで、そう感じました。そして、もう少し藤子の日常の場面を入れてほしいと池田監督には提案してみました。
それと友さん……友次郎役の高橋昌也さんがほとんど口をきかないキャラクターでしょ。両方静かな人ではなく、藤子はもうちょっと活発に、元気に演じてみたい、とも。私たちの年代って、つまらないことにはこだわらないというか、そうなったら仕方ないわ!って、一種の潔さみたいなものを持っている気がするのね。藤子もきっと、そんな人じゃないかなと思ったんです。
自分のビジョンをはっきりと言葉にする香川さん。衣裳に関しても、藤子の“生活感”を大切に
した。
香川 池田監督は、前作の『赤い鯨と白い蛇』(2006年)を御覧になられていて、あの映画の着物姿のイメージをふくらませたかったようなんですが、藤子は、友さんの身のまわりの世話をしていますし、働くのに不都合もあったので、 お店では和服、普段はもう少し活動的な服にするのはどうですか、とお話しました。

タイトルの挙がった『赤い鯨と白い蛇』は、数々の名作ドラマを発表してきた名演出家、せんぼんよしこの映画監督デビュー作。香川さんは以前、せんぼん作品では「愛の劇場」シリーズの『縁』(1961年)で芸術祭奨励賞を受賞している。
香川 芥川比呂志さんとの夫婦役でした。せんぼんさん、『赤い鯨と白い蛇』の現場でもお元気で、厳しさも演出の粘りも、ぜんぜん変わられていなかった。
今回の撮影の合間には、映画の展開同様、若い世代との対話──西島秀俊や加瀬亮との交流があったという。
香川 西島さんは、評論家かしらと思うくらい、本当に何でもよく知ってらっしゃるのでビックリしました。加瀬さんもそうですけど、お二人とも本当に映画が好きでたまらないという感じでね。私、最近あまり観ていないから刺激されて、勉強しなきゃって。同じ部屋でのお弁当のとき、溝口組や黒澤組のことなんかを、こうだったのよ、と話したら熱心に聞いてくれました。
役が潜り抜けてきた人生を背負う重み
二人がいろいろと質問してしまうその気持ち、よく分かる! 何しろ日本映画の黄金時代を生き、支え、今もその息吹を伝える方なのだ。そういえば香川さん、名女優・田中絹代の監督デビュー作『恋文』(1953年)、さらには『女ばかりの夜』(1961年)にも出演されていた。女性監督の歴史が、こうしてひとりのアクトレスを通じて現代に繋げられていく。これは素晴らしいことである。

助演ではあるが、『東南角部屋二階の女』での香川さんは重要な役だ。タイトルは、実は藤子のことを指しているのだから。劇中、彼女がふと口ずさむ歌は、西條八十作詞の童謡「かなりや」。短いが、とても印象的なシーンになった。

西條八十作詞の童謡「かなりや」はこんなですね。
唄を忘れた金糸雀(かなりや)は
後ろの山に棄てましょか
いえいえ それはなりませぬ
唄を忘れた金糸雀は
背戸の小藪に埋けましょか
いえいえ それはなりませぬ…
香川 あの曲は監督さんが選ばれたんです。昔、藤子がよく歌っていたんでしょうね。私も馴染みの深い曲です。
香川さんは女学生の頃、西條八十と会っていた。戦時中、疎開先の茨城県の下館で。そのエピソードは、1992年に自らまとめられた初の著書「ひめゆりたちの祈り 沖縄のメッセージ」(朝日新聞社)に載っている。戦争の現実を記憶する世代のひとり。香川さんは、あらゆる意味で日本の語り部である。
戦争の影は、『赤い鯨と白い蛇』『東南角部屋二階の女』にも射している。
香川 別に意識して選んでいるわけではないんですけど、私の年代の役柄というと、戦争を通ってきた世代になるので、どうしてもそういう過去は背負うことになります。この頃はいろんな人生を潜り抜け、今があるという役が多いですね。大変なんですが、やりがいがある。画面に登場しただけで、過去を滲ませなければならない。
たとえば地方の大きな家の奥さん役だったりしても、そこで子供時代から長年暮らしているような存在感を出すのは難題です。若いときにはなかった難しさですね。『赤い鯨と白い蛇』では、いわゆる認知症の役。以前からやってほしいというお話は、他でも何度かいただいていたんです。
でも勇気がなくて、なかなかお引き受けできなかった。それと私としては、犬を飼ったり、植物を育てたり、自分が何か責任を持つことで、症状がよくなった例を聞いていましたのでね。そんな描き方があってもいいんじゃないかとずっと思っていたんですよ。
完全には治らなくても何かのきっかけで、少しずつ症状が回復することはあるらしいんです。『赤い鯨と白い蛇』の役は、自分の暮らした昔の家に訪れ、だんだんと大切な過去を思い出していくでしょ。そこがとても良かった。私はこういう役がやりたかったんです。テーマそのものを表面に強く出さなくても、背景に浮き上がってくる作品が好きですね。
今でも完成作は、試写のタイミングが合えば御覧になるそう。
香川 自分で映画館に行くこともあります。試写を観るのはあまり好きじゃない、怖くって(笑)。試写会では一番後ろに座って、みんなに分からないように最初に出てくるんです。何十年も経てば冷静に見られるようになるんですけどね。
2008年6月に新文芸坐で一大レトロスペクティヴ上映があった。2冊目の著作「愛すればこそ スクリーンの向こうから」(勝田友巳編/毎日新聞社)の出版記念。香川さんはトークショー以外にも劇場に足を運ばれた。
お世話になった名監督、昔の撮影所を語る機会
香川 何本か観直しましたが、松竹京都で大曾根辰保監督が手がけられた『流転』(1956年)という映画には愛着があります。私にとって初めてのカラー作品で、やったことのない踊りも三味線も1週間くらいで必死に覚えた苦労の思い出もありますけど、役がとっても好きだったんです。わりと受け身の役が多かったのが、師匠のために自らを投げうって尽くす、積極的なしっかりした女性像で、そういう役が珍しかったものですから。
それと田中徳三監督の『疵千両』 (1960年)、あれは過労で撮影の途中、倒れたりしたものですから。ご迷惑かけた作品なのでどんなだったかなあと思って観にいきました。

2008年、香川さんは第26回川喜多賞に選ばれた。「映画を通じて国際間の友好を深め、理解を増すことに努めた業績を記念」して、というのが受賞理由だ。
香川 生前親交のあった(川喜多)かしこ夫人の生誕100年の年にいただけるなんて、光栄で、ありがたかったです。でも私、そんな何もしてないんですよ。2007年の東京国際映画祭の審査委員も「第20回の節目だから」と依頼されまして、皆さんの助けがあったからできたんです。お世話になった名監督のこと、昔の撮影所のことなど、いろいろお話するのも少しは映画界への御恩返しになるかなという気持ちでして……。
トークショーでは大したお話はできませんけど。でも映画って機会があれば何十年経っても観られるのが本当にいいですよね。
長い女優生活を過ごされてきたが、結婚し、出産され、新聞記者である御主人のお仕事について、3年間、ニューヨークへ渡米していた時期もあった。名演を刻んだ、黒澤明監督の『赤ひげ』(1965年)が完成した後である。

3年間の渡米の経験と、帰国後の仕事
香川 アメリカでは、ご近所とのおつきあいもフランクでしたし、普通の主婦として暮らせたことは、大きな経験になりました。お料理もいろいろ教わって(笑)。それまで私、台所に入る時間、なかったですからね。何もできなかったんですよ。だから主婦の勉強を3年間させていただいた留学時期でした。楽しかったですね。
1968年末に帰国。スクリーン復帰作は『華麗なる一族』(1974年)。『男はつらいよ 寅次郎春の夢』 (1979年)のマドンナ役では、アメリカに住んでいた(!)という設定だった。


『春駒のうた』(1986年)を挟み、しばらく映画界から遠ざかるが、熊井啓監督の『式部物語』(1990年) で、20〜50代を演じ分けた豊田四郎監督の『明日ある限り』 (1962年)以来の老け役にチャレンジした。この演技で香川さんは、キネマ旬報助演女優賞に輝いている。

香川 初めて本格的な老け役をやらせていただいて、何かが吹っ切れました。で、また10年くらい映画はないかなあと思っていたら、黒澤監督から『まあだだよ』 (1993年)のお話があったものですから、本当にあのとき嬉しかったですね。また黒澤組に会えるって!

その『まあだだよ』では助監督を務めていた、黒澤組生え抜きの小泉堯史監督からオファーされ、『阿弥陀堂だより』(2002年)に。一瞬ではあるが、周防正行監督の『Shall we ダンス?』(1996年)で、ヒロイン・草刈民代の母親役(ただし写真で!)出演しているのも忘れ難い。


香川 とにかくお話を聞きましょうって渋谷でお会いしたんです。本人がやって来るなんて珍しいって(笑)。だいたい事務所を通すものですが、私は所属はなく、フリーですから、今もそれは普通のこと。写真だけの出演は初めてで、数秒でもダンスのシーンとかあるといいんだけど、って提案してみたんですが、申し訳ありません、と頭を下げられ、写真だけとはいえ誰でもいいというわけにはいきませんから、と口説かれました(笑)。
草刈さんとは一度お目にかかったことはあったんです。日本テレビの『知ってるつもり』という番組で。私は第一志望がバレリーナだったものですから、草刈さんのお仕事、しかも初めての映画ならばいいかなと思って、それで写真出演したんです。
世代を超えて作る映画の現場
ちなみに、香川さんの可憐なバレリーナ姿は『東京のヒロイン』 (1950年)で観ることができます。『東南角部屋二階の女』もそうだが、香川さんは、是枝和裕監督の『ワンダフルライフ』(1999年)、篠原哲雄監督の『天国の本屋 恋火』(2004年)など、新世代の監督たちとの仕事にも積極的だ。つまり身も心もとっても、若いのである。


香川 篠原さんとは、そのお話をいただく何年か前に、私が出席した神戸の映画祭でお会いしたことがあるんです。そのときに篠原さんの『草の上の仕事』が受賞して、これからもがんばってくださいね、とお話していて。そういうご縁もあって、篠原さんの作品は『はつ恋』(2000年)を拝見して、いいなあと思ってました。是枝さんはデビュー作『幻の光』 (1995年)が良くってね。映画のお仕事は、できるだけで幸せですが、若い方と御一緒するのは毎回ワクワクします。



ところで名著(……と呼びたい)『愛すればこそ』のエピローグに、「コメディーをやってみたいです、大人の」と香川さんは記されていたが、これは今後、ぜひ観てみたいものだ。どんなコメディーがお好きなのだろう?
香川 アメリカ映画でいえばビリー・ワイルダー監督の作品。感覚が洒落ていて大好きです。それと日本にも木下さんがいらっしゃいましたね。木下惠介監督。『お嬢さん乾杯!』(1949年) なんか楽しかったなあ。大好きな原節子さんも出ていらして。モダンでいて、品があるでしょ。映画はやっぱり、品があってほしいですよね。成瀬巳喜男監督の『驟雨』 (1956年)。 あの役も大好きでした。


優しく、しかし、確かな意志を込めて、語りかけてくる。この道に入って60年目。すでに次回作が決まっていたようだが、「まだ明かせなくて」とふんわりと微笑む香川さん。芳醇な歴史を身にまとい、それに安住することなく自ら更新し続ける、現在進行形の、稀有な女優である。

キネマ旬報2008年10月上旬号掲載記事を再録!