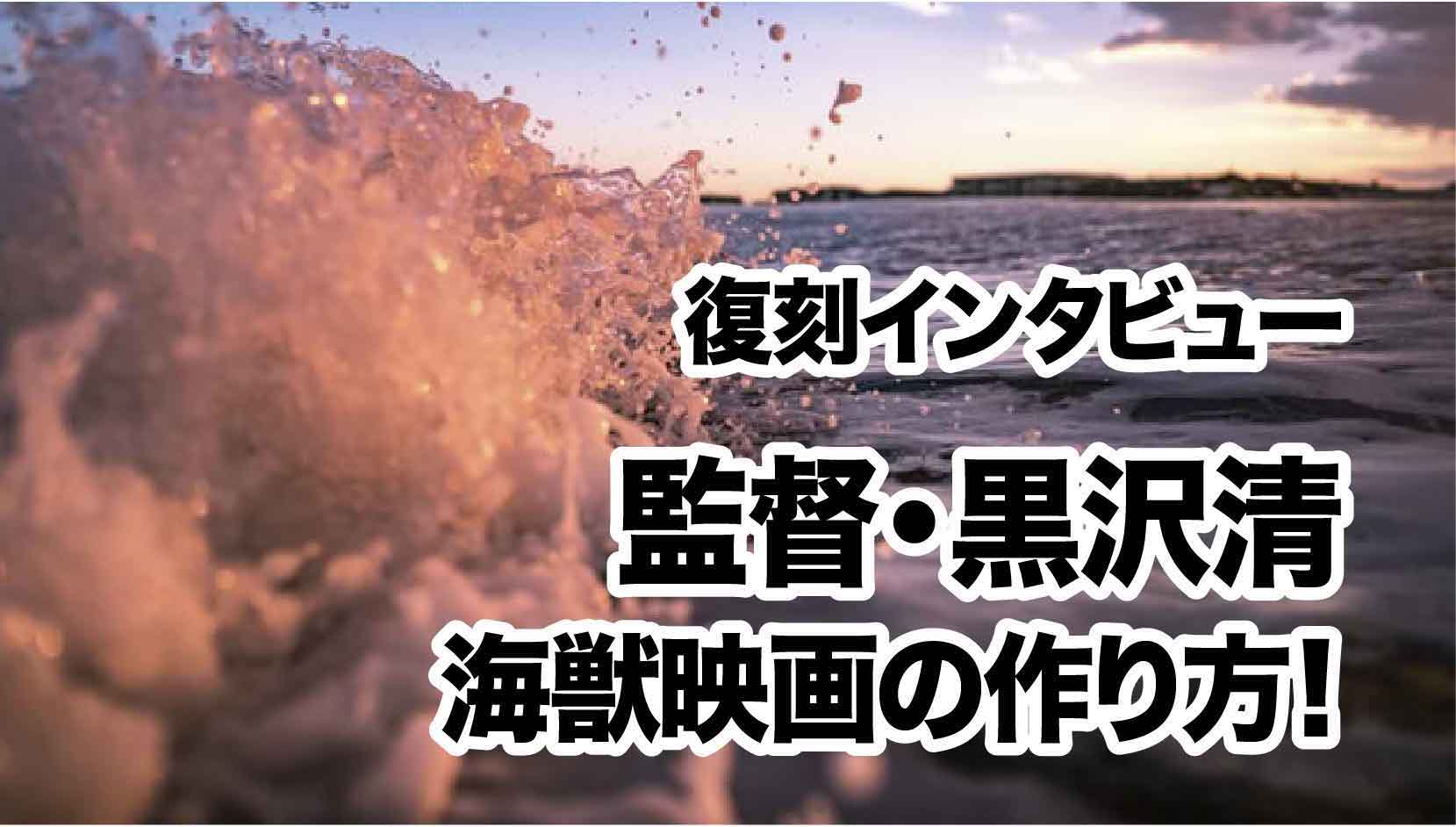黒沢清監督のインタビュー記事を復刻掲載です!

黒沢清監督の映画『スパイの妻』が10月16日に公開されます。先のヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を受賞した映画です!

そんな黒沢監督、2013年の映画『リアル〜完全なる首長竜の日〜』公開にあたり、行われたインタビューにて怪(海)獣映画についてあれこれ語っていただいた内容がとっても面白い!

「首長竜を出したかったんですよ」と言う監督が解説する、怪(海)獣映画の作り方!をどうぞお楽しみください!

黒沢清プロフィール
くろさわ・きよし
1955年兵庫県生まれ。大学在学中から8mm映画を撮り始め、1983年『神田川淫乱戦争』で商業映画初監督。
『CURE キュア』 (1997年)をきっかけに、以後の作品は世界的に注目を集めている。
2012年の「贖罪」はTVドラマであるにもかかわらず、ベネチアを始めとする世界各地の映画祭で公式上映された。その他の作品:『地獄の警備員』(1992年)『回路』(2000年)『叫』 (2007年)『トウキョウソナタ』(2008年)『リアル〜完全なる首長竜の日〜』(2013年)『クリーピー 偽りの隣人』(2016年)『旅のおわり世界のはじまり』(2019年)など。新作は『スパイの妻』(2020年10月公開)
データ『リアル~完全なる首長竜の日~』
2013年
原作:乾緑郎「完全なる首長竜の日々」
監督:黒沢清
出演:佐藤健、綾瀬はるか、中谷美紀、小泉今日子、オダギリジョー、染谷将太、堀部圭亮、松重豊
インタビュー
(取材・文 轟夕起夫)
──佐藤健×綾瀬はるかのダブル主演、第9回「このミステリーがすごい!」で大賞を受賞した乾緑郎の『完全なる首長竜の日』の映画化です。佐藤さんはよくインタビューで、「他の映画とは“ルール”が違い、既成の決まりごとから自由な作品」だと語られていますが。

潜在意識の入れ子構造
黒沢 そうですか。たしかに原作からしてなかなか厄介というか、読む者を惹きつけつつ混乱させる小説でしたので、脚本の“ルール作り”は大変ではありました。近年、『シャッターアイランド』(2010年/マーティン・スコセッシ監督)や『インセプション』(2010年/クリストファー・ノーラン監督)など、現実と潜在意識の入れ子構造の作品が発表されましたが、一度はトライしてみたいジャンルだったんですね。


でも、自分から進んで手を上げるには勇気が必要で、平野隆プロデューサーからこの原作を渡されたときは「ついに来たか!」という感じでした。
──映画のジャンルとしては、かなり古くからあるものですよね。
黒沢 それこそ『カリガリ博士』(1920年/ローベルト・ヴィーネ監督)だったり、ひょっとするともっと過去へと辿れるかもしれませんね。

というのは、登場人物がハっと気づくと時間や場所が全く変わっているシチュエーションって、現実に起きたら大変なんですけど、映画だと当たり前のことじゃないですか。むしろ、瞬間的にパっと時空間が変わってこそ映画表現たり得るわけで、「映画で物語が語れる」と気づいたときから作り手は皆、まずやろうとしたことでしょう。
逆に、なめらかに時空間を繋げていくほうが難しかったりする。つまり、観客を混乱させるのは至極簡単で、どうすれば映画としては整然と「混乱している登場人物」を描けるのかを探っていきました。
一種のSFファンタジーと割り切る
──ここで映画の設定を要約しますと、幼なじみで恋人同士の浩市(佐藤健)と淳美(綾瀬はるか)がいて、1年前、漫画家の淳美は自殺し、命を取り止めたものの昏睡状態になり、“センシング”という最新医療によって彼女の脳内に浩市が入っていく、と。観客は、昏睡状態の淳美と意志疎通を図る浩市を主軸に見ていくことになりますね。
黒沢 ええ。浩市はどれが現実で、どれが意識下の出来事なのかが混乱していく。これを混乱させずに見せるのって本当に難しいんですよ。自分としては初めての挑戦だったので原作に乗っかりつつ、一種のSFファンタジーであると割り切って、この映画のルールとしては“センシング”の装置を通せばこうなるんだと、それ以上のリアリティを追求することはやめました。
──国立先端医療センターで精神科の医師(中谷美紀)と脳神経外科医(堀部圭亮)が“センシング”を担当しているんですが、いかにもな実験者、科学者然とした人たちが登場すると、黒沢清ファンは「あ〜、来た来た!」とアガります(笑)。
美術は現実にありそうな装置
黒沢 装置の造形は美術の清水剛さんにお任せしたんですけどね、僕の当初の妄想ではもっとマットドクター風な、フランケンシュタイン博士の実験室みたいな世界だったんです。でもそれをやると確実に映画そのものが混乱すると思いまして(笑)。
で、もう少し現実にありそうな装置をいろいろリサーチし、それを単になぞってもつまらないので、現在のMRIを少し飛躍させた架空の装置を作ってみました。
──『LOFT ロフト』(2006年)以来の出演、劇中、中谷さんの存在が怪しくて怪しくて目が離せませんでした。


『LOFT ロフト』は黒沢清監督の日韓合作ホラー映画です。出演は中谷美紀、豊川悦司、西島秀俊、安達祐実、鈴木砂羽、加藤晴彦、大杉漣、ほか。
中谷美紀の一貫した怪しさ
黒沢 怪しいですよねえ〜。最終的には中谷さんの一貫した怪しさが、この映画のトーンになったなと僕は考えてまして。浩市は、先ほども述べたように淳美の意識の中に入って以降、現実世界との区分がつかなくなり、奇妙なことが日々起こっていく中、中谷さんの怪しさだけが常に安定して一貫しているんです。
それは狙った演出で、僕の目論み以上に上手くいった気がします。中谷さんがあれだけ怪しく安定しているから、観客も安定感を持続できる。もし中谷さんがノーマルな芝居をしたら、観客はどこに乗っかっていいのか、逆に混乱すると思いまして。
もちろん、異常すぎても気になって失敗なんですけど、いい塩梅で現実と非現実の狭間を埋めてくれた。彼女の存在がこの映画のベースを作っていると言っても過言ではないです。
──では、主演の若き2人を演出されてみて、いかがでしたか。
勢いのある俳優のパワー
黒沢 やっぱり、勢いのある俳優って、いいですね(笑)。ある種、何をやっても成立してしまうパワーが漲っている。脚本を読んで分からないところもあったでしょうし、僕に質問しても解答が曖昧で困ったはず。それとかなりのシーンがCG合成を前提としていて、現場ではどうなるか分からない状況の中、不確かなまま演じることが多かったんですが、それらを吹き飛ばす勢いが2人にはあるんですよ。
佐藤さんはとても献身的な得がたい俳優で、綾瀬さんはかなり考えて演技をされる方なんですが、いざ現場では何事にもトライしてくれ、ありがたかったです。あの天真爛漫さ、ムードメーカーな資質は生まれ持ったものだと思いました。
八丈島のロケ効果
──八丈島でロケーションされていますが、雰囲気バツグンの場所ですね。
黒沢 今回初めて行ったんですが、東京からけっこう近くて、飛行機で40分くらいで着いちゃうんです。奇妙な島でした。行って分かったことなんですけど、綺麗な砂浜は一切なく、噴火して溶岩で出来ていて、ビーチがないものですから、観光客もそう来ない。絶海の孤島みたいな雰囲気でした。
一説によると『マタンゴ』(1963年/本多猪四郎監督)も、八丈島で一部ロケをしたという話がありますね。僕、『マタンゴ』は大好きな映画なんです。

──ある意味、本作は『シャッターアイランド』であり『マタンゴ』で、そこで黒沢清的な“贖罪の物語”が展開する、と言ってもよい。
黒沢 ん、まあ〜、そうですね(笑)。
──VFXスーパーバイザーは長い付き合いの浅野秀二さんの担当で。
VFXと首長竜
黒沢 大学の後輩で、彼も元は自主映画の作家だったんですが、気がつけば『回路』(2000年)以来、ほぼ毎回何らかの形で彼の力を借りています。


黒沢清監督の『回路』は、出演:加藤晴彦、麻生久美子、小雪、有坂来瞳、松尾政寿、武田真治、風吹ジュン、役所広司、哀川翔、ほか
今回は『回路』どころではなく、目一杯、僕のキャリアの中で最も多くCG合成を使いましたね。撮影が終わってから半年ぐらいその作業にかけましたから。いろいろとやってみたかったことに挑めました。思いきって言えば「日本映画でも、やればできるじゃないか」という感じでしたね。
──その最たるものは首長竜ですね。
黒沢 あれを出したいというのは、僕の強い願望です。プロデューサーには「そんなの出して、本当に大丈夫ですか」と言われましたが、絶対に出したいと粘りました。浅野も一番こだわってくれて、竜の造形とか、そのへんはある程度予想がついたんですが、白眉は水の表現ですね。水から上がって来る首長竜、その全身水浸しの映像がいい。
CGでの水の表現
スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジュラシック・パーク』 (1993年)や『ロストワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)の頃はまだ、水の表現は難しかったんですよ。だから、プレシオサウルスは出していないんじゃないかな。水からザバーッと出て来る表現には限度があったんです。


その後、ハリウッドも進化して今や大変な技術ですけど、その最先端の水の表現を取り入れてみました。ぜひ、専門的に見ていただきたいのは、首長竜がザバーっと水から現れ、全身からしたたって広がってゆくあの水です。全部CG合成なんですが上手くいきました。
──地下から上がって来る瞬間、興奮しました!
怪獣の大きさ設定
黒沢 やりたかったんですよ、あれが。念願が叶いました。オブセッションというほどのことはないんですけど、僕は10mくらいのモノが襲って来てほしいんです。たとえばスピルバーグの『ジョーズ』 (1975年)の鮫がそうですね。

怪獣級の50mになるとちょっと興味が薄れる。スピルバーグもホオジロザメやティラノザウルスみたいに10mくらいのモノが好きですよね。ティガー戦車もそう。だいたい10mくらいのモノが人間を襲って来る。僕もそれが好きで、とにかくやりたくて、ただ、あの大きさのモノはそう簡単には出せない。
ポン・ジュノが『グエムル-漢江の怪物-』(2006年)で見事にやっていた。

なんでこの手の題材を日本映画ではやらないんだろうと忸怩たるたる思いがありまして。後ろから追いかけられる恐怖感がいいんですよねえ。ゴジラ級のモンスターはまた別の表現領域で、ビルの向こうから姿が見えて、手前は何百人と逃げている。2mくらいですとエイリアンや恐竜ヴェロキラプトルとか、あとは怪人のサイズ。レザーフェイスもそうですが2mのサイズは以前、『地獄の警備員』(1992年)でやったことがあって、柱の影からヌッと出て来ると明らかに人よりデ力いという、これも僕の好きなサイズ。
で、今回5m以上10m以内のやつがやっと出来たと。


黒沢清監督作『地獄の警備員』は出演:久野真紀子、松重豊、長谷川初範、大杉漣、ほか。
現実とインナーワールド
──嬉しいことに『地獄の警備員』の殺人鬼、松重豊さんもキーマンとして出演されていますが、劇中、主人公の浩市は現実とインナーワールド、双方の見境がだんだんとつかなくなっていく。このシチュエーションに関する表現で苦心された点は?
黒沢 あまりないです。いや、挑む前は「これは難儀だぞ」と構えていたんですね。でもあまり神経質にならなくてもいいのかもと考え直しまして。というのも、現実とインナーワールドは、物語的には明確に違うんですが、映像にしたら見え方はどちらも変わらないんです。
そもそも映画そのものがどこかインナーワールドっぽいじゃないですか。映画館のスクリーンの中で生起していることって、現実と似ているけれど、“別次元の世界である”と我々は自然と認識している。だから少々の混乱は平気で、画面にもし首長竜が出て来たら「意識下の話」と了解することができる。これは映画独特の面白さで、我々はスクリーンに映っている出来事はいわば、半覚醒の状態で眺めているわけですよ。
──だからこそ、デタラメなビジョンが許されるところもありますね。
客観描写を極力減らす
黒沢 デタラメといえば登場人物たちの現実をどこまで見せるか、脚本段階でけっこう悩んだところでした。下手をすると全部がデタラメに見えてしまう。意識下で大層なことが起きてはいても現実は、“センシング”の装置をつけられて横たわっているだけなんですから。その姿を、医者が心配そうに見守っている。こういった客観的な現実をどこまで見せるべきか、ずいぶんと悩みました。で、結局けっこうカットしたんですよ。要するに、こういう題材の場合、客観描写は極力減らしたほうがいい、というのがやってみた僕の結論です。『インセプション』でも登場人物たちが寝ているシーンが一番、観客にツッコまれそうなところじゃないですか。「こんなので大丈夫なのかよ、おい」って(笑)。あれに近い感じですね。意識下よりも現実の扱いのほうが僕には難しかったです。

──黒沢さんが敬愛されているリチャード・フライシャー監督の『ミクロの決死圏』(1966年)はどうですか?

黒沢 あれは上手いです。あれだけ体内ですごいことが起きつつ、現実というか、外では医者たちがなんとなく見守っているだけなんだけど、違和感なく繋いでいる。まあ、その描写に今回初めてチャレンジしたわけで、やりながらいろいろと学びました。
──脳内に入るといえば、『マルコヴィッチの穴』(1999年/スパイク・ジョーンズ監督)という作品がありましたが、今回の映画全体が、黒沢さんの頭の中という考え方もできますよね。
ファンタジー
黒沢 僕の頭の中、その全てが映し出されているかは分かりませんけど、映画というひとつのファンタジーとシンクロしていることはたしかですね。そういう意味で、僕が付けた題名ではないんですが、“リアル”ってタイトルは意味深です。どこにリアルがあるのか。全部がリアルといえばリアルなんですね、経験する者にとっては。極論するなら、この世にリアルでないものなど、何ひとつないとも言える。
──夢で経験したことも、リアルといえばリアルだと。ところで、黒沢清的な悪夢に慣れ親しんできたファンからすれば、ラストの肌触りは、「また違った領域へと我々を運んでくれたなあ」と、そんなふうに感じました。
黒沢 『インセプション』も『シャッターアイランド』も、あるいはこの手のジャンルって「これも別の夢かもしれない」みたいなのがひとつの定番になっているじゃないですか。なので僕は最終的には、明快で晴れやかな終わり方にしたいと。もちろん、解釈は観てくださった皆さんの自由ですが。
──これは、黒沢清流の王道のラブストーリーとも言えますね。
黒沢 そうなっていれば、嬉しいですね。いろいろとメチャクチャなことが起こりますが、この2人を突き動かしているものは精神的な、いわば愛に支えられているんだろうと。そんな単純な原理に準じ、物語を綴ってみました。
──ただし、その愛のためには相手の、もしかしたら自分の見たくないものも直視しなくてはならないのがミソで。
ラブストーリー
黒沢 ええ。今回は佐藤さんと綾瀬さんという、キャスティング的には分かりやすい組み合わせですが、僕はこれまでもラブストーリーでは一貫しているんですよ。とても単純明快なところがある。バカみたいといえばそうなんですけど、今回も知らず知らず“地”が出てしまいましたね。つまり、男が女を、女が男を思う気持ちは最初から最後まで絶対に変わらない。強く思っているから混乱するし、相手が信じられなくなったりし、でも途中でやめることはなく、最後まで思いを貫き通す。
『回路』だったり、『CURE』 (1997年)や『叫』 (2007年) なんかもそう。

で、家族が出て来ると関係性が冷やかになる。だから今回も気持ちがいいくらい、浩市の母親役の小泉今日子さんが冷淡なキャラ(笑)。僕はああいう冷たい関係が好きなんですよね。家族間はクールだけども、愛し合う者同士は反対に、揺るぎなく結ばれている。
──万が一、この映画みたいなシチュエーションになったら監督は、相手の意識下を覗いてみたいですか?
黒沢 基本的には絶対見たくない。でもそうしないと救えない、前に進めないなら、勇気を出して相手の意識下に入って行くかもしれません。赤の他人だったらいいですが、知っている人の意識なんて見たくないですよ。関係ないかもしれませんが、僕、ツイッターもフェイスブックも一切やってなくて。相手の本音が出ちゃいそうじゃないですか。本音とか聞きたくないんですよ。褒められていてもイヤで、なんか構わないでほしいというか。「自分のことを思っている」と考えだけでイヤな感じがして。だからごくごく表面的な付き合いがいいですね(笑)。あるいは話すならば、フェイス・トゥ・フェイスでとことん語り合いたいです。

映画秘宝2013年7月号掲載記事を改訂!

黒沢清監督の関連記事のご紹介!監督作『アカルイミライ』についての記事はこちらにあります。