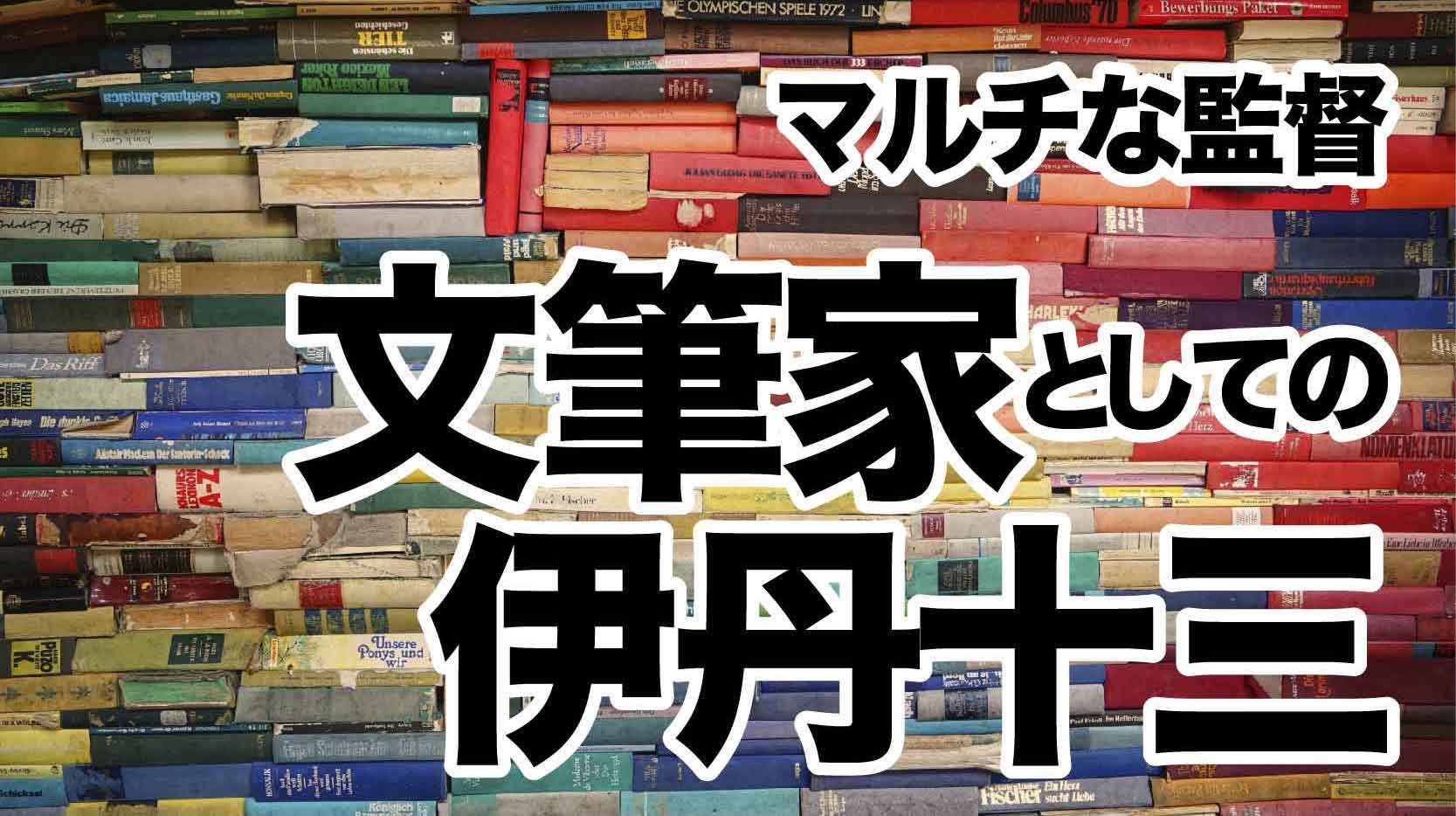極めてマルチな監督・伊丹十三の、文筆家としての仕事に注目します!
マルチな趣味人・伊丹十三
余談から始めたいと思う。伊丹作品の中に『二日酔の虫』なる短編があるのを知ったのは、五味一男氏に取材したときのことだった。日本テレビ『クイズ世界はSHO by ショーバイ!!』『投稿!特ホウ王国』『マジカル頭脳パワー!!』『速報!歌の大辞テン!!』といった人気番組の総合演出で、ヒットメーカーとして“10割打者”の異名をとった方だ。
で、その『二日酔の虫』の話なのだが、かな〜り昔、伊丹十三が『お葬式』を撮るずーっと以前にテレビ番組「11PM」にて発表した前衛的短編(カフカ風) だそうで、若き五味氏はこれを見て感銘を受け、テレビの世界へと飛び込んだのだという。

『二日酔の虫』は、厳密にいえば伊丹作品には入らないのかもしれない。ま、おそらくは、ちょっとした遊び心で作ったものだろう。ところでもう一本、伊丹十三には『ゴムデッポウ』という自主製作の短編映画があった。
俳優の世界に踏み出したばかりの、まだ“一三”と名乗っていた頃のこと。家の中で西部劇ゴッコよろしく、ワイワイ仲間たちとゴム鉄砲に興じたり、外に買い物に出かけたり。手持ちキャメラも一緒にフラフラ。
そこにはのちのヒットメーカーの風情などまったくなく、『二日酔の虫』を作ったときのスタンスにも通ずるであろう、好奇心の赴くままに振舞うマルチな趣味人の顔がある。
さてそうした趣味人としての顔は、映画監督においても大いに見出されたものだが、それ以上に存分に発揮されていたジャンルがあった。
文筆家=伊丹十三だ。
文筆家・伊丹十三
処女作となったのは1965年の「ヨーロッパ退屈日記」。

俳優として所属していた大映を退社後、雑誌「洋酒天国」にて小文を発表し、連載は雑誌「婦人画報」に受け継がれて1冊の本へとまとまった。手持ちの文春文庫のあと書きによるとイキサツはこうである。
「外国から帰ると「文藝春秋」から原稿の依頼があった。生まれて初めて文章というものを書いた。これが没になった。うちには向かないというのである。「洋酒天国」のような雑誌だとピッタリくるのだが、ということであった。くだくだしいことを略すと、その「洋酒天国」に山口さんがいたのである」
山口さんとは“江分利満”こと作家の山口瞳で、最初の原稿に「ヨーロッパ退屈日記」とタイトルをつけたのも氏だ。ロンドン、マドリッド、パリ……まだまだ外国旅行が珍しかった時代に何度となく渡航していた伊丹十三は、さながら日本代表のごとき立場で異文化体験を紹介している。
映画、服装、料理、音楽、語学などについて、単に迎合するのではなく私見を交え、あくまでも軽妙な筆致で。
この渡航はニコラス・レイ監督 『北京の55日』 (1962年)、リチャード・ブルックス監督『ロード・ジム』(1965年) への出演のためでもあったわけで、一日本人俳優の目より眺められた、外国映画の現場ルポとしても読める。


伊丹十三が座談の名手であったのは、よく知られているところだが、談話を文章にまとめる才能もまたひときわ際立っていた。それを楽しめるのが「小説より奇なり」と「日本世間噺大系」である。

「小説より奇なり」には、文豪 (井伏鱒二!)、俳優、著名人らが登場し、ハゲ談義に興じたり、“ペットは犬か猫か”をめぐって論戦を繰り広げる。
また、「日本世間噺大系」はその市井篇といったカンジで、女性たちによる生理座談会、蜜柑の正しい剥き方など雑学的ヨタ話が、身辺エッセイとともに嬉々として並べられている。
その興味の触手の伸び行く先は硬軟、縦横無尽に飛び散らかって、「女たちよ!」「再び女たちよ!」「女たちよ!男たちよ!子供たちよ!」の連作では、女性論、育児論にまで筆は及び、ついには男という生き物の在り方への根本的懐疑、という難問へと辿り着く。


日本、ならびに日本の男は、いかにして自らの幼児性を克服するかーーこれは最後まで伊丹十三を捉えていた大きなテーマのひとつなのだが、ターニングポイントとなったのは、精神分析学者・岸田秀氏との出会いだろう。
フロイト心理学を発展的継承した岸田理論のいわゆる“幻想論”が、心理学的問題のみならず、社会現象一般に対しても快刀乱麻を断つその著書「ものぐさ精神分析」。

文庫版のあと書きに伊丹は、初読の衝撃を「私は一気に催眠術をかけられたものとしての自分を外側から見る視点を得ることができた」と記している。
岸田氏との「哺育器の中の大人」や、ジャック・ラカン研究の第一人者、佐々木孝次氏との「快の打ち出の小槌」と続けざまに精神分析講義本をものし、1981年には月刊誌「モノンクル」も発刊するが、これは1年もたずに廃刊。

のちに「自分たちよ!」にまとめられた内容を見ると、精神分析のスタイルで挑む人生相談(南伸坊氏のイラスト付き)。フジテレビ『小川宏ショー』での〈死体持参花嫁事件〉討論の全収録。
それから栗本慎一郎×金井美恵子×佐々木孝次による座談会〈サガワ君の場合〉。さらに映画、人物、写真、漫画について論じあげ、まったく目が回るくらいに脱ジャンル化が夥しい。
とりわけ、黒澤作品の名スクリプター・野上照代さんに蓮實重彦氏と共同インタビューした〈黒澤明、あるいは旗への偏愛〉は、言ってみれば記号学的視点による映画論であり、岸田理論同様、蓮實氏のその“表層批評”が伊丹十三に多くのものを与えた事実を示している。
ある意味では微笑ましいほど新潮流の言説に影響されやすい人であった。監督デビュー作の『お葬式』も、表層批評との出会いがなければ生まれなかった(参照:「ユリイカ」1997年10月号 四方田犬彦氏〈映画史的記憶から解放されて〉)。きっと説明原理が好きだったのだ。説明してもしきれない世界の成り立ちが。
精神分析も表層批評も、自分を呪縛する何ものか(例えば父・伊丹万作!)からの解放を求めた結果だったようにも見受けられる。

父・伊丹万作も多才!映画監督であり俳優、エッセイスト、挿絵画家の一面も!
いつしか「小説より奇なり」の頃の雑食さは影を潜め、それは少し残念だったが、1985年刊の「フランス料理を私と」ではホスト役として、自分で作ったフランス料理をふるまい、またまた多分野のエキスパートたちとあらゆるテーマについて語りおろして、もはや総合雑誌の編集長のごとく機能していた。

振り返ってみれば伊丹十三は、極めて〈雑誌的〉な人であった、と思う。
彼の作った映画がそうだ。書物がそうだ。生き方がそうだ。あらゆる事柄を興味の対象にして食らいつき、そして時々の異才(岸田、蓮實、そこから繋がる黒沢清、周防正行、近年では三谷幸喜)の仕事に着目し、自ら媒介となってクローズアップした。
多種多様な人々との交流を望んだマルチの男。伊丹十三がいなければ、『マジカル頭脳パワー!!』だってなかったかもしれないのだ。その影響はこれから、思いも寄らぬ形であらわれてくるかもしれない。
(轟夕起夫)

キネマ旬報1998年3月下旬号掲載記事を改訂!

関連記事、こちらにあります!