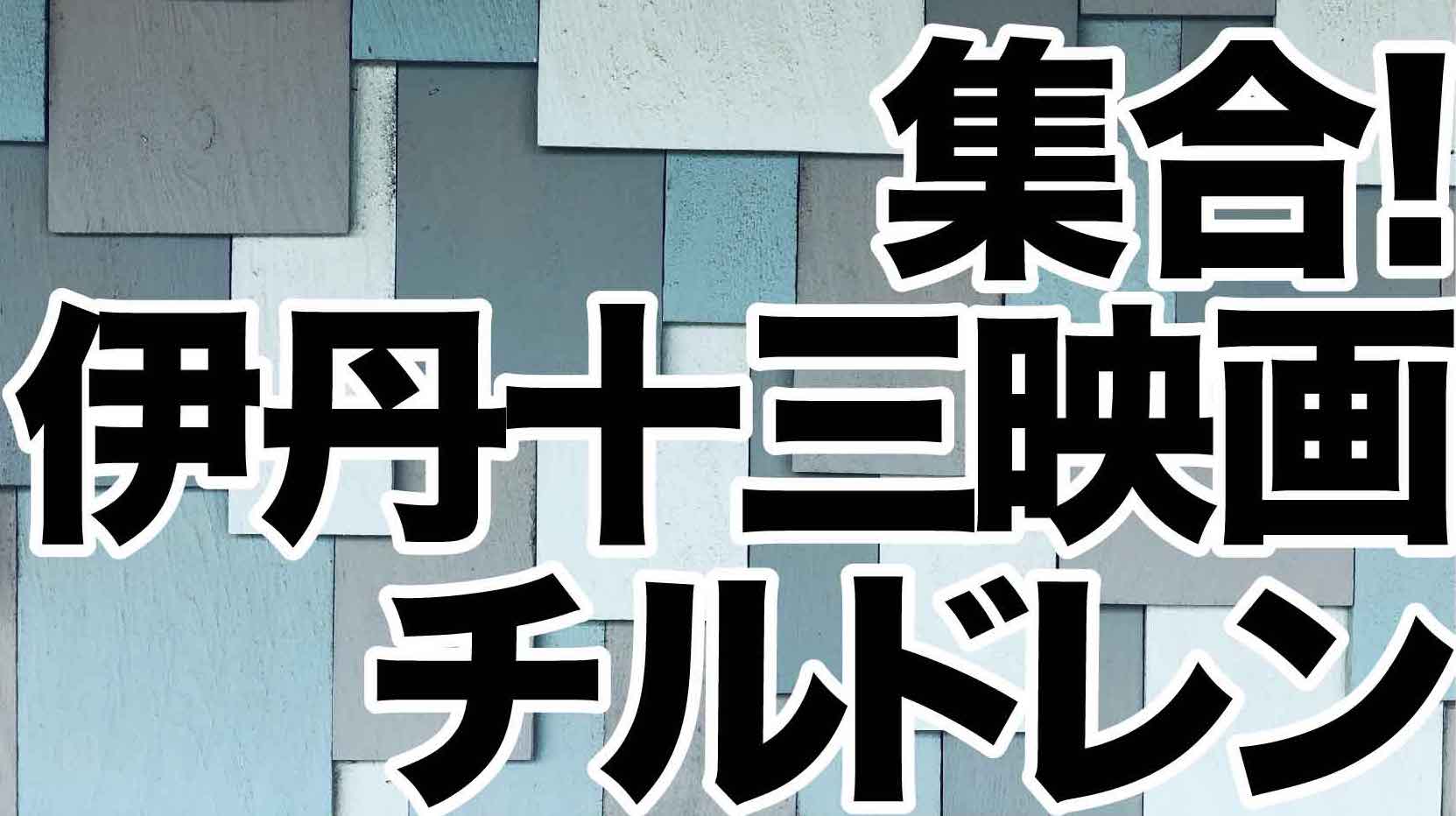伊丹十三(1933年5月15日〜1997年12月)は、その名で新作映画の観客が呼べる監督で、新作映画公開時の広告には「伊丹十三の新作!」がメインで打ち出されました。
多くの観客を魅了した映画に影響を受けた人たちはもちろん多いです!
ここでは、伊丹映画に出演した役者たち、影響を受けた演出家たちをご紹介。勝手に「伊丹チルドレン」とくくらせていただきました!
伊丹十三映画に出た役者・俳優
伊丹組を代表する俳優というと、宮本信子を筆頭に、山﨑努、三國連太郎、津川雅彦の4人がまず挙がるが、脇役の常連俳優では7本出ている加藤善博、続いて6本の高橋長英、5本の不破万作、三谷昇が多い。女優では4本の柴田美保子と朝岡実嶺か。
さて。長編監督デビュー作『お葬式』(1984年)を彩った、バラエティ豊かな面々のことだけでもう延々と書き綴れるが、ともかく、“いい顔”をした老人、大人たちを伊丹十三はそこに集めてみせた。

奥村公延と菅井きんの老夫婦を筆頭に、金子信雄、財津一郎、佐野浅夫、大滝秀治、笠智衆……さらには通夜の席に顔を出す老人会仲間に、日本映画の黎明期から名を成した藤原釜足、香川良介、田中春男、吉川満子の4人を揃えたのは激シブだった。
この傾向は『タンポポ』(1985年)にも見られ、大友柳太朗(これが遺作となった)、加藤嘉、中村伸郎、嵯峨善兵、原泉などが脇を支え、『あげまん』(1990年)の島田正吾あたりまではこういう豊かなキャスティングが可能な時代だったのだ。


かと思えば、『あげまん』に当時 TVキャスターだった石井苗子(クレジットは MITSUKO)を呼び、『スーパーの女』(1996年)、『マルタイの女』(1997年)には伊集院光を起用。


時には意表を突いたキャスティングも。例えば『マルタイの女』の刑事役のとき、伊集院はダイエットで60キロ減量していた体重を伊丹十三の要望で元に戻すことになり、1カ月で30キロ増量した。
刑事役で『マルタイの女』といえば、従来とは違うカッコ良さが滲み出ていた名古屋章も忘れ難い。『ミンボーの女』で伊東四朗のとんでもない怖さを表出させるなど、出演者に違った光を当てて異質な顔を引き出すのも上手かった。

伊丹映画に大抜擢され、頭角をあらわした俳優のツートップは、『タンポポ』の渡辺謙と役所広司。前者は、山﨑努がプロデュースしたピーター・シェーファー作の舞台『ピサロ』 (1985年)で脚光を浴びたのがキッカケに。伊丹は山﨑から依頼され、その台本の翻訳を担当していたのだった。後者は、市川森一脚本のTVドラマ『親戚たち』(1985年)に出ていたのを観て。
もうひとり、『マルサの女』で“マルサのジャック・ニコルソン”と呼ばれる当たり役をもらったのは、大地康雄。この人の場合は、再放送のTVドラマ『深川通り魔殺人事件』(1983年)で川俣軍司を演じていたのを偶然観て決定したのだった。
伊丹十三映画から出た演出家・監督
2011年、伊丹十三の伝説の自主映画『ゴムデッポウ』が東京国際映画祭で特別上映され、ブルーレイ化された。
もう1本、ぜひ探して出してほしい短編がある。『二日酔の虫』という作品だ。これは、伊丹十三が『女たちよ!』に載せた同名エッセイを自ら実写化したもので、簡単に記せば、こういう映像が展開するらしい。

すなわち、二日酔いで苦しむ男がこめかみ近辺に出来物を見つけるのだが、中から紐状の白い物体を引っ張りだしていくうちに完全にそれを出し終え、今度はこめかみの穴に冷水を注ぎこみ、穴を手で押さえて頭を振って洗浄して、スッキリするまでが描かれていくのだ。
まだ『お葬式』で劇場デビューする前、おそらく1970年代初頭のこと。かの深夜のTVバラエティ番組「11PM」の“8ミリ映画特集”なる企画で発表されたそうで、観た人はけっこういる。
例えば『タンポポ』公開時のパンフレットを捲ると、漫画家の長谷川法世が触れており、「ぼくはこの人こそ待ちわびた日本喜劇界の星だと決めた」と記している。
他にも、感銘を受けた結果、「テレビの世界へと飛び込んだ」と教えてくれた人もいた。ずいぶん前に、取材の折に直接聞いた。日本テレビでかつて「クイズ世界は SHOW byショーバイ」「マジカル頭脳パワー!!」「エンタの神様」などを企画・プロデュース、総合演出し、数々の高視聴率番組を放った五味一男だ。
番組放送中にあえてCMを挿入し、視聴者の期待度を上げたり、過度にテロップを入れて笑いを生み出す手法は、当初は『二日酔の虫』のように斬新かつトリッキーで、後発のバラエティ番組にも多大な影響を与えた。
が、今では功罪半ばに感じる部分もある。仕方ない。それがヒット作の宿命だ。重要なのは、とても特異ではあるが、複雑な事案を「口語体で分かりやすくする」こと。伊丹映画はそれを徹底させた。
いや、映画を作る以前、テレビマンユニオン制作の番組( 『天皇の世紀』『遠くへ行きたい』『欧州から愛をこめて』 など)ですでに実践しており、もっと遡れば、エッセイや著作物(の文体)からもその姿勢は明らかだった。

テレビマンユニオンはテレビ番組の企画、制作などを手がける会社です。
前衛と面白さ、わかりやすさは、決して相反しないという大胆なテーゼ。伊丹十三はこれを証明し続けようとした。近年、そんな異才の影響を認める人がまた、だんだんと現れてきた。
高3の春、テレビ放映で『マルサの女』と出会い、録画したものを100回(!)以上観た中村義洋は自らを“イタミスト”と呼んでいるとか。
映画監督を志すキッカケになり、実際に『スーパーの女』の現場では伊丹組の助監督の経験もある彼は、今でもクランクイン前には書籍「「マルサの女」日記」(文藝春秋)を読み返すという。

今年、映画監督デビューし、『モテキ』が大ヒットした大根仁も“伊丹っ子”を自称しており、「「マルサの女」日記」(文藝春秋)を模した「モテ記〜映画「モテキ」 監督日記〜」(扶桑社)を発表するほどの徹底ぶり。


伊丹十三の衣鉢は時を越えて受け継がれている。が、避けられない落とし穴というか、永遠の問題は、ヒットを生み出し続けようとすると、「前衛と面白さ、分かりやすさは、決して相反しないというテーゼ」のバランスが微妙に取れなくなってくること。
伊丹十三もそこで大いに苦しんだと思う。ヒット作あるところには必ず、伊丹的な“栄光と憂鬱”がある。この難題についてもっと深く考えるためにも、『ゴムデッポウ』と並ぶもうひとつの原点、『二日酔の虫』が観てみたい。
(轟夕起夫)

映画秘宝2012年1月号掲載記事を改訂!

関連記事、こちらにあります!