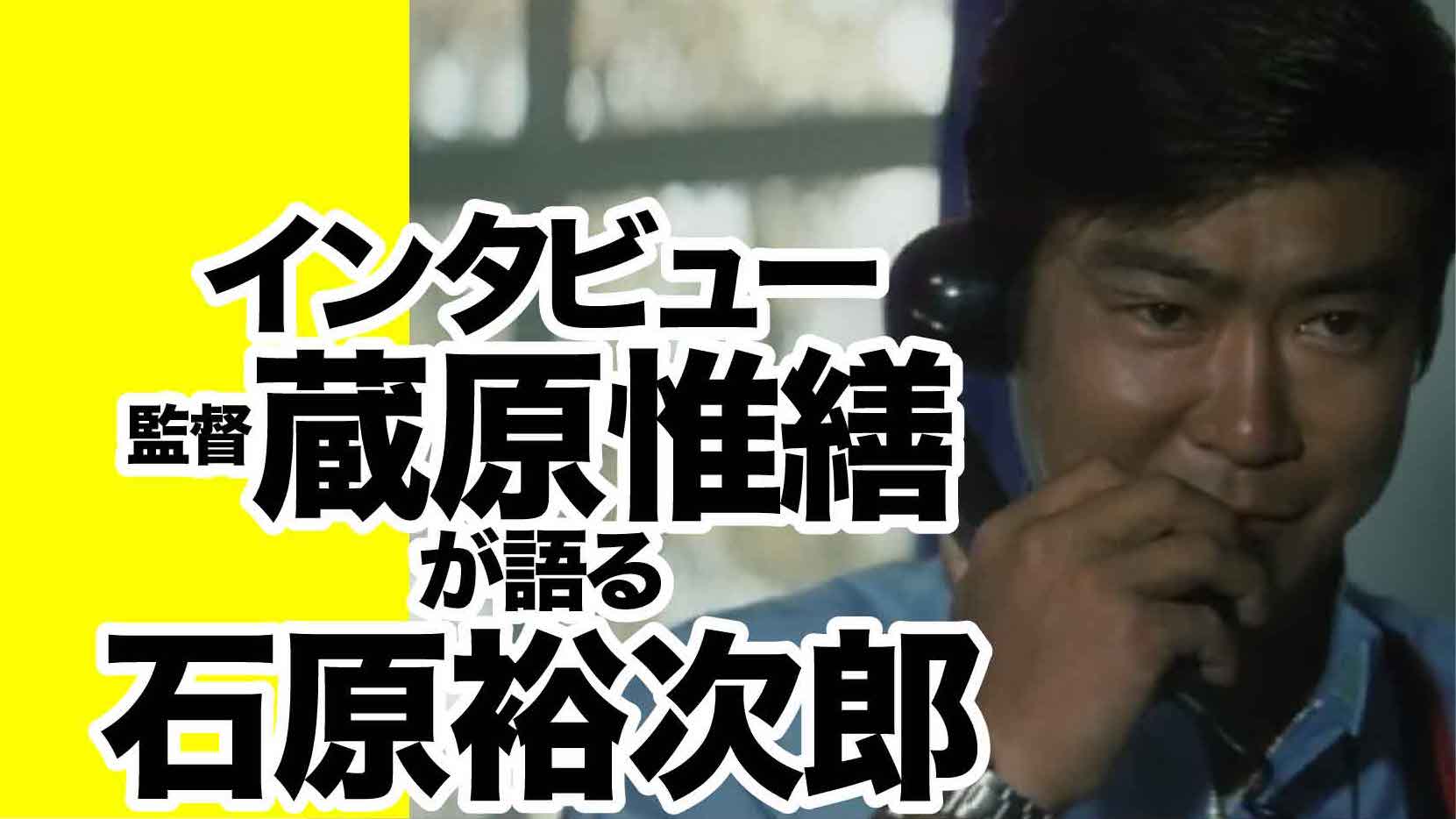蔵原惟繕監督(1927年ー2002年)が生前語った石原裕次郎(1934年ー1987年)。その貴重なインタビュー記事を改訂してお届けです。

初主演作はトリュフォーやゴダールがいち早く褒めた作品に!
どんな映画も「寝かせ具合」で味が出てくる。もともとイイ味が備わっていれば熟成は尚更だ。
たとえリアルタイムの熱狂と興奮に立ちあえなくとも、手にした者のテイスティング、横に添える料理次第でその風味は変わる。
むしろ早すぎた開封ゆえ「失敗」の烙印押された映画に、時価の適正なテイストを与えることだって出来るだろう。それが遅れてきた世代の特権(であり強がり)だ。
一体何の話をしているのか?
石原裕次郎である。この不世出の大スターの残した数多の主演映画を眺めた時、明らかに他とは異質に輝き、もとのイイ味に「寝かせ具合」が加わったものがある、蔵原惟繕監督による1960年代の一連の作品だ。
おいらはドラマー(大ヒット映画『嵐を呼ぶ男』で裕次郎が歌う有名なフレーズ)でも、七曲署のボス(大人気ドラマ『太陽にほえろ!』の役柄)でもない、そこには「21世紀のための裕次郎」がいる。


とはいえ、フルーティな香りと味わいを愉しむには、一度1950年代のテイストにも口をつけてみたほうがよい。
蔵原氏がチーフ助監督を務めていたのが『狂った果実』(1956年/中平康監督)だからだ。

「初めて会ったのは、裕ちゃんが20才そこそこで、こっちが29才のときだった。当時誰もが憧れたアメリカのジェームス・ディーンのように、ある種時代の中から必然として出てきた素材というのかな。彼はそういうタイプの新しい役者……というか、新しい青年像をヴィヴィッドに肉体化していたと思う。初めて見たときその驚きはあったね。
僕はB班で葉山ヨットハーバーで撮影していたんだけど、裕ちゃんは葉山の自宅から現場までヨットで来るわけですよ。そんな役者、以前も以後にもいなかった。すでに持っているワイルドさと育ちの良さね。何か突き動かされる魅力がありました。
時代を呼吸している感覚、それを従来の人間像に閉じ込めずどこまで開放できるのか。だからちょっと常識から逸脱した映画でないと彼はハマらないと思った。その点『狂った果実』はぴったりでした。
時代の中である幸福な出会いを果たした作品だった。批評家時代のトリュフォーやゴダールがいち早く褒めたのもよくわかりますよ」

フランスの映画監督、フランソワ・トリュフォーとジャン=リュック・ゴダールについては、こちらのドキュメンタリー映画のレビューが参考になりますヨ。
「太陽族映画」といういかにもなブランドを蹴散らすほど、のびのびとしなやかに動きまわり、一回性の輝きを強烈に焼きつけた裕次郎。
新たに出現したこの彗星をスクリーンの中に掴まえるため、撮影や編集の方法論に刷新が訪れた。いや、作る側の意識が否応なく変えられたのだ。
「ヨット上のシーンは、ミッチェル(注:大型の撮影機)なんて長大で重厚なカメラではとても追いきれず、こんなもん捨てちまえって気分になった(笑)。アリフレックス(注:ミッチェルに比べ軽量で廉価な撮影機)がまだなかった頃でしょ。一番軽いアイモ(注:当時の映画用では最小撮影機)を担いでキャメラマンとボートに乗って動きを追いかけた。アイモだと躍動的に、しかも持続して撮れるからね。
つまり僕らが手持ちで覗くカメラの目がそのまま画面になったんだ。瞬間瞬間現れては消えていく、彼の発散するサムシングを捉えようと、自分の目線とカメラが一体化して裕ちゃんを見つめていった。それはあとあと僕の映画の方法論にまでつながっていくわけですね」
それまでのアクション・ドラマの常識を壊す共犯者
ジャック・ケルアックの「路上」(注:タイトルは書籍により「オン・ザ・ロード」)に代表されるビート文学に傾倒し、ソニー・ロリンズ、マイルス・デイビス、マックス・ローチ(1964年の『黒い太陽』では音楽を担当!)といったモダンジャズの洗礼を浴びていた蔵原氏と、この時の裕次郎の存在は、小気味よくクロスしていたに違いない。




まるでビートニクの始祖、ニール・キャサディのごとく自由闊達な精神を体現していた裕次郎。

ニール・キャサディは、先に登場の、ジャック・ケルアックの小説「路上」の登場人物のモデルになったとされるヒッピーコミューンで生活していた人!
勢いは止まらない。『狂った果実』の翌年、蔵原氏は彼の主演を得て、『俺は待ってるぜ』(水の江滝子製作)で監督デビュー作を果たす。映画は大ヒットした。

「こう言葉にすると味もそっけもないけれど、僕らの内なる〈脱出願望〉を裕ちゃんに託していましたね。海の向こう側に広がる、しかし手には触れることのできない、当時の若者たちの孤絶した状況や鬱積した心情を。
それを描くのにどういうスタイルがいいか……叙情性ではなく乾いたアンニュイっていうのかな。この主人公は実際には向こう側に行けないわけだから、アンニュイな空気感を全体の息づかいとして出していくスタイルにした」
そう。ヨコハマのバーのカウンターに立つ裕次郎。兄とブラジルに渡ろうとし、今か今かと戻りを待っている。だが兄は来ない。ヤクザの組織にとうに殺されていた。二谷英明との壮絶な格闘シーンを、この新人監督が3日間徹夜して撮りあげたのは語り草である。
「2日目にスタッフには〈もういいんじゃないか〉って言われた。それまでのアクション・ドラマの常識からいったら、ラストの格闘はもっと単純でよかった。
でもあれは僕の中では、えんえんと殴り続けていく必然性があったんですよ。兄を殺され組織に復讐する際の、あの内側から沸き起こってくる憎悪、それは自分の置かれている状況への苛立ちでもあって、そうした憎悪をアクションへと昇華させたかった。
格闘の過程で主人公の怒りがエスカレートしていき、しかし殴っても殴っても解消しきれない、その長さが必要だった。本当はもっと激しくしたかった。
それを泣く泣く10カットほど削って、それ以上削れなくって、孤立無縁になって押し通そうと思っていた3日目、ひとりセットで思案していた僕のうしろから裕ちゃんが〈監督、やりましょうよ〉と言ってくれた。
彼も自分の肉体の中で憎悪の表現がもっとあるべきだと感じていたんでしょう。
ああ、この男とこれからも映画を作っていきたいなぁと思いましたね」
だが、大ヒットが裏目に出てしまうこともある。続いて裕次郎主演で『風速40米』『嵐の中を突っ走れ』(1958年)を担当するが、これは蔵原氏にとっては押しきせの企画に過ぎなかった。


その鬱憤を晴らすかのように川地民夫主演の『狂熱の季節』(1960年)でジャパニーズ・ビート魂を爆発させた。
「1本当たると類型化した企画がどんどん出てくる。突然4番打者みたいな立場にさせられて、何本か、やっぱり意に沿わない形になった。
プロとしてテクニックを駆使するだけで、裕ちゃんに手を付ければつけるほど嘘っぱちになってしまった。裕ちゃん自身の気持ち? まだまだ〈たかが映画〉と思っていたんじゃないかな。〈俳優は男子一生の仕事ではない〉とよく言っていたでしょ。
でもスターとして虚構の中にどんどん閉じこめられて、イヤだったんじゃないかなあ。鋭い感性の持ち主でしたからね。かといってNOと反抗しないところが育ちの良さなんだけど。
どこかで窮屈な感じはあっただろう。僕はそういう形骸化していく裕ちゃんを見て、何か違うぞ違うぞと思っていた」
ムード・アクションの魅力とはまた別の石原裕次郎へ
で、1962年ーー何が起きた? チャンスが到来した。まず魅惑のメロドラマ『銀座の恋の物語』を作った。

浅丘ルリ子を起用し、裕次郎とどこまでも拮抗するヒロイン像を築きあげた。
そしてロード・ムービー『憎いあンちくしょう』が放たれたのだ。

ポスターの名惹句を借りるならば〈東京→九州、ジープを駆って一六○○キロ! 日本縦断に若さと情熱をぶちまける豪快裕次郎‼〉。
ここに、1960年代を疾走するひとりの監督と選ばれしカップル、さらには〈自動車〉が揃い踏みした。
しかし、なぜ〈自動車〉が?
そのことを説明するために、矢作俊彦氏の美しい文章をここに引いてみよう。
波止場にジャギュアを停め、彼は降り来る雨を口へ受けとめる。そのとき、我々にこの車は第二のヒロインのように見える。主人公が女に求めているすべてを体現して見せる。ともに雨に濡れ、疲労した主人公をコノリー皮のシートでやさしく包み、主人公も、やがてそっと幌をさしかけて雨から守ってやろうとする相手。(中略)この美しく、切ない雨のワン・カットを決して忘れることはないだろう。浅丘ルリ子の代役を、ほんの数瞬、自動車がやりおおせたのだ。(新潮文庫「ドアを開いて彼女の中へ」)
「自動車っていうのは、単に人を乗せるための道具じゃないんだよね。裕ちゃんが乗ったときにモノからひとつのキャラクターに変身していく、というのが僕の狙いだった。彼らの情念を運んでいく車という美しいモノ。メカと人間が一体になった瞬間、それは人間であって人間ではない状態なんだ。
そういう視線でこの映画は、裕ちゃんとルリ子、あるいは自動車との関係を描いていった。人間の意志で移動を可能にする一番の美しいメカ。だからあれはジャギュアじゃなきゃダメだったんだ。僕も当時乗ってましたから。いかに御しきれない車か、よくわかっていた。
そのどうにもならない狂暴さを含めた個性と美しさ。絶対に車はジャギュアしか考えられなかった」
ひょんなことからジープに腰を下ろし運搬する彼の代わりに、ジャギュアと一体となって裕次郎を追うルリ子。
『憎いあンちくしょう』のそんな旅の涯てに用意されたラストは、時にルリ子の代役をもやりおおせたそのジャギュアを廃棄し、山の頂きで、抱き合い、太陽の激しい光線を浴びながらキスを交わしあうふたりの姿だ。まさしく裕次郎が〈太陽の男〉であることを証明した一瞬!
だがジャギュアがセスナに変わった次の『何か面白いことないか』(1963年)のラストでは、カーっと差し込む残照に、コックピットの裕次郎はまぶしさを隠せず、サンバイザーで光線を断ちきり、映画はそのままジ・エンドを迎えてしまう。果たして両者の違いは何なのか?
「うーん……現実に対し、やりたいこと突き通していくとき、行けるところまで行ってやろうとして、限界がまだ見えていないのが『憎いあンちくしょう』のラストだった。でもね、『何か面白いことないか』では限界が見えてるんですよね。
主人公の辿るであろう道を考えるとちょっとネガティブで、待ち受ける未来のまぶしさに目をそらさざるを得なくなる。
ただこれはちょっと失敗したね。本当はそのあとを描かなきゃいけなかったんだ……」
少々補足しなくては。顔を合わせれば「何か面白いことない?」と口々に言いあうだけの倦怠ムードの世に、確固たる意志を持って、セスナを手に入れるために売り主のルリ子と対立する裕次郎。
この対立はマスコミをも巻き込んで、まるで「主人公=裕次郎だけが輝いていてよいのか?」と観る者に問いかけているような、ヒーロー否定のアナーキーな展開になっていく。
それがラスト、今まで太陽の欲望を肯定し、充足の輝きを発散してきた、ビートな精神を体現してきた男の自己否定にも取れる行為で映画が終わる――わけはない。ラストにはやはり続きがあった。
「あの先ですよね。信さん(『銀座の恋の物語』以来の名コンビ、脚本家の山田信夫)とはもうひとつドラマを作るべきだったんです。
セスナで飛べなくなるだろう主人公がそれでもどこまで脱出できるのかを追いかける。できることならもう1本作って3部作にしたかったんです。
3本目はムード・アクションの魅力とはまた別の裕ちゃんが、たぶん日本という土壌から超えて、海外へと飛び出ていき、グローバルな世界でどういう闘いをしていったかを描いたでしょうね」
石原裕次郎と蔵原惟繕との、ビートな試みの末
日本映画は、主人公が海外脱出しようとしてあえなく夢が頓挫する物語をたびたび繰り返してきた。もしこの3部作が完結していれば、ヒーローが日本という土壌を超えていく晴れがましい瞬間に立ち会えたのだろう。
しかしそれは欠落してしまった。『何か面白いことないか』のあと、裕次郎は舛田利雄監督の『太陽への脱出』(1963年)でいきなり海を越えてバンコックに登場し、異国の地でダークなヒーローを演じてラスト、銃弾を何発も浴びて、初めてスクリーンの中で果ててみせた。

そして蔵原氏との共同作業の欠落を埋めるかのように、自分のプロダクションの第1作に内なる〈脱出願望〉を具現化する『太平洋ひとりぼっち』を選んだ。


『太平洋ひとりぼっち』は市川崑監督作です。
単身、ヨットで大海原を進み、サンフランシスコへと渡った堀江謙一のノンフィクション冒険譚。さらにロンドン→パリ間を競いあうオールスター・キャスト映画『素晴らしきヒコーキ野郎』(1965年)で日本代表の役回りを演じ、ハラキリギャグで世界を笑わせた。


『素晴らしきヒコーキ野郎』はケン・アナキン監督作。
だが、何かが違う。何かがズレてしまった……。一方、蔵原氏は1967年、日活を去っていた。あの欠落の1本をはさんで、監督と選ばれしカップル、〈自動車〉が三たび揃い踏みするには『何か面白いことないか』から6年後、石原プロ製作の『栄光への5000キロ』 (1969年)まで待たねばならなかった。

舞台はもちろん海外、アフリカ。そこで開催される世界的なレースラリー。裕次郎は自動車と一体になって走り始めるーー。
矢作氏の助けをもう一度借りよう。
こだまアルプスの山ひだ、向こうの山岳道路をアルピーヌA110が来る。かすかに谺するそのエンジン音。アルピーヌが手前の山ひだに隠れる。ふっと、何も聞えなくなる。そして、再び、そのコーナァからフレンチ・ブルゥの鼻面が見えた瞬間、 忘れもしない、あれこそ、日本映画の銀幕に本当の意味で自動車が登場した、その一瞬だった。(『ドアを開いて彼女の中へ』)
「あれは僕の長年の企画が、裕ちゃんの耳に入って実現したんですよ。ある意味で運命的な出会いでした。モンテカルロ・ラリーをはじめ、ヨーロッパのレース、日本グランプリ、そしてサファリ・ラリーへと転ずる、ドライバー裕次郎とその恋人浅丘ルリ子、ジャン =クロード・ドルオーとエマニュエル・リヴァのカップルの、愛と友情と戦いを描き、大地を激走する人と車が織り成すダイナミズムに彼らが活欲する自由に向かって、走り続けることをやめない男と女たちの物語なのです。
続いて、エーリッヒ・マーリア・レマルク著の「モンテカルロに死す」で、これらのモチーフを裕ちゃんで再び描いてみたかったのですが、残念ながら実現に至らず、それ以来彼の作品を撮る機会がありませんでした。
いま、悔恨としてあるのは、日活をクビになりフリーにならざるを得なくなったわけだけど、以後もっと積極的に接触すべきだったなあと。
プライベートでもっと語りあっておくべきだったなあ……と。
ある日ね、強烈な夢に襲われたんですよ。石原プロの試写室で裕ちゃんが 『栄光への5000キロ』を観ている。で、こういうのをもう一回やりたいんだ、って言う。パっと目が覚めたら、本当に彼の匂いがした。そこに彼がいた気配した。何かあったんじゃないかって不安になって、石原プロに電話したら、もうダメかもわからないって。
死線をさまよっていたんだね。彼が亡くなった時は慟哭したね……あの時、僕の青春も空っぽになってしまったんだ……」
デビュー当時、LIFE誌に「日本のジェームス・ディーン」と紹介された男、石原裕次郎。
彼と蔵原氏との、ビートな試みの末に辿りついた『栄光への5000キロ』は長らく再公開されていない。今日、脱出願望募ってやまぬ我ら〈遅れてきた世代〉が切に求める「21世紀のための裕次郎」を、これ以上「寝かし」ておいていいものか。夢の中の裕次郎の〈夢〉はスクリーンに映し出すべきものだ。(インタビュー・構成/轟夕起夫)

1999年8月上旬号掲載記事を改訂!

関連記事、こちらにあります!