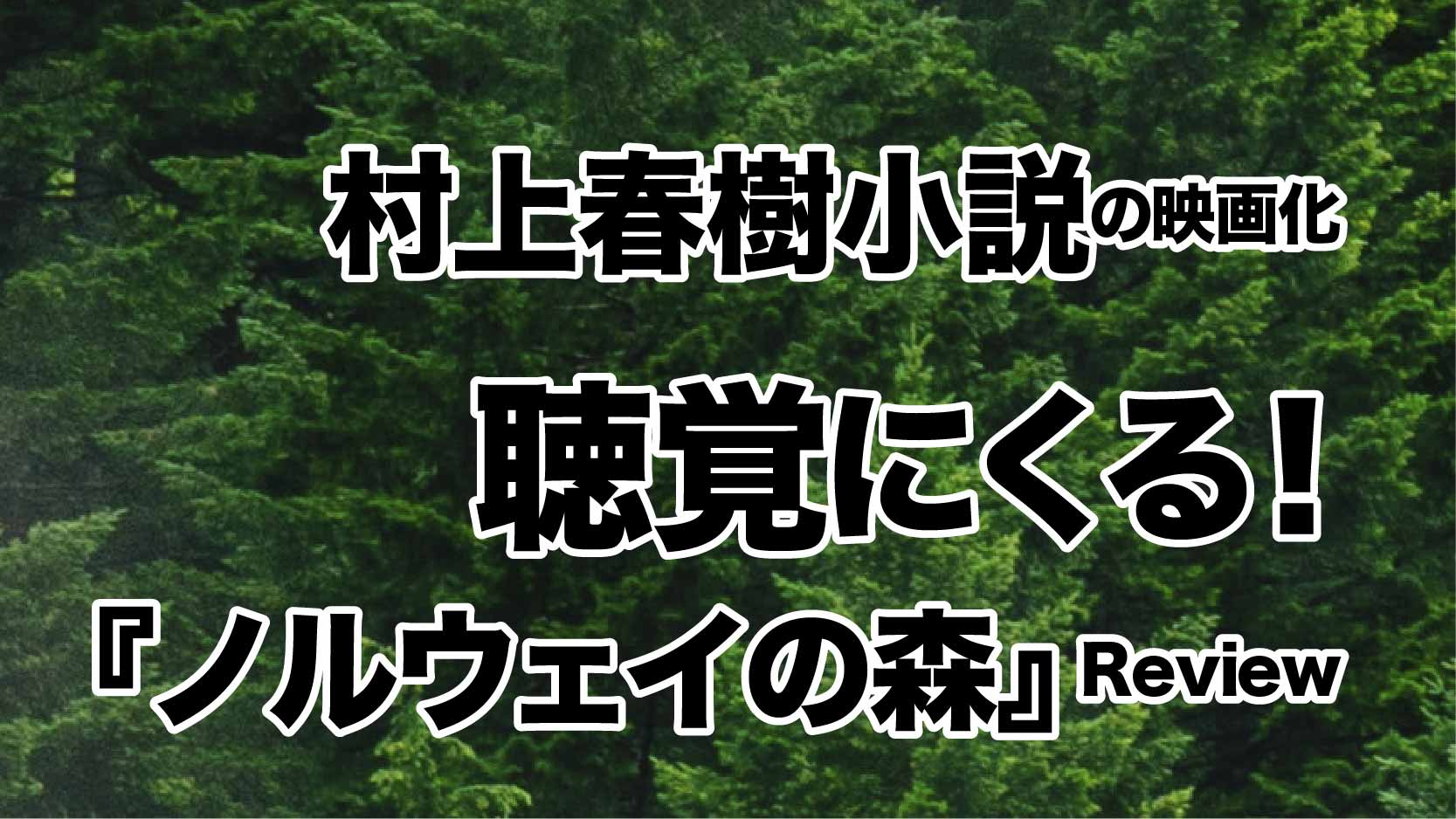映画「ノルウェイの森」は、村上春樹の小説が原作です。


監督はトラン・アン・ユン、出演は松山ケンイチ、菊地凛子、ほか。
レビューをどうぞ!
囁きを聴く――「ノルウェイの森」の優れた“カヴァーアルバム”
えーと。何から書くべきか。そうだ! 「ノルウェーの森」が良かった。
“ノルウェイの森”ではない。ビートルズの名曲「ノルウェーの森」。
しかもレイコさん(霧島れいか)が劇中でギター弾きながら歌っているやつ。
レイコさんというのはヒロイン・直子(菊地凛子)の、京都の入院先の同居人ですね。いい声だった。いいアレンジだった。
そう。この映画は全編、耳が否応なく反応してしまう。
東京で再会したワタナベ(松山ケンイチ)と直子。直子……というか菊地凛子が喋り始めると「あ、直子ってこういう声してたんだ」と素直に感じいってしまった。
彼女と対になっているのが、緑を演じた水原希子の声のトーン。1960年代の日本映画の女優さんってよく、こういう声の出し方、してませんでしたっけ?
ぶっきらぼうだけど愛嬌のある……褒めすぎかもしれないけど、ちょっと若尾文子的なエロキューション。くぐもった“生”のヴァイブレーション。好きだなあ。
そして各登場人物を繋ぎ、それぞれを際立たせる役割を担ったワタナベは、本作の語り手ではあるが、いわば増幅器、アンプのような存在で、気配を消しながらもちゃんと通底音を響かせている。
さらにところどころにCANやドアーズの楽曲がかかり、ジョニー・グリーンウッドが『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』に続いてノイジーなサウンドメイクを施して、音像を演出する。

CANはドイツのロックバンド!


ドアーズはアメリカのロックバンドです!



映画『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』については、レビューがこちらにあります。
もちろん、全てはトラン・アン・ユン監督の計算のもとに構築されているのだろうけれども。

誰もが叫ばない。むしろ呟いている。つまりは、囁きを聴く映画なのだ。それが極点に達するのが、全てを語ろうと試みる直子に耳を傾け、ワタナベが受け止めようとするシーン。
官能的で感動的な草原での長い長いワンショットだ。
果てしなく、行ったり来たりするワタナベと直子に、リー・ピンビンのキャメラが移動撮影で寄りそう。トラン・アン・ユンの発案だそうだが、これを体現した松山ケンイチと菊地凛子、スタッフワークは見事である。
映画ならではのイマージュ、もうひとつの「ノルウェイの森」が生まれた、と言ってもいい。
ラストの、原作でも名高い、緑との電話のやりとり、「僕は今どこにいるのだ?」とワタナベが自問自答するシーンも聴きどころだ。
彼は、まるでどこでもない世界の真ん中にポツンと立ち尽くしているように見える。なぜか、ベルナルド・ベルトルッチ監督の映画の寓話性を思い出した。
そういえばリー・ピンビンは、ベルトルッチの『ラストエンペラー』、そのヴィットリオ・ストラーロのキャメラに多大な影響を受けたという。で、トラン・アン・ユンは今回の撮影前、出演者たちにベルトルッチの『ベルトルッチの分身』を見せたのだとか——。


『ラストエンペラー』は、アカデミー賞作品賞受賞作。音楽は坂本龍一が担当した映画です。


『ベルトルッチの分身』(1968年)は初期の作品です。
村上春樹の原作のエッセンスは、「二十歳前後の青年が成長過程でみつめる世界の光景」であり、「人々が孤独に戦い、傷つき、失われ、失い、そしてにもかかわらず生き延びていくこと」。これである。
監督トラン・アン・ユンの美意識が隅々にまで反映されているが、終わってみると、原作を初めて手にしたときの“読後感”が甦る。すなわち、まどろみから覚めると、体の芯がジワ〜っと火照っているような。
音楽でいえばとても優れた、“カヴァー・アルバム”ではないか。

キネマ旬報2010年12月下旬号掲載記事を改訂!