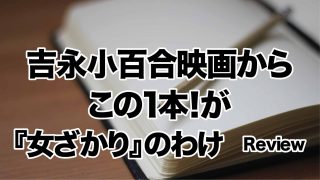現在、大林宣彦監督の遺作となった映画『海辺の映画館―キネマの玉手箱』が全国で公開中です。
尾道にある映画館を舞台に、3人の男性が戦争の歴史を辿りながら、無声映画、トーキー、アクション、ミュージカルと銀幕の世界へタイムリープ。
出演は厚木拓郎、細山田隆人、細田善彦、吉田玲、成海璃子、山崎紘菜、小林稔侍、高橋幸宏、白石加代子、尾美としのり、武田鉄矢、南原清隆、片岡鶴太郎、柄本時生、村田雄浩、稲垣吾郎、蛭子能収、浅野忠信、伊藤歩、品川徹、入江若葉、渡辺裕之、手塚眞、犬童一心、根岸季衣、中江有里、笹野高史、本郷壮二郎、川上麻衣子、満島真之介、大森嘉之、渡辺えり、窪塚俊介、長塚圭史、寺島咲、犬塚弘…

すでに『海辺の映画館―キネマの玉手箱』を観た方も、これからの人にも、すべての大林映画ファンに贈る、監督の超ロングインタビューを復刻です。
『海辺の映画館―キネマの玉手箱』の前作、余命宣告されてからクランクインした映画『花筐/HANAGATAMI』の公開時に行われたものです。
これまでのキャリアを振り返りる中で、映画作りの姿勢をうかがい知ることができる、超ロングインタビューとなります。
プロフィール
おおばやし・のぶひこ
(1938年1月9日〜2020年4月10日)広島県尾道市出身。「マンダム」など数々のCMで名を馳せ、1977年、『HOUSE ハウス』で商業映画デビュー。 『転校生』(1982年)に始まる 尾道三部作、ほか、多くの古里映画を手掛ける。2004年春の紫綬褒章受賞、2009年秋の旭日小綬章受賞。
インタビュー〜大林宣彦の過去・現在・未来〜
(取材・文 轟夕起夫)
本作の存在自体、さらには作品が生まれるまでのプロセス、バック・ストーリーがひとつの事件である! 大林宣彦監督の『花筐/HANAGATAMI』。

「映画化するのは終生の夢であった」と、監督が語っていたそれは、太平洋戦争前夜を生きる若者たちの青春群像が、儚く、眩しく、美しく、とびっきりエモーショナルにつづられてゆく。
原作は、あの三島由紀夫が読んで小説家を志すきっかけになったという檀一雄の純文学の短編小説。

実は本作の脚本の初稿は、大林監督の劇場用映画第1作『HOUSE ハウス』よりも前に書き上げられていた。

つまり、40年の時を経て「終生の夢」は実現したのだった。
今回のロング・インタビューでは、この「幻のデビュー作」を軸にしつつ、ますますラジカルになっていく映画作家、大林宣彦の「過去・現在・未来」に迫ってみる。
戦争を生き残った人間の責務
大林 40年前と今とでは、全く違う映画になりました。40年の間に、あまりに世の中が悪い方向へと動いてしまったんですね。映画は常に時代を映す鏡ですから。劇中に「青春が戦争の消耗品だなんてまっぴらだ」というセリフが出てくるけれども、現在の多くの若い人たちの青春がまた、無残にも戦争の消耗品になりかねないような事態が刻々と進行している。この映画をつくることは戦争を知っている、あの戦争を生き残った僕の世代の人間の最後の責務、だと信じるんです。
なぜ10年越しに「幻のデビュー作」はつくられることになったのか? 大林監督は毅然と、まっすぐこちらの目を見て、こう言葉を紡いだ。
大林 正直なことを言うと、40年前にはホッとした気持ちもあったんです。「撮れなくて助かったな」って。檀さんも、それから僕の父親も世代的にまさに先の戦争に青春を捧げざるを得なかった。その心の奥深くにまで触れ、それを僕が映画にする力があるのかという、逡巡はありましたからね。原作のことを優れた文化として愛していても、やっぱりね。
檀一雄が文芸誌に「花筐」を発表したのが昭和11年(1936年)。翌12年、日中戦争が勃発し、処女短篇集「花筐」の出版記念予告日に召集令状を受け取り、大陸へと赴いた。一方、大林の父の義彦も昭和13年(1938年)に軍医として出征、6年間にわたって中国や東南アジアの激戦地を転戦した。
大林 だからね、映画のクランクインの前日に、医師から「肺ガン、ステージ4、余命半年」と伝えられた時、僕はショックを受けるどころかとてもほっとしたの。余命を否応なく意識する今ならば、檀さんや父親の世代の若者の戦地での覚悟、捉えがたい胸中に少しは近づくことができる気がして。それともうひとつ、かつて「花筐」の映画化の話をするためにお会いしていた晩年の檀さんは、肺ガン末期の状態で、代表作の「火宅の人」を口述筆記で仕上げてらした。「ああこれで、僕は檀さんとやっと繋がれたんだ」って、そんなふうに強く思えたんですよね。
小説「花筐」との出会い
そもそも大林監督が、小説「花筐」を初めて読んだのは1960年代の後半。すでに1950年代半ばから8㎜を回し、自主映画作家の先駆者として注目されていた。1963年には初の16㎜作品『喰べた人』でベルギー国際実験映画祭審査員特別賞を受賞。1964年、新宿紀伊國屋ホールの開館イベントとして「120秒フィルムフェスティバル」を企画し、16㎜の個人映画『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道』を上映。これを観た電通のプロデューサーからCMの仕事を紹介されることとなり、以後、CMディレクターとしても世界で活躍するようになる。そして、その異才ぶりと飛び抜けた業績から商業映画のオファーを東宝から受け、「花筐」の企画を提出、しかし、これまで誰も観たことがないような映画を、と望まれて決定した企画が『HOUSE〜』だった。
大林 コマーシャルの仕事で東宝の撮影所にはずーっとお世話になっていて、僕と組んだことのある職員の皆さんが口々に、「大林さんがもし、東宝で映画を撮ったら、日本映画もお客さんが増えるんじゃないか」と応援をしてくださったんですね。それでひょいと突然、アマチュアのインディーズの人間が東宝映画を撮ることになったんです。その頃アメリカでは、8㎜少年のアマチュア、スティーヴン・スピルバーグがハリウッドに紛れ込んで『JAWS/ジョーズ』(1975年)で大ヒットを飛ばしていた。

そこで中学生のウチの娘(=大林千茱萸。原案者としてクレジット)に相談したら、ちょうどお風呂からあがった時だったのですが、腰まである長い髪をすきながら「この鏡に映っている私が、私のことを食べに来たら怖いよね」と言った。僕は瞬間的に「いいぞ、これは哲学的だ!」と思ったんです。単なるショック・ホラーではなく、僕の大好きな怪奇と幻想の入り混じった、『JAWS/ジョーズ』とは異質の純文学的な映画が撮れる、とイメージが浮かんだ。で、もっとほかにないかと訊いたら、「ピアノを弾いていて、ミスタッチをしたら鍵盤が私の指を噛み砕くの」とか「寝ようと思って押し入れを開けたら、布団がどさっと私に覆い被さってきて食べようとした」とか、「田舎のおばあちゃんの家に行って、井戸でスイカを冷やしていたら、そのスイカがぱっくりと割れて食べに来た」などいろんなアイデアを出してくれたんですよ。
さっそく、彼女のアイデアを集めて7人の少女が田舎の古屋敷に食われていくという基本プロットをつくり、翌日、「花筐(その時のシナリオでは「花かたみ」のタイトルだった)」でも共同脚本をお願いした桂千穂さんのもとを訪ねた。すると「問題は、なぜ食べられるかでしょうね」と訊かれ、僕は「理由はひとつ。戦争です」と即座に答えました。恋人を戦争で失った娘の怨念がお化け屋敷となり、戦争を知らない無邪気な彼女たちをむさぼり食っていく。つまり、根っこの精神性が、初めに撮ろうとしていた『花かたみ』、ひいては今度の『花筐/HANAGATAMI』と結びついた映画だったんです。
映画監督デビュー
1975年に企画会議を通り、77年に完成、全国公開された『HOUSE〜』は、頭の固い大人たちはともかく、若い映画ファンを熱狂させた。75年の段階で大林監督に持ち込まれた脚本を読み、GOサインを出した東宝の重役(=松岡功。後に社長、会長に)の言葉は語り草だ。「こんな無内容な脚本は、初めて読みました。でも私が良いと信じる脚本を映画にしても誰も観てくれません。どうか、私が到底理解できないような映画をつくって驚かせてください」。時代の風に変化が訪れていた。
では、当初撮ろうとしていた『花かたみ』は、どんな映画だったのか。
大林 まず女優さんは全てファッション・モデルを使う。セリフは全部アフレコで声優に。それで音楽を先に用意し、そこに演技を乗せるというヴィジョンでした。キャスティングを宝塚歌劇団のスタイルでやってみたら、きっと古典性と実験性がミックスした映画になるんじゃないかと思ったんですね。そこまでやらないと当時、檀一雄さんの書かれた、戦争と平和、虚実の狭間を危うく綱渡りするような原作の意図は伝わらないだろうと懸念していたので。
「花筐」というのは、表立って戦争を描かずして、しかもその怖ろしい気配を読者に全身で感じさせようとする高度な小説なんです。登場人物は皆、自分はいくつまで生きられるのかということを考え、内心では怯えている。でもそれを筆にはせず(筆にすれば国家犯罪人になってしまうから、実際には筆にできず)、恋愛や友情の描写しかしないで、気配で試してみようと檀さんは決めていたわけで、そのあえて選び取った、表現の不自由さに僕は共感を覚えたんですね。
軍国少年だった頃の記憶
表現の不自由さ──。医学の道に進み、研究者として活躍できた6年間を戦場で費やした大林監督の父、義彦もそうだった。遺されていた手記には復員した時の実感が、かような言葉で書かれていた。「やっと戦時生活も終わった。これで自分で考え、自分の意思で生きていける。本当の自分の人生が返ってきた」。
大林 僕はね、生前、父の戦争体験、戦争中の青春についてはほとんど何も知らないまま過ごしてきたんです。僕が1歳の時に軍医として出征し、敗戦後に帰ってきてから父は戦地のことは頑なに語らなかったし、母もまた何も語らなかった。戦争に負け、母が僕を殺めて一緒に死ぬつもりでいて、結局未遂のまま朝まで話をした一夜のことは鮮明に今も記憶にあるけれども、母の口からついぞ回想されることはありませんでした。僕はその時、恐怖は覚えず「よかった、母ちゃんはきっと痛くなくラクにボクを死なせてくれるだろうから」と思ったんですね。それでもし誰も殺してくれなかったら、どうやってひとりで死のうかとも考えていた。日本の正義を信じていた軍国少年でしたから。でも誰も殺してはくれず、昨日まで戦争に負けたら死ぬ、と言っていたのに皆、平和だ、平和だと浮かれ出して、日本の大人は一体どうなっているんだと。つまり、敗戦後の日本の大人のやることを素直には信じられなくなった、というのが僕たちの世代なんです。
キャスティングと演出
『花筐/HANAGATAMI』では、原作の時代設定を昭和12年から、監督自身が記憶する太平洋戦争直前の昭和16年に置き変え、「戦争」を大きな軸にシナリオに加筆がされた。主要キャストは、唯一の自由である“不良”として学友たちと青春を謳歌するなか、いつしか戦争の渦に飲み込まれてゆく主人公、榊山俊彦に窪塚俊介。彼が身を寄せる、佐賀県唐津に暮らす叔母、江馬圭子には常盤貴子。そしてヒロイン、肺病を患い、やむを得ず部屋に閉じ込められている従妹の美那には矢作穂香という布陣。
大林 キャスティングは常盤貴子くんから始めたんですけど、前作の『野のなななのか』(2014年)で20年の念願叶ってついに大林組の一員となり、主役をお願いしてね。今や僕の映画を代表する女優さんです。

窪塚くんは『転校生−さよならあなた−』(2007年)以来の常連ですが、貴子くんにあわせて、最初から関彦役に決めていました。

美那役の矢作穂香くんは初めての付き合いで、会った時はNYへの自主留学から帰ってきて、少し太っていたから「肺病病みの役はできないよ、5kg痩せておいてね」と言ったら、8kgも痩せてきた子なんですよ。女優さんをもう少し紹介すると、美那の2人の友達、あきね役の山崎紘菜くんは『野のなななのか』にも出てもらっていて、千歳役の門脇麦くんは『まれ』(2015年)という朝ドラで貴子くんが共演し、彼女が推薦してくれたんです。

僕の現場では俳優にマネージャーは付かないのが不文律。今回も45日間、皆さんマネージャーなし、ひとりで現場に来てもらったのですが、自分の出番のない日もあるわけで。で、若い女優さん同士ですから、お茶ぐらい一緒に飲んだだろうと思って、撮影が終わってから穂香くんに訊いたら、「いえ、道で会っても顔を合わせないよう通り過ぎていました」と言う。「どうして? 仲悪いの?」「だって映画の中の美那は、千歳とお茶を飲みません。だから、私たちも街で会っても知らないフリをしていました」と。俳優たちが自主的にそんなふうに自己管理をし、役で居てくれたから、もう細かく演出する必要がなかった。セリフを与えれば、自然にその役として動いてくれました。
俳優の実年齢と役柄の年齢
大林組初参加が多い男優陣も見てみよう。俊彦が憧れを抱く、アポロ神のように雄々しい美少年、鵜飼に満島真之介。お調子者の阿蘇に柄本時生。老成した面持ちの、虚無僧のような吉良には長塚圭史。満島と柄本は実年齢は28歳、大胆にも窪塚は35歳にして17歳の学生役に。長塚に至っては40歳を過ぎている。
大林 唯一キャスティングで困ったのは、長塚くんが演じた吉良だけですよ。この吉良だけが難しくてね。素晴らしいポスターを描いてくれた、千茱萸さんの夫で絵の作家の森泉岳土くんが声をかけ、助けてくれたんです。「監督、何か悩んでますか?」「うん、吉良だけがなあ、見つからないんだよ」「何をおっしゃるんですか。長塚圭史さんがピッタリじゃないですか!」「ええっ? そうかい?」「あの人以外、僕には考えられません」と。「そうかねぇ、40過ぎてるぜ、彼は」と言うと、「演じ手に年齢はないというのは、監督の持論じゃないですか」と諭されてしまった(笑)。確かに演ずるとはそう。かつての実人生での蓄積、例えば高校生の経験があるからこそ高校生役を違った角度から演じられるのであって、キャスティング後は何の抵抗感もなく、吉良役の長塚くんも、他の3人もそれぞれの役を独自につかまえてくれ、大成功だったと思います。
表現で傷ついた世の中を包む
さて、2017年9月のことである。この『花筐/HANAGATAMI』の公開を記念し、東京の老舗の名画座・新文芸坐にて、「ワンダーランドの映画作家 大林宣彦映画祭2017」と銘打った特集が組まれた。2週間で33本もの作品が上映され、大林監督も連日、劇場に足を運んで改めて自作と向き合ったそう。
大林 うん、そうしたらね、いろんな発見があっておもしろかったんです。先ほど『HOUSE〜』と戦争との関係をお話しましたが、池上季実子くんが扮していた主人公の新しい母親の名前は何と、江馬涼子。これは実現しなかった『花かたみ』で、江馬圭子役に決まっていた鰐淵晴子さんがこの役を引き受けてくれたのでそこから付けてしまったんですね。さらには檀一雄さんの娘さん、檀ふみさんもチラリと特別出演していたりして、幻のデビュー作の名残が見られる。もっと初期の、16㎜作品『喰べた人』では、前半は1960年代高度経済成長期の飽食の時代をパロディにしているんだが、ところがなぜかお腹いっぱいになった人たちが後半、突然包帯を吐き出すんですよ。そうして包帯はそこにいるお客もレストランも全て包んでしまう。すっかり忘れていたんだけども、久々に観返したら思い出しました。あれは共同演出の藤野一友さんと「後半どうします?」ってことになって、「じゃあ、包帯をみんなが吐き出して、総てを巻いてしまおう」と僕が提案したんです。「なぜ?」って藤野さんが聞くから、「戦争で日本中、皆が傷ついているんだから、今、地球を包帯で温かく包んでやりたいんだよね」って。あのシーンにはそういう意味が込められていた。で、今度の『花筐/HANAGATAMI』にも、手に火傷をした吉良の部屋に大量の包帯がなびいているんですよ。実はこれまでも僕の映画にはたびたび包帯が登場してきたんですが、そうか、初の16㎜作品からあったか、と感慨深かった。
特集では『花筐/HANAGATAMI』との深い親近性が認められる16㎜作品、『EMOTION=伝説の午後=いつか見たドラキュラ』(1967年)も上映された。
40年間考え続けた「花筐」
大林 『〜いつか見たドラキュラ』は、ロジェ・ヴァディム監督の『血とバラ』(1960年)にオマージュを捧げた映画なんです。ヴァディムは僕と同様にアプレゲール (戦後派)の作家で、戦争を体験し傷ついたフランスの若者の悲劇を、リアリスティックに切り取るのではなく、耽美なヴァンパイア譚にくるみながらデカダンスの伝統を用いて美的に描きましたよね。『血とバラ』は撮影前、常盤貴子くんにも観てもらいました。今回の特集上映では、「ああ、僕 は40年間、「花筐」のことを考え続けていたんだなあ」と気づかされましたよ。『花筐/HANAGATAMI』の最後の美那のセリフは、『転校生』 (1982年)のあるシーンと対になっているし、『異人たちとの夏』 (1988年)の病室の風間杜夫さんの枕元には、僕の大切な2冊である「花筐」と「草の花」が置いてあった。


丸山才一さんの小説が原作なのに、『女ざかり』(1994年)では冒頭、藤谷美紀くんが「花筐」を朗 読しているところから始めている。


『女ざかり』のレビューはこちらにあります。
『あした』(1995年)の小型客船「呼子丸」っていうのは唐津市の呼子町からのネーミングですし、挙げていたらキリがありませんね。

そういえば『ふたり』(1991年)のラスト、主演の石田ひかりの部屋の本棚にも「花筐」と「草の花」が置かれていた。

「草の花」とは大林監督が16歳の夏休みに出会った福永武彦の小説だ。福永の原作では「廃市」(1983年) が映画化されており、「草の花」は『さびしんぼう』(1985年)の後に尾美としのり、富田靖子という最高のキャスティングで企画されたものの、惜しくも流れてしまった。



口述筆記の手法で撮る
「大林ワンダーランド」は海のように広く、世代によって入り方はいろいろである。ちなみに、常盤貴子は『ふたり』と『青春デンデケデケデケ』(1992年) がリアルタイムで決定的な大林映画体験になり、そこから過去作へと遡っていったそう。『花筐/HANAGATAMI』については「監督の脳内のフィルターを通ると純文学はここまで行間が広がるのか!」と、身をもって映画の可能性を感じたという。実際、その撮影方法は革新的だった。

小林 余命宣告をされてね、治療のためにいったん現場を離れる時、『野のなななのか』の助監督をやってくれた、僕の息子ほども若い松本動(ゆるぐ)くんに監督補佐になってもらいました。現場は動くんに任せると言ったら、ひどく不安そうな顔をしているので「お前なあ、監督が病気になって現場を離れるって、こんなラッキーなことはないんだ。準備は全部できているんだぞ。だから君の裁量で君がつくりたい映画をつくりなさい。仮に俺が現場に戻ってきても、いないと思え」と発破をかけたんです。そうしたら動くんにとっては幸か不幸か、僕は現場にすぐに戻ってこられたんですね。でも、約束を守って干渉はせず、目立たないように普段は見ることのないビデオモニターを眺めていた。そこにはね、客観的な映画のシーンではなく、シーンを演出する動くんが見ている主観の世界が映っていたんです。
で、僕はね、よし、今回は口述筆記の映画をやろうと思った。檀一雄さんに最後にお会いした時、ご自分ではペンを握れず口述筆記で「火宅の人」を書いていらして。口述筆記って誰でもできるわけではなく、作家との信頼関係があり、実際に口にしていないことまでその文体で書けなければならない。この方法のほうが自分の欠点まで客観的に見ることができ、作品が良くなるかと想像してみた経験を思い出してね。では具体的に何をやったのか。シナリオの改訂です。3000箇所くらい付箋を貼って、元のオリジナルの脚本になかったセリフを足していき、「動くん、ちょっとこのセリフを入れてよ」と渡していった。映画のテーマになった「青春が戦争の消耗品だなんてまっぴらだ」というのも最後までシナリオにはなく、あれは完成台本にようやく刷り込まれたセリフでした。毎日ホテルを出る前に新聞、TVのニュースを頭の中に叩き込んで、それで現場に行って、役者さんの芝居に3000近くのセリフを増やすことで、まさに口述筆記的な映画になりましたね。
マスターショット・システム
そして撮影が終わり、編集を始めたら、大林組初のマスターショット・システムが自然と成立していた。
大林 ハリウッド映画っていうのはね、監督は現場を指揮するだけで編集はプロデューサーとプロデューサーが雇った編集マンで進めるもの。監督は全てのアングルのカットを撮っておくというのがハリウッドの契約で、それをマスターショット・システムって呼んでいるんだけど、動くんはあらゆる角度から全部撮ってくれていたんですね。少しは想定外の演出もありましたが、おもしろがって取り入れて、結果、初号試写をやったら誰も予想していない編集の映画になっていた。大林宣彦が処理しただけではなく、今の時代が持っている緊迫感、ジャーナリスティックな空気感みたいなものが図らずも僕個人のレベルも超えてこのフィルムに焼きつき、僕の望む風化しないジャーナリズムが映画という形で具現化されていました。
音楽の付け方はサイレント映画
音楽がまたすごいのだ。1996年に大林監督に見出され、以降の作品ほぼ全てを手掛ける山下康介。今まで大林映画の台本には、あらかじめ作曲家でもある大林監督の譜面も付けられていたのだが、それを止め、全編を任された。バッハの無伴奏チェロ組曲をモチーフにすることは監督からのサジェスチョン、そこに多様な音色を重ねて、映像に拮抗するアヴァンギャルドな表現を達成した。
大林 檀一雄さんを偲ぶ会で“花逢忌”というのがありまして、毎年1回開かれているんですよ。能古島の檀さんの文学碑がある場所で。去年(2016年)の夏かな、撮影前に招かれた時にバッハの無伴奏チェロ組曲が演奏されたんです。息子の太郎くんが「親父はこの曲が大好きでした」と教えてくれ、僕は知らなかったから、これはもう全編この曲が鳴り響く映画にしようと決めたんです。
僕の音楽の付け方はね、サイレント映画なんですよ。つまり全然ないか、全編に付けるか。サイレント映画というのは音楽がなくても成立しているでしょ。逆に全編に付けてもよい。僕にとってはね、新しい映画っていつも古典でもある。だから今もサイレント映画が一番新しい、と思っている。映画が誕生したのと同時に発生し、あらゆる表現が実験であり、しかも発明でもあった。僕はサイレント映画の誕生期からを観ることができた世代です。
もっと言えば日本で観ることができる1960年代までの映画は全部観ている。その養分を活かして40年前に「花かたみ」を企画し、代わりに『HOUSE〜』を撮った頃、周りにあった現代の映画というのが、ほとんど全て古典を忘れ、未来への展望もない、リアリズムの日常性ばかりのものが主流を占めていたんです。そうではなくて映画の虚構性、現実を虚構で再構築し、真実をあぶり出す行為、すなわち、ウソから出たマコトを描く映画をやるためには、いわゆるメジャーの制度に則った映画とは一線を画し、新しいことをやらなきゃいかんなと考えた。そうしたらやっぱりサイレント映画へ立ち還り、原点に立ち戻っていくんですよ。
黒澤明との交流
ウソから出たマコト──。
かの黒澤明監督は『さびしんぼう』を観て感動し、黒澤組スタッフ全員に観るように伝えた。そして1989年、大林監督は黒澤明本人から指名され、彼を被写体とするCM(NEC オフィスプロセッサ)を撮ることとなった。1990年には『夢』のメイキングを担当(『映画の肖像 黒澤明 大林宣彦 映画的対話』)。「あなたにとって夢とは何ですか」と大林監督は質問した。その答えは……「夢は本音が語れる。現実ではなかなか本当のことが語れないけれど、夢こそは本当のことを勇気を持って語れる場所だ」。

著書「映画、この指とまれ」(アニメージュ文庫)によると「ここに、黒澤映画の本質がある」と大林監督は断じて、こう続けている。「夢とは、現実離れした、フワフワした心地良い風船で、現実の前には儚く消えてしまう、そんなやわなものではないんです。この現実の中の、人の歴史や政治や愛や生きる誇りに対して、夢というひとつの虚構が、どれだけの力を持って正直に訴えうるかという信念がある」。
言うまでもなく大林映画の本質もまた、そこにあるのだ。とてつもなく耽美な「大林ワンダーランド」へと誘う『花筐/HANAGATAMI』は、『この空の花 長岡花火物語』(2012年)、『野のなななのか』と並んで“戦争三部作”を形成している。

表現すべきは人間の正気
大林 おそらく『花筐/HANAGATAMI』が真に必要なのは、大人ではなく、今後、新しい戦争を迎えるかもしれない僕らの“子供たち”なんですよね。ただこれは、反戦の映画ではない。厭戦です。理屈を超えて戦争なんてイヤだという映画。これも黒澤さんに教えてもらったんですが、「俺たちは表現者だから、プラカードは担がないよね」と。「プラカードを担いで何かもの申そうとするならば、僕らが運動家になるか政治家になった方が早いよ」とおっしやっていた。それを僕流に言い直せば、戦争という狂気に対して、僕たちが表現すべきなのは人間の正気だけなんだと。
正義は信じられないです。戦争に勝ったほうの正義が、つまりは正しかったということになる。自らの正義を通そうと思えば、永遠に勝ち続けなければならないんですから。正義なんていうのは自分の都合にしか過ぎない。かつての日本がそうだったよね。そういうことを僕たちは負けたから学べたんです。これは僕たちが自信を持って言わなければならないこと。この世には映画にだけハッピーエンドがあるんです。現実世界にハッピーエンドはない。でも、現実だけを信じていたら僕たちには生きていく希望すらなくなる。
平和だってウソですよ。一番の大ウソ。だって人間は一度もそれを実現していない。けれどもせめて平和という大ウソを信じて、信じていればいつかこの大ウソも真実になるかもしれないと希望を持ち、「人間よ、勇気を持って、平和な未来はきっと来る、と信じて生きていけ」というのが第一次大戦、第二次大戦で祖国を追われ、家族を殺され、未開の地アメリカにやって来た、ユダヤ系の敗者たちが切り開いたハリウッドのフィロソフィーです。つまり戦勝国アメリカだけのものではなく、世界中の敗戦国民たちの平和を願うハッピーエンド。「映画には必ず世界を平和に導く美しさと力がある」という黒澤監督の言葉を思い出しますね。
生きていくこととは
映画作家・大林宣彦の「過去・現在・未来」。最後に、その未来について記そう。幸いにして、抗ガン剤治療によって病状が劇的に好転! 現在は「余命は未定」とのことだ。が、『花筐/HANAGATAMI』の終盤に突如登場する、主人が不在のディレクターズ・チェアがちょっと気になる。
大林 あれはね、最初の構想では冒頭の窪塚くんの長ゼリフを、僕自らが出演して語るつもりだったんですよ。撮影したけれども使わなかった。そうしたらあの最後のシーン、僕が座る予定だった無人のディレクターズ・チェアが、まるで遺言みたいに見えるんだよね(笑)。今頃もし、死んでいなくなっていたら、「大林宣彦は歴史的な名作を最期に残した」と伝説になるんだけど、そうはカッコ良くはいかなくて。もう次回作に向けて動き出しています。今度は反動で「こんなものは映画じゃない」、『花筐/HANAGATAMI』はあんなに良かったのに…なんて言われるのは分かりきっているわけだけど(笑)、まあ僕は僕であり続けるしかない。そういうことの連続が、生きていくこと、生き抜くことなんですよね。

DVD&ブルーレイでーた2017年12月号掲載記事を改訂
大林宣彦傑作ピックアップ
『HOUSE ハウス』(1977年)

おばあちゃんの屋敷に訪れた少女たちが次々といなくなる…
『花筐』(『花かたみ』)の代わりに商業映画デビュー作となった新感覚ホラー。 現在も世界的にカルト的な人気を博している。
『金田一耕助の冒険』(1979年)

前代未聞の金田一が登場、邦画初の本格パロディ作品
つかこうへいがダイアローグ・ライターを務め、横溝正史の小説『瞳の中の女』をパロディ満載で映画化。角川映画との蜜月はここからスタート!
『ねらわれた学園』(1981年)

薬師丸ひろ子がブレイク。アイドル映画の礎を築く
眉村卓の小説を、オプティカル合成を駆使して映像化した薬師丸ひろ子主演作。漫画家・手塚治虫の息子、手塚眞が嫌味な優等生役で怪演。
『転校生』(1982年)

男の子と女の子の、心と体の入れ替わり青春コメディ
山中恒による児童文学「おれがあいつであいつがおれで」を映画化。“尾道三部作” の1本目で、ロケ地をファンは聖地巡礼した。
『時をかける少女』(1983年)

原田知世が銀幕デビューを飾ったファンタジー
大林監督が「『オズの魔法使』(1939年)のジュディ・ガーランドに比べられるべき」と賛辞を送った原田知世の映画デビュー作。原作は筒井康隆の同名SF小説。
『さびしんぼう』(1985年)

『転校生』『時をかける少女』に続く尾道三部作
富田靖子がひとり4役を演じ、尾美としのりと共演。さびしんぼうと名乗る少女が、片思いの空想ばかりしている少年の前に現れる。
『野ゆき山ゆき海べゆき』(1986年)

あえてセリフを棒読みにするなど実験的な試みも
鷲尾いさ子が鮮烈な演技を披露した映画デビュー作。佐藤春夫原作の「わんぱく時代」を、尾道を舞台に映画化。
『異人たちとの夏』(1988年)

山本周五郎賞を受賞した山田太一の小説を映画化
死んだはずの両親と再開した男の奇妙な体験をつづった大人のためのファンタジー 。出演は風間杜夫、秋吉久美子、片岡鶴太郎。
『ふたり』(1991年)

石田ひかり×尾道 新たな3部作の始まり
後に『はるか、ノスタルジィ』(1993年)でも組む石田ひかりを主演に抜擢し、赤川次郎の同名小説を映画化。共演は中嶋朋子で、 幽霊となった姉とその妹の絆の物語。
『青春デンデケデケデケ』(1992年)

リアリティを重視してリハーサル&NGはなし
1960年代初頭にバンドを組んだ四国の高校生の青春をつづる。「人生にNGはない」と大林監督が一発撮りで演出。浅野忠信がリードギター担当の青年役。
『女ざかり』(1994年)

新聞社で論説委員が書いた社説が波紋を広げる…
丸山才一のベストセラー小説を、吉永小百合ほか豪華キャストで映画化。大林監督は 「あなたのシワを撮りたい」とラブコール、 吉永にほぼノーメイクを要請した!
『SADA 戯作・阿部定の生涯』(1998年)

その手練手管を駆使し、主題歌の作詞も担当
黒木瞳がスキャンダラスな事件を起こした実在の女性、阿部定を演じた第48回ベルリン国際映画祭国際批評家連盟賞受賞作。主題歌『定のサバダバダ』の作詞は大林監督。
『転校生-さよなら あなた-』(2007年)

10年にひとりの逸材・蓮佛美沙子でセルフリメイク
大林監督が「10年にひとりの逸材」と絶賛した蓮佛美沙子主演のセルフリメイク作、にしてアナザーストーリー 。 公開時「5年後に今度は『転校生 ―こんにちは あなたー」を撮ろう」とも。
『この空の花 長岡花火物語』(2012年)

大林的戦争三部作、第一弾
花岡花火と戦争、3.11をテーマにした一大スペクタクル。規制の映画文法にとらわれない混沌とした映像は、もはや映画を超えた体験。 本作から完全デジタル撮影へと移行した。
『野のなななのか』(2013年)

「大林的戦争三部作」の第2弾
舞台は、北海道芦別市。終戦を迎えてなお続く戦争に翻弄された者たちの悲運を描く。 時代への危機感がいっそう募る。常盤貴子が念願の大林映画出演を果たしている。