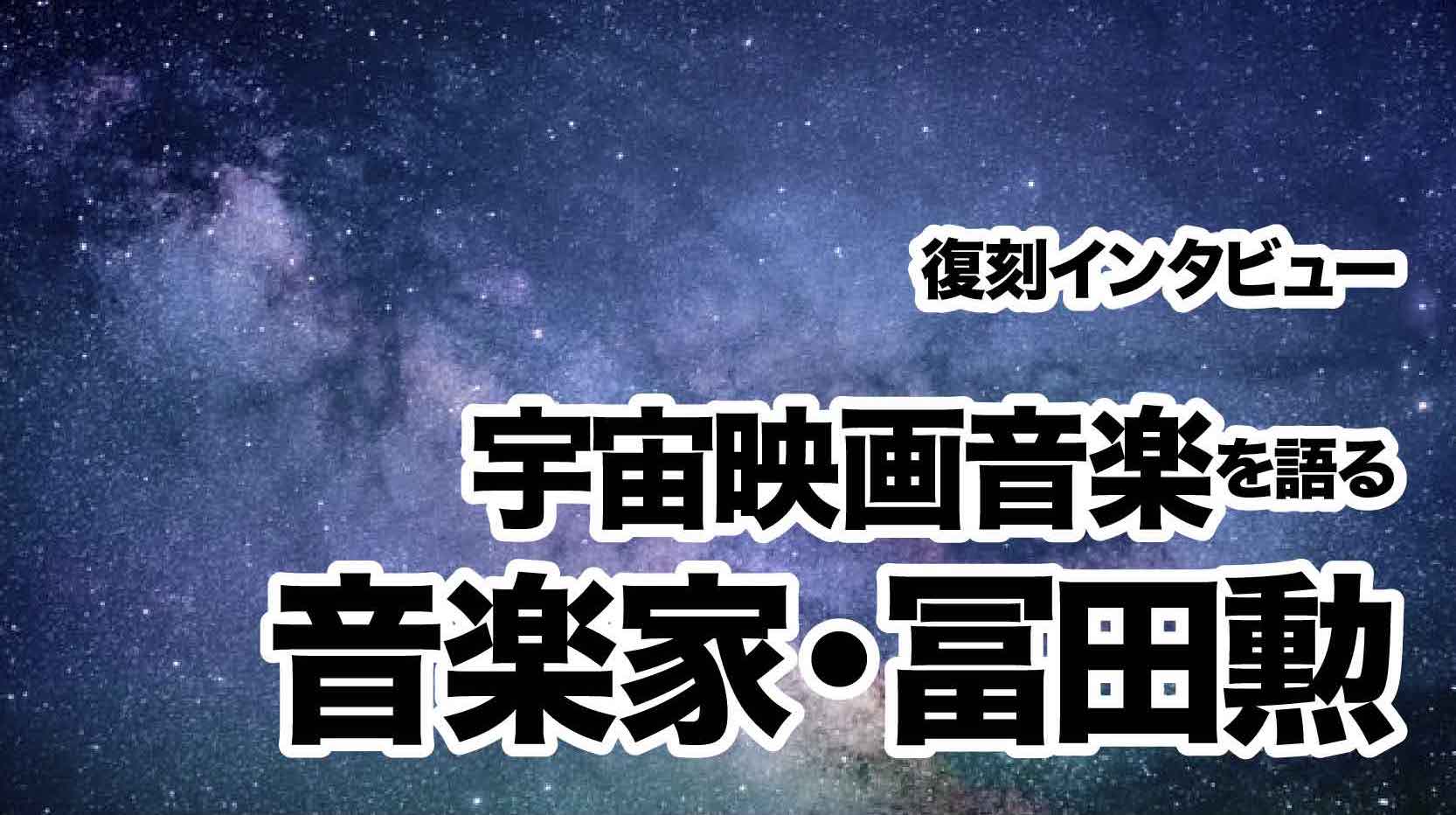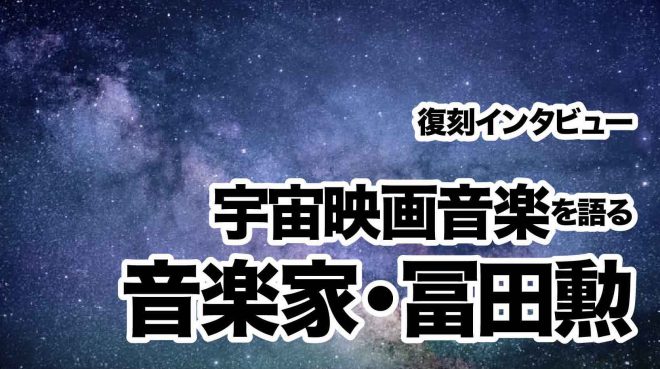

シンセサイザーの大家として世界的に知られ、グラミー賞の候補にもなった大作曲家、冨田勲さんのインタビュー記事を蔵出しです。
冨田さんが音楽を担当した映画『おかえり、はやぶさ』の公開にあわせて行われたインタビューとなりますが、映画の仕事については残念ながらこれが遺作となりました。
宇宙映画の名曲と、『おかえり、はやぶさ』に込めた情熱を語っておられます!
冨田勲プロフィール
『おかえり、はやぶさ』概要

2003年5月。小惑星探査機[はやぶさ]が打ち上げられた。JAXAのエンジニア助手・健人(藤原竜也)は、失敗した前機[のぞみ]の責任者だった父(三浦友和)への反発もあり、[はやぶさ]成功へ奔走する。
監督:本木克英 脚本:金子ありさ 音楽:冨田勲 出演:藤原竜也、杏、三浦友和、前田旺志郎 2012年 松竹
インタビュー冨田勲〜宇宙映画の名曲と込めた情熱
(取材・文 轟夕起夫)
冨田勲。テレビ黎明期から活躍する大作曲家であり、また、シンセサイザー音楽のパイオニアにして大家でもある。1974年に発表したアルバム『月の光』は米国のヒットチャートで1位を獲得、グラミー賞の候補に。
続く、いわゆる宇宙3部作『惑星』『宇宙幻想』『バミューダ・トライアングル』にて展開した立体的で広がりのある音響世界はなおも進化し、映画『おかえり、はやぶさ』に豊かな音像を与えている。



冨田勲 『おかえり、はやぶさ』では、ラストにワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」を編曲し使ったんですが、それは名高いスタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』の影響もあると思います。
「ツァラトゥストラはかく語りき」ほか、既成のクラシックを有効に活用したあの映画の手法には当時とても衝撃を受けたんですよね。で、私にとってアリア「イゾルデの愛の死」は、星雲の涯てへと吸い込まれていくような、宇宙的なイメージを喚起する最高の曲だったわけです。


ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」は全3幕からなる楽劇(オペラ)です。


『2001年宇宙の旅』(1968年)はスタンリー・キューブリック監督のSF映画。全編にクラシック音楽が使われています。
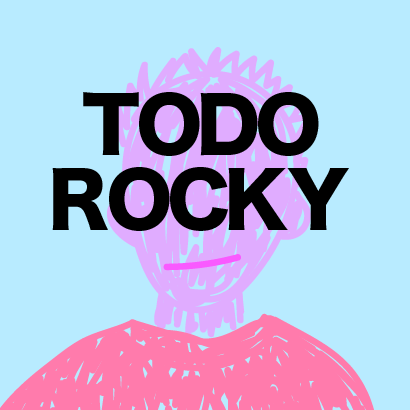
さらに宇宙映画と音楽の話題を通して、スティーブン・スピルバーグ監督の『未知との遭遇』と『E.T.』が挙がった。音楽はいずれもジョン・ウィリアムズ。ちなみにウィリアムズの代表曲「スター・ウォーズのテーマ」は先の冨田のアルバム『宇宙幻想』に、『未知との遭遇』のテーマ曲はアルバム『バミューダ・トライアングル』に、それぞれ冨田流のアレンジで収録されている。


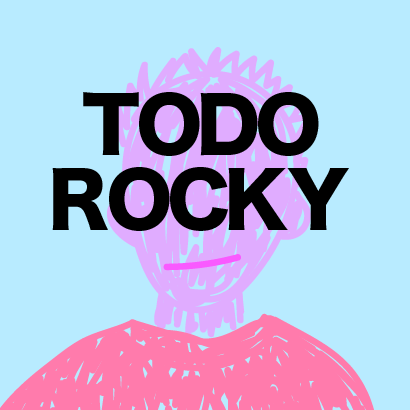
「未知との遭遇」の音楽について
人間が外的生命体と交信するレミドドソ。の旋律、そこから展開していくダイナミックなスコアが見事! ウィリアムズも冨田氏同様、現代音楽の技法を習得していました。
「E.T.」の音楽について
20世紀初頭のロシアのロマン主義を意識した音作り。少年とE.T.との友情がすばらしいメロディで奏でられ、ウィリアムズはこの音楽でアカデミー賞作曲賞を獲得しました。
冨田勲 公開時、映画館では大勢の観客が、巨大なマザーシップが降臨してくるシーンで泣いてましたね。私も言葉にできぬ感動を覚えました。若い時分は本物と遭遇したくて、ずいぶんUFOを追いかけましたよ(笑)。『未知との遭遇』も『E.T.』もオーケストレーションが壮大な宇宙のイメージとぴったりでよかったなぁ。
1984年、冨田氏はオーストリアのリンツ市で、ドナウ川両岸の地上、川面、上空一帯を使い、超立体音響を構成し、8万人の聴衆を音宇宙に包み込む[トミタ・サウンドクラウド]を開催。以後、天空と交信するかのごときこの大イベントを、日本や海外各地で精力的に手掛けてきた。
冨田勲 子供のころから空を飛ぶことへの夢があったんですね。私の憧れの的は戦時中、隼や鍾馗などの戦闘機の設計にかかわり、戦後は日本のロケット工学の父となられた糸川英夫(1912〜99)さん。後年、先生と親交を持つことができましてね。なんと還暦からクラシックバレエを始められ、1977年、帝劇公演の『MoogPlanets』にて、私の音楽で踊られた時は感無量でした。
2011年6月にリリースしたアルバム「惑星 ULTIMATE EDITION」では、糸川氏に敬意を表した新曲「イトカワとはやぶさ」を発表。映画「おかえり、はやぶさ」にもそのモチーフはちりばめられ、深い親交のあった日本の宇宙開発の先駆者への富田氏のオマージュが感じられる。
冨田勲 目的地の小惑星はイトカワと呼ばれ、隼から命名された探査機がそこにたどりついてサンプルリターン計画を成功させた。これは奇跡ですよ! その礎となった先生への気持ちを凝縮し、音楽に込めました。
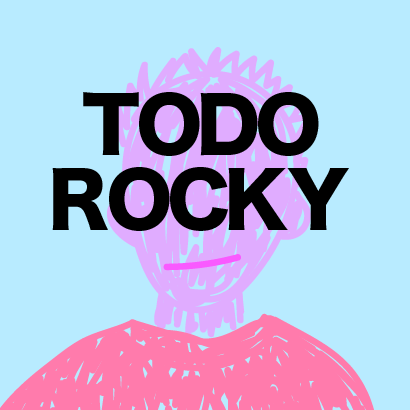
T 2012年春号掲載記事を改訂!