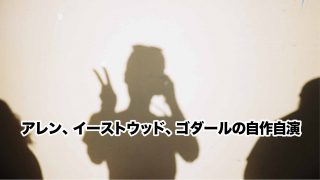現場で経験を積んだ俳優が監督した映画はけっこうあります。面白い映画もたくさん!カーク・ダグラスの例もそのひとつ。

監督業へと活動の場を広げていった、そんな先駆者たちについて、轟の復刻原稿から見ていきます!

列挙の映画人たちのアツアツの映画熱をお届け!

もはや当たり前となった「スター&名優の監督進出」。本稿ではそれを切り開いた先人たちの足跡から、今も使えそうな“方法論”を独断的に拾ってみたいと思う。
女優の妻を主役に立てて俳優の夫が撮る、は王道
最初に記すべきはこれだ。
【女優業の妻を主役にしろ!】。
メル・ファーラー、ポール・ニューマン、ジョン・カサベテス、伊丹十三、ウディ・アレン、ティム・ロビンス、アントニオ・バンデラス
それは夫婦にして、俳優同士ならではの美しき結晶。オードリー・ヘプバーンで『緑の館』(1959年)を作ったメル・ファーラー。

『レーチェル レーチェル』(1968年)でジョアン・ウッドワードの新境地を、自らの名声とともに高めたポール・ニューマン。

極めつけはジーナ・ローランズとジョン・カサヴェテスのコンビだろう。

このコンビでの作品は『こわれゆく女』(1974年)や『グロリア』(1980年)など計6本、高い評価を受けてます。
伊丹十三、ウディ・アレン、ティム・ロビンス、アントニオ・バンデラス……創作の源は“ミューズ”にあり、というわけだ。

伊丹十三さんは、宮本信子さんと。『タンポポ』(1985年)や、『マルサの女』(1987年)、『あげまん』(1990年)など。世に出すたびに大ヒットでした。

いろいろとお騒がわせのウディ・アレンですけど、初期監督作『ウディ・アレンのバナナ』には2番目の妻ルイーズ・ラッサーが出演。離婚後のパートナー、『アニー・ホール』(1977年)でダイアン・キートンは、数々の主演女優賞を手にしました。

ウディ・アレンの場合はご自身出演もします。

ティム・ロビンス監督、スーザン・サランドン主演『デッドマン・ウォーキング』(1995年)で、彼女はアカデミー賞主演女優賞に!


アントニオ・バンデラス監督、メラニー・グリフィス主演は『クレイジー・イン・アラバマ』(1999年)など。

名監督を夫に持った女優が、自ら監督になったパターン
ジャンヌ・モロー、アンナ・カリーナ、左幸子
しかし、言うまでもなく女優とは撮られるだけの存在ではない。ましてや名監督にして奇才、ウィリアム・フリードキン、ジャン=リュック・ゴダールとの生活を経験したこの二人ならなおさらだ。
前者は『ジャンヌ・モローの思春期』(1979年)を撮ったジャンヌ・モロー。後者は『同棲生活』(1973年/未公開)のアンナ・カリーナ。つまり【映画監督の妻とは呼ばせない!】である。
日本で彼女らに匹敵するのは誰か? 左幸子だ。
フランスのオムニバス映画『L‘AMOUR Au Féminin(原題)』(1971年/「日本編・アキ子」を担当)に参加した際は、夫で監督・羽仁進の提案で演出にチャレンジしたらしいが、『遠い一本道』(1976年)では自らのプロダクションを設立、国鉄(現・JR)労働組合との共同製作で、合理化のもと力強く生きる北海道の職員夫婦を描き出してみせた。


『ジャンヌ・モローの思春期』、『同棲生活』、『遠い一本道』は、今は残念ながらDVDでもなかなか見つけづらい作品です。
どうしても描きたいテーマがあったパターン
となると、肝要になってくるのは【作品に主義主張を込めろ!】ということ。
ジョージ・C・スコット、ジョン・ウェイン、ケヴィン・コスナー、丹波哲郎、三國連太郎
『激怒』(1972年)で基地汚染問題をテーマにしたジョージ・C・スコットのような人もいれば、私財を抵当に入れ、当時1200万ドルを投じ、愛国心から10年間温めた企画『アラモ』(1960年)を製作、監督したジョン・ウェインのような人もいる。


監督した『アラモ』はアカデミー作品賞ノミネート!

ウェインなど、破産しても懲りずに悪評粉々たる『グリーン・ベレー』(1968年)を放つほどの豪快さだった。実は年齢的限界を感じ、監督への鞍替えも考えていたそうだが、ケヴィン・コスナーにも通ずる〈オレ映画〉の先駆者だ。


ケヴィン・コスナーは監督・主演『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(1990年)でアカデミー監督賞受賞。〈オレ映画〉というのはこの記事が、最低作品の宴、ゴールデンラズベリー賞に選ばれてしまった『ポストマン』(1997年)の後に書かれたからでしょう。でも『ワイルド・レンジ 最後の銃撃』(2003年)はいい映画でした。

ほかにも『砂の小舟』(1980年/共同監督・原田雄一)を皮切りに、“霊界の宣伝マン”として総監督を務め『大霊界』シリーズを世に問うた丹波哲郎、『親鸞・白い道』(1987年)の三國連太郎などが挙げられる。


タッグを組んだ相手に恵まれて成功したパターン
つぎに肝に銘じたいのは【良き協力者を得るべし!】だろう。
ジーン・ケリー、リチャード・アッテンボロー、ウォルター・マッソー
たとえば『私を野球につれてって』(1949年)からスタートした、MGMミュージカル・スターのジーン・ケリーと天才振付師であったスタンリー・ドーネンとのコラボレーションは、“共同監督”という形で『踊る大紐育』(1949年)、『雨に唄えば』(1952年)、『いつも上天気』(1955年)といった傑作群を生んだのだから。
むしろケリー単独の「舞踏への招待」(1956年)になると、かえって彼の実験精神が暴走し過ぎて不評となる始末。

英国アクターとして初の映画製作会社ビーヴァー・フィルムを、親友ブライアン・フォーブズと共同設立したリチャード・アッテンボロー。ジャック・レモンの初監督作『コッチおじさん』(1971年)の主演にはやはり盟友ウォルター・マッソーの名があった。

指導者に恵まれて成功したパターン
ここでもうひとつ重要なポイントが【イイ師匠を掴め!】だ。
クリント・イーストウッド、田中絹代、三船敏郎、松田優作
崇めていたドン・シーゲルとセルジオ・レオーネに愛され、『恐怖のメロディ』(1971年)で監督進出したクリント・イーストウッドの栄光の歴史を見よ。

もっとスゴイのはこの人である。木下惠介が脚本を手がけ、成瀬巳喜男の助言で「あに・いもうと」の助監督につき、修行の末に『恋文』(1953年)を撮った田中絹代。続く『月は上りぬ』(1954年)ではオリジナル脚本を提供した小津安二郎が溝口健二と喧嘩をしてまで彼女を推薦、撮影に協力した。

三船敏郎も恵まれている。『五十万人の遺産』(1963年)では黒澤明のアドバイスを受け、その馴染みのスタッフがフォローした。

『アラモ』でウェインの師匠ジョン・フォードの手伝ったシーンがカットされてしまった事例と比較すれば、何たる幸運だろう。
ま、そもそも監督志望で、さしたる師匠もおらず、それでも『女性対男性』(1950年)を皮切りに確かな演出力を示していった佐分利信や、『狩人の夜』(1955年)のチャールズ・ロートンのような異才もいるにはいるのだが……。

佐分利信監督作は『叛乱』のように主演を兼ねることも。


チャールズ・ロートンの『狩人の夜』は、のちに評価が高まった作品。

さて、『ア・ホーマンス』(1986年)を監督した頃に松田優作が師と仰いでいたのは工藤栄一だが、ついでに【自作自演でイケてる映画を撮れ!】というのも加えておこう。

自作自演だからこそ成立したパターン
ブルース・リー、バート・レイノルズ、ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、シルベスタ・スタローン、スティーブン・セガール、チャールズ・チャップリン、バスター・キートン、フランク・ロイド、萩本欽一、北野武
『吼えろ!ドラゴン 起きて!ジャガー』(1969年)、『片腕ドラゴン』(1973年)のジミー・ウォングに、『ドラゴンへの道』(1972年)のブルース・リー。
『ゲイター』(1976年)、『シャーキーズ マシーン』(1981年)のバート・レイノルズ。

ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、シルベスター・スタローン、スティーブン・セガールもこの範疇に属する。
これらを“芸人道”で語るなら、チャールズ・チャップリン、バスター・キートンらを源流に、『手』(1969年)、『俺は眠たかった!!』(1970年)の萩本欽一、ビートたけし=北野武へと続く。

演出舞台まで広がったパターン
サー・ローレンス・オリヴィエ、ホセ・フェラー、ピーター・ユスティノフ、ロベール・オッセン
さらに、サー・ローレンス・オリヴィエ、ホセ・フェラー(甥はジョージ・クルーニー)、ピーター・ユスティノフ、ロベール・オッセンと並べれば【舞台の演出を会得しとけ!】になる。

ローレンス・オリヴィエは『ハムレット』(1948年)でアカデミー作品賞、主演男優賞のダブル受賞。ジョージ・クルーニーは後に、監督進出しましたね。

時代の変わり目にハマったパターン
デニス・ホッパー、ピーター・フォンダ、シドニー・ポワチエ
いわゆるアメリカン・ニューシネマの先鞭をつけた『イージー・ライダー』(1969年)のデニス・ホッパー、『さすらいのカウボーイ』(1971年)のピーター・フォンダ、ブラックムービーの潮流に乗った『ブラック・ライダー』(1972年)のシドニー・ポワチエを並べれば、クエンティン・タランティーノへと連なる【時代の変わり目を狙え!】という方法論が浮上するだろう。
製作で成功した後に監督したパターン
カーク・ダグラス、ウォーレン・ベイティ、ロバート・レッドフォード、山村聡、勝新太郎
だが、最も有効な“方法論”といえば、【製作者としてまず成功しろ!】で決まりである。
1949年にブライナー・カンパニーを設立し、スターによる独立プロの成功者となり、1973年から監督業にも乗り出したカーク・ダグラス。

ウォーレン・ベイティも2000年のオスカーで“アーヴィング・G・タールバーグ”賞(プロデューサーに贈られる賞)を授かった通り。


初めて製作を手がけたのは、主演作『俺たちに明日はない』(1968年)でした。


初監督し、製作・出演もした『天国からきたチャンピオン』(1978年)はアカデミー賞で9部門にノミネートされました。
そして「俳優→監督」の流れを決定的にしたロバート・レッドフォード。彼は『白銀のレーサー』(1969年)、『候補者ビル・マッケイ」』(1972年)、『大統領の陰謀』(1976年)などの製作、主演で地歩を固め、満を持して「普通の人々」(1980年)で監督業に専念、いきなりオスカーを得た。
一方、日本ではもともと劇作家を志し、1952年に現代プロダクションを設立した山村聡がいる。『蟹工船』(1953年)で監督デビューするや、日活、東映東京とオールマイティに活動し、滋味深い作品を残した。

そう考えると、三船プロと組んで『黒部の太陽』(1968年)を作った“プロデューサー”石原裕次郎は間違ってはいなかったが、彼自身の監督作がないことを考えれば、卓越した演出が光る『顔役』(1971年)を挟みながら70年代半ばまで、『座頭市』『子連れ狼』『御用牙』などのヒットシリーズを連発していた勝新太郎に軍配は挙がるだろう。彼の“プロデューサー”を含めた製作面での業績はもっと評価されてよい。

石原裕次郎さん、監督作はなかったんですね。
一気にすべてを掌握した別格
オーソン・ウェルズ
ところで以上の“方法論”というやつは、便宜上分けられているだけで、実際はひとりひとりの俳優に複合的に関係してくるものだが、『市民ケーン』(1941年)で製作、監督、脚本のすべてを掌握し、今回のポイントのほとんどをクリア、おまけに主演してカリスマにまでなってしまったのがオーソン・ウェルズだ。しかし、のちの“呪われた作家ぶり”を眺める限り、やはりこの世ままならなさを痛感せざるを得ない。
が、それでも俳優たちはかねがね、こう思っているに違いない。
「指揮ができるという自信があれば、バイオリニストに甘んじる必要はないだろう?」(byポール・ニューマン)と──。


キネマ旬報2000年5月下旬号掲載記事を改訂です!

以上、約20年前の記事を復刻してみました。

関連記事理もご紹介!

記事内に登場のタイトルは、動画配信サービスで見つからない場合、古いタイトルの在庫が豊富なDVD宅配サービスを利用するのもテです。