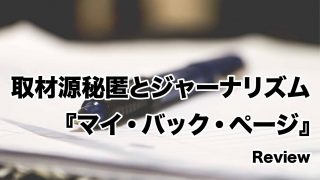映画批評についてのコラムです。
3本のフェイバリット・ムービーと贖罪意識と補助線と

雑誌「DVD&動画配信でーた」で「三つ数えろ!」という企画ページを担当している。

ちなみに「DVD&動画配信でーた」は、創刊当初の誌名は「ビデオでーた」。その後、「ビデオ&DVDでーた」、「DVD&ビデオでーた」、「DVDでーた」、「DVD&ブルーレイでーた」と変更となり、現在のタイトルになってます。
誌名史に、まんま劇場外映画観賞の歴史が見えます!
登場していただくのは、映画監督の方々。何かひとつのテーマを選んでもらい、それに沿って、三本のフェイバリット・ムービーについて語っていただくのである。
で、同時に、新作のこともお訊きする。これらを総合すると、一見無関係そうに見えた三本の映画(を包んだテーマ)がその新作の底辺に潜んでいる場合も。監督の基本的嗜好を反映している三本だから、そういうことも多々あり得るのだ。
例えば、『八日目の蟬』を携えての成島出監督は、“心揺さぶられた衝撃作”というテーマを掲げられて、『タクシードライバー』『ミーン・ストリート』『ラストタンゴ・イン・パリ』をセレクトされた。


『八日目の蟬』の原作は角田光代の小説。テレビドラマ化ののちに映画となりました。


『タクシードライバー』『ミーン・ストリート』はいずれもマーティン・スコセッシ監督、ロバート・デ・ニーロ主演の映画です。


『ラストタンゴ・イン・パリ』はベルナルド・ベルトルッチ監督、マーロン・ブランド主演。公開当時はエロティックな表現が物議を醸しました。

理由を伺って、驚いた。
時は1980年代初頭。浪人生となり、予備校に通うため下宿先を決め、上京したその日。新宿駅を出ると、目の前に人が降ってきたのだという。なんと、投身自殺を目撃してしまったのだ。ショックで、予備校へと手続きに行く気は起こらず、足はなぜか三鷹のほうへと向かっていた。おぼろげに情報として知っていた(今はなき)名画座・三鷹オスカーのもとへ吸い込まれてしまい、そこで組まれていたのがこの三本立て。
現実の“衝撃”にさらに映画の“衝撃”が重なってゆくわけだが、詳細は、連載を覗いていただければ幸いだ。
さて。はばかりもなく自己宣伝で終えるつもりはない。「私の映画批評の姿勢」である。
熟考した結果、勝手ながら自分の「三つ数えろ!」をここで選ばせてもらおうと思う。きっとそのほうが、“姿勢”めいたものが浮かび上がってくるのではないか……今日の気分でいえば、次の三本がいい。『ダブルベッド』(1983年)、『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)、『マイ・バック・ページ』(2011年)。観た順だ。テーマは「自分の深層心理が綴られている三本」とでもしておこう。
一本目の『ダブルベッド』は、中山千夏の同名小説を藤田敏八監督が映画化した作品。

30代の頃に出会って、やたら泣けて仕様がなかったのだが、だからといって、ここで描かれているような、あんな爛れたセックスライフを送っていた過去はありませんよ! とにかく中年夫婦(岸部一徳、大谷直子)とその友人(柄本明)、若き恋人(石田えり)たちが入り乱れ、どエライことになると。
妻の不貞を知り、雨の中、若き小野田官房長……じゃなかった、岸部さんがひたすら壁当てキャッチボールをしているシーンがグっときた。おそらく自分なりに、青春とやらの行き止まり、あるいは終止符を感じて、身につまされたのだろう。
二本目の『ジョゼと虎と魚たち』はリアルタイムで観た。これも泣けた。

足が不自由なジョゼ(池脇千鶴)と、大学を出たばかりの男(妻夫木聡)とのドーしようもない、けれども濃密な時間の記録。
原作は田辺聖子の短編小説。監督は犬童一心。男が女をおんぶするシーンのある作品が好きなのだ。神代辰巳の『青春の蹉跌』やら、佐々木昭一郎のTVドラマ『夢の島少女』やら。あの一切合切を“背負ってる感”がいいのだ。むろん、自分には忘れがたき、おんぶの思い出などはないのだけれども。

そして、三本目。これから公開される山下敦弘監督の『マイ・バック・ページ』は、本誌でもお馴染み、川本三郎氏の若き日の葛藤と挫折の物語である。


『マイ・バック・ページ』についてはこちらのレビューもあります。
時代設定的にはほとんど接点のない、言ってしまえば“遠い昔の話”なのにもかかわらず、並行して自らの悔恨の日々、マイ・バック・ページを振り返らされてしまった。
とりわけエピローグ部分にはヤラれた。それまで仮死状態に陥っていた者が、忘れていた呼吸の仕方を思いだし一気に息を吸いこんで、空気を吐き出したかのような安堵と解放感と、はたまた、新しい人生が始まってしまうことのおののきが綯い交ぜになった、そんな身体的な感覚を追体験させられた。
劇中、川本氏を演じているのは、妻夫木クン。彼の出演作が二本というのは偶然だが、にしても、この三本の映画に共通しているものは一体何だろう。
ずばり、贖罪意識だろうか。では誰に対しての? 女性への? いやいや、ご迷惑をかけている編集者の方々への?
ハ〜イ、終了ぉーっ。
一介のライターを俎上に乗せ、こんな俗な分析をしても何にも面白くない。しかし監督や作品を対象にすると、実に多様な関係性が見えてくる。幾何の問題を解くがごとく、批評やインタビューでヒントとなる“補助線”を引けると嬉しい。もうその、ほんのヒントでもいいのだ。
が、御存知のとおり、映画というのは、とてもヤッカイなものである。Berrys工房も以前、こう歌っていたではないか。『付き合ってるのに片思い』(作詞・作曲/つんく♂)と。

ドーです、このタイトル。付き合ってるのに片思いなんですよ! 自分が好きでも、相手はちゃんと振り向いてくれるとは限らないのだ。なんという切ない関係……でもそんな状態さえも楽しむしかないわけで。映画に対する僕の心の中は常に、“付き合ってるのに片思い”——複雑な気持ちが渦巻いている。

キネマ旬報2011年4月下旬号掲載記事を改訂!