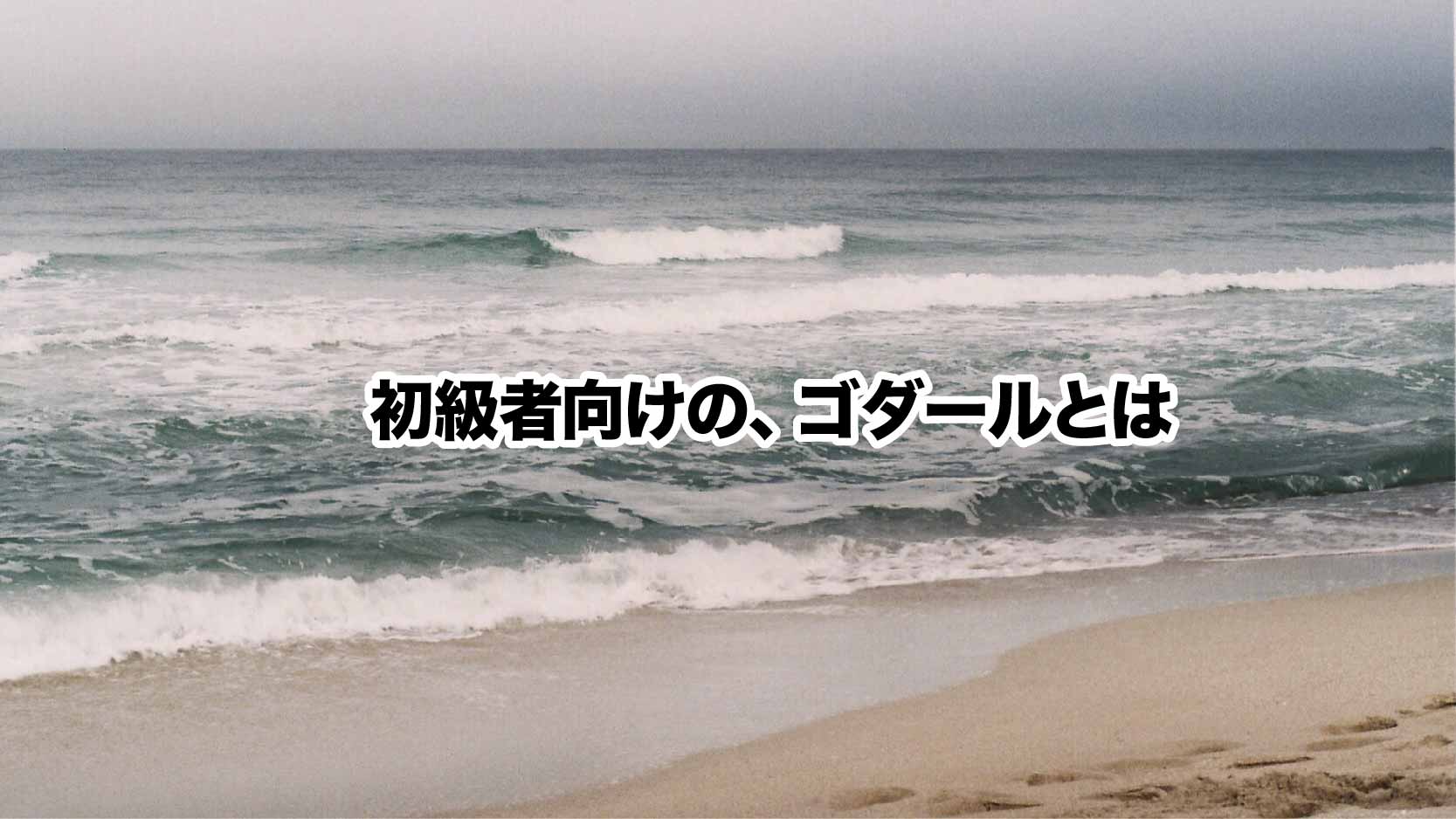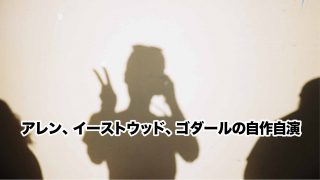ヌーヴェル・ヴァーグの旗手、ゴダール。撮った映画の評価は永遠。

リアルタイムに観ていたなら分かる凄さも、今初めて出会うとなると、正直言ってわかりにくい。

不思議な映画は解説されるとぐっと面白くなることがあります。

てことで、ゴダール解説記事を復刻です!

ゴダール・リフレクション。それは「イメージ」の乱反射!
(文・轟夕起夫)
永遠のパンク作品
「ゴダールが好き!」と言うことは簡単だが、どこがどう好き、と説明するのは、本当に難しい。
別に、あの頭の禿げあがった風体のあがらない男そのものにメチャクチャ魅かれているわけではないはずだ。作品オンリー。それもどちらかというと1960年代に作られたポップでキュートなイメージのやつ。
ま、あくまで「イメージ」ってところがミソなのだが。これがついついマネしたくなるカッコ良さなのだから困る。そこが重要。
ゴダール映画は「イメージ」を無数にリフレクションさせてゆく。反射。寄せては返す波のように。それがヌーヴェル・ヴァーグの真髄だ。
つまり、二度目の波とは一度目と同じように見えても明らかに違う波なのだ、と開き直ること。だからここではそんな風に、リフレクションの波に身を委ねて“ゴダール”を旋回してみようと思う。まさに彼の映画のように――。
というわけで、ゴダールの長編デビュー作『勝手にしやがれ』(1959年)である。まずこれからしてリフレクションの映画だった、本人もこう言っている。「ハワード・ホークス監督の『暗黒街の顔役』(1930年)のリメイクをめざしたのだ」と。


『勝手にしやがれ』は主演・ジャン=ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグ。ゴダール自身も密告者役で出演してます。

しかし二度目の波は違う波。それはハリウッドの犯罪映画の傑作には似ても似つかない代物になった。
というか、原題のごとく、主人公たちがエンディングめざし「息せききって」突っ走る、ほかのどの映画にも似ていない“永遠のパンク作品”になってしまった。
ハイセンスなファッション
ところで「ハリウッドの犯罪映画」にはなれなかったものの、アメリカ(映画)に憧れていた当時のゴダールの気分は、ファッションを通じてフィルムの中にしっかり焼きつけられている。これを見逃すテはない。
スウェードのジャケットとシルクの靴下で身を飾り、ハンフリー・ボガードに憧れるジャン=ポール・ベルモンド。
そして、Tシャツ姿のヒロインの登場だ! ヤンキー娘ジーン・セバーグのTシャツには“ヘラルド・トリビューン”のロゴが記されていて実にキマっているのだが、これはフレンチTシャツと呼ばれるもので、肩口から二の腕の3分の1までに収まる袖丈が絶妙なアイテム……と、エスクァイア別冊「映画的、ファッション!」には説明してある。
ついでにいうと『KIDS』(1996年)でクロエ・セヴィニーが着ていたTシャツもその流れにあるのだと。ふーむ。『勝手にしやがれ』は映画の革命であったが、映画の中のファッション革命も同時に果たしていたのだな。しかもなお、現代においてもジャストで「使える」映画。

それはもう一点、ジーン・セバーグにぴったりだったボーダーのTシャツを例にとっても自明のことだろう。
ボーダーといえば人気デザイナーのアニエスb.。何しろゴダールの1987年の作品『右側に気をつけろ』は、アニエスb.“提供”で公開されたのだった。

もともと映画館に足繁く通うシネフィルであり、ゴダール以外の作品でも『カンフー・マスター』(1987年)で衣裳協力、『カルネ』(1994年)、『ミミ』(1996年)の監督ギャスパー・ノエヘの多大な協力を惜しまぬ彼女だが、とりわけそのファッションの成り立ちにおいて、ゴダール映画がいくつもの霊感を与えていても不思議ではなかろう。

1998年には両者の深〜い関係を示すイベントもあった。フランス年を記念し、日本で開催されたアニセスb.映画祭。そこでは彼女のセレクトで7本のフランス映画が選ばれたわけだが、中に、ゴダールの激レアものの『はなればなれに』(1964年)が入っていたのだった。

『はなればなれに』は、やはりゴダールのハリウッド・ミュージカルへの傾倒が別の波になって返ってきた、面白ギャング3人組のお遊戯スケッチ風ムーヴィーの傑作。唐突にジュークボックスのジャズ(作曲はミシェル・ルグラン!)に合わせ、3人がマジソン・ダンスを踊るカッチョいいシーンがつとに有名で、日本では2001年にようやっと初公開された。
ミューズはアンナ・カリーナ
3人組のひとりは、ゴダール映画の女神(ミューズ)アンナ・カリーナ。彼女の“アフター・ガーリーズ”な王道ファッションがとても印象的。
クールネックのセーター、チェックの膝丈プリーツスカートにピーコート、足下には黒ハイソックス、さらに耳隠しお団子ヘアのアンナ・カリーナ。
まったく元祖オリーブ少女って感じで、これまたジャストな感覚なのだ。恐れ入ったぜアニエスb.、いやいやゴダールさん。
クエンティン・タランティーノへの影響
さて。定番エピソードだと思うが一応。その『はなればなれに』の原題「Bande à part」が、熱狂的ファンゆえクエンティン・タランティーノの共同製作会社の名前になっているのであった。直情的なタランティーノらしい。
しかも彼、出てもいないのに履歴書に“『ゴダールのリア王』(1987年)出演”と書いていたらしい。何という男だ。

『パルプ・フィクション』(1994年)では『はなればなれに』のダンスシーンを、ジョン・トラボルタ&ユマ・サーマンで甲斐甲斐しくもリミックス。よっぽど好きなんだね。
この“リミックス”という方法論の発展的継承、てな見地からも、タランティーノは作家的にゴダールと1本繋がっている存在ではある。

レオス・カラックスへの影響
しかしもうひとり、ゴダール狂で知られるレオス・カラックスは、「カイエ・デュ・シネマ」誌の批評家から映画監督へ、というゴダールと同じ軌跡を歩み、『ゴダールのリア王』にもちゃんと役者として出演した正当追っかけ派だ。
カラックスからすれば「タランティーノはゴダール道に反する」なんて怒っているかも(推測)。
ま、その生真面目さが『ポンヌフの恋人』(1991年)以降の長い沈黙を生み、新作『ポーラX』までに8年もの月日を重ねさせたのだろうが……。
アンナ・カリーナとココ・シャネル
ん? 少々話がズレたか。まあいいではないか。寄せては返す波に漂っていればそんなこともある。脱線ついでに“アンナ・カリーナ”という芸名を考えた超有名なデザイナーの名も記しておこう。ココ・シャネルである。
ココ・シャネルは1930年代、ハリウッドに正式に招待されたフランスのデザイナーとしても知られるが、すぐフランスに戻って映画、演劇界に多大な功績を残した。
カリーナと出会ったのは、ルイ・マルの『恋人たち』(1958年)やロジェ・ヴァディムの『危険な関係』(1959年)でジャンヌ・モローの衣裳を手がけたあとであろうか。
デンマーク生まれ、コペンハーゲンからパリにやってきたばかりのカリーナは、カメラマンの紹介で「ELLE」の女社長エレーヌ・ラザレフのもとに行き、そこでたまたま同席していたシャネルと遭遇。シャネルは当時の彼女の名前“アン・カリン”を「語呂が悪い」と指摘し、ずばり“アンナ・カリーナ”へと変えたのだった。
ゴダールとアンナ・カリーナの結婚と離婚
本筋に戻ろう。ゴダールとアンナ・カリーナが結婚したのは1963年。彼女が『小さな兵隊』で初主演した直後である(実は当初彼女は『勝手にしやがれ』にも出演するはずであった。ほんの端役だが)。

ゴダールの映画は公私を共にしたコラボレーションとなった。それはまた1965年に離婚するまで、2人の恋愛模様が作品の中に微妙に反射=リフレクションしていることを意味していた。
子供を欲しがる妻(カリーナ)と夫の困惑を描いた『女は女である』(1961年)。

美しくも哀しい娼婦(カリーナ)の一生を12章のストーリーにした『女と男のいる舗道』(1962年)。

妻(ブリジッド・バルドー)が夫のもとを去ってしまう『軽蔑』(1963年)。

不倫する人妻(マーシャル・メリル)の日常生活をレポートした『恋人のいる時間』(1964年)。

そして別れる寸前にカリーナと組んだ1965年の2本。現実のパリを未来都市に見立て、“愛(ラムール)”の一語をつぶ やいてコンピュータの管理会社から男と女が脱出する『アルファヴィル』(1965年)。女をひたすら愛し、翻弄され、最後には裏切られる男の悲喜劇『気狂いピエロ』(1965年)。
どうだろう。すべてがそのまま2人の関係とリンクしているとは言えないまでも、微妙な影を落としていることは明白だ。
離婚後に撮られた『メイド・イン・USA』(1966年)でカリーナは、謎めいた犯罪に深入りするジャーナリストに扮し、さながらハンフリー・ボガートのようなトレンチ・コートを着て、次々と血なまぐさい事件を引き起こして歩く。「さよなら、アンナ」。そんなゴダールの別れの言葉が漏れ聞こえてくる。〈私〉映画。これは今日の“ドキュメント・ドラマ”の走りといえよう。

ちなみに写真家の荒木経惟がいちばん好きなゴダール映画は『女と男のいる舗道』だとか。わかる気がする。そう、彼こそはセンチメンタルな旅を繰り返す〈私〉写真の実践者。
変貌するスタイル
このあとゴダールは、政治とブルジョワ社会を赤塚不二夫的、すなわち『天才バカボン』的に笑いのめした『ウィークエンド』(1967年)を撮り、アンヌ・ヴィアゼムスキー、アンヌ・マリー・ミエヴィルとパートナーを変えるごとに映画のスタイルもどんどん変貌させていった。


こちら、赤塚不二夫の漫画のテレビアニメ『天才バカボン』。

ヴィアゼムスキーが出演した『ワン・プラス・ワン』(1968年)では、『悪魔を憐れむ歌』制作時のローリング・ストーンズ(最初ビートルズにアプローチしたが断られた)の録音風景を捉えながら、当時強く共鳴していたブラック・パンサーの政治的メッセージをところどころにぶちこんでアジビラ映画を作り上げた。

パリが5月革命を迎えるとますます過激に若者を煽動し、同志アンヌ・マリー・ミエヴィルと出会うと完全に商業映画から背を向けてしまう。彼が再び日本の劇場に戻ってくるのは1983年のことだ。
音楽のチャレンジ
その復帰策『パッション』(1982年)についてムーンライダーズの鈴木慶一はこう述べている。
「『パッション』がショックだったのは、音の使い方がずれているということだね。口とずれたりすることもあるし、手前の音が次のシーンにかぶっていたり、こぼれていたり、あのエディットの仕方が、当時イギリスで流行っていた「ダブ」というレゲエのサウンド処理の仕方に似ていた」(現代思想『ゴダールの神話』)。

ムーンライダーズとして、『ヌーヴェル・ヴァーグ』『カメラ=万年室』といったアルバムを発表、「アルファビル」「彼女について知っている二、三の事情」とゴダール映画そのもののタイトル曲も残している鈴木慶一。先の発言は、さらにこう続いている。
「わざとずらしたり、音をカットしたり。『これはダブ映画だな』とひそかに思っていたら、パンフレットを見たら、坂本龍一が同じようなことを言っている(笑)」
そういえば『中国女』(1967年)には人民帽を被ったアンヌ・ヴィアゼムスキーが登場。当時のゴダールには毛沢東主義の思想的なバックボーンがあったわけだが、坂本龍一≒YMOが人民帽をビジュアル・イメージにもってきたというのも“ゴダール・リフレクション”の一端といってもいいだろう。


坂本龍一が参加していたYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のアルバム「イエロー・マジック・オーケストラ」には、「中国女」というタイトルの曲が収録されてます。

1970年代以降、「ダブ」にも似た手法をゴダールは“ソニマージュ”=音(ソン)+映像(イマージュ)と名づけ、理論化し、両者の関係をますます多義的(あるいは無意味的)に結びつけた。
そうしていまも、ユーウツな表情を見せながら彼は音と映像で遊びまくっている。
その方法論はジョン・ゾーン(『ネイキッド・シティ』で『軽蔑』を破壊的にカヴァー、さらには『ゴダール』という楽曲も!)といった前衛的なアーティストに引き継がれているばかりでなく、いまや普通のDJ(VJ)行為となった(ピチカート・ファイヴの活動全般を見よ!)。

ジョン・ゾーンはサックス奏者で作曲家、音楽プロデューサー。


ピチカート・ファイヴの楽曲は「渋谷系」と呼ばれました。

寄せては返す波。思わずマネしたくなるカッコ良さ。寄せては返す波。そして今日もまた、彼の預かり知らぬ世界のどこかで、ゴダール映画は上映されている。

smart1999年10月号掲載記事を改訂!

ヌーヴェル・ヴァーグとは、1950年代末からフランスで起こった映画の新しい波のこと。ゴダールや、フランソワ・トリュフォーなどの若手映画人が起こした波です。
ゴダールの活動が、まんまヌーヴェル・ヴァーグとして起きていたことと言えます。

こちらの関連記事も、ご紹介!