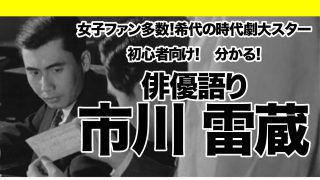高峰秀子は、1924年生まれ、2010年に亡くなりました。映画の旧作をたどると、あれもこれもと出演しているスター女優。

どんな女優だったか? 軌跡をたどります。
天才的子役の誕生
手っ取り早く高峰秀子の代表作を探そうとすれば、「山本嘉次郎、成瀬巳喜男、木下惠介」という、彼女の出演歴の多い3巨匠の作品になるのだろう。
だが、当然ながら「忘れ難き高峰秀子」はもっともっと無数にいる。それらも含め、ざっと概観してみるとしよう。
まずは子役時代。そもそもは1929年、隣人であった松竹蒲田の俳優・野寺正一の案内で、義父が彼女をおぶって蒲田撮影所の見学に。たまたま映画『母』の「5歳女児」オーディションが行われており、義父が60人ほど連なっていた行列の最後に並ばせたところ、たちまち監督の野村芳亭の目に止まったという。
女優・高峰秀子の誕生だ。御年ちょうど5歳。
松竹蒲田撮影所への正式な入社が決まり、映画は大ヒットを記録した。野村芳亭は母物や新派悲劇調の名手。その手の作品には天才的な子役が必須で、しかも高峰は和製シャーリー・テンプルともいうべきモダンさも兼ね備えていた。
少女スターへ
島津保次郎監督の『レヴューの姉妹』(1930年)や『愛よ人類と共にあれ・前後篇』(1931年)では少年役もあてがわれたが、オカッパ頭で快活、愛らしい彼女は人気を得、雑誌の表紙を飾り、ブロマイドも飛ぶように売れた。
子役としてキャリアを重ねていく過程で、小津安二郎監督とも出会っている。
昭和初期のしがないサラリーマン一家の生活を描いた『東京の合唱』(1931年)。主人公の娘役で、内容のほうはなかなかシビアなコメディだが、屈託のない笑顔を見せる幼い高峰秀子に触れることができる。

松竹はすでに撮影所を蒲田から大船へと移していたが、1937年、松竹を退社し、東宝の前身であるP・C・Lに移籍。ここから『藤十郎の恋』(1938年)、『綴方教室』(1938年)、『馬』(1941年)など、山本嘉次郎監督との名コンビが形成されていく。



それらの作品の製作主任であった黒澤明とは残念ながら、のちに山本嘉次郎、関川秀雄との共同監督作である組合礼賛ムービー『明日を創る人々』(1946年)しか残せなかった(しかも黒澤は、自らのフィルモグラフィには入れていない)。
が、P・C・Lが東宝になると、彼女の活躍は目覚ましく、ますます際立っていく。
歌うスターへ
例えば、東宝が配給契約を結んだ南旺映画、千葉泰樹監督の『秀子の応援団長』(1940年) 。タイトル通り、プロ野球団アトラス軍の大ファンという設定で応援歌を作り、それがキッカケでヒロイン・秀子がチームのマスコット的存在になってしまう多幸感に満ちた快作だ。
この中で、野球選手役である歌手の灰田勝彦と高峰は、主題歌「燦めく星座」を一緒に唄っている。ある意味、アイドル映画、自分の名をタイトルに冠した映画が出来上がってしまうあたり、明らかに特別な存在であった。

また、声楽家の奥田良三と長門美保に師事し、彼女は歌うスターとして躍進していった。
1942年にはレコード「森の水車」を発表。時節柄、米英的という理由で発売禁止になったが、戦後、日劇のショー『ハワイの花』に出演、灰田勝彦と共演してフラダンスを踊り、喝采を浴びた。これをもとに映画化したのが谷口千吉監督の『東宝ショウボート』(1946年)である。
成熟した娘へ、そして大人の女性へ
東宝は争議によって混迷を極めていたが、イデオロギーよりも純粋に映画を作りたいと1947年、組合の政治主義に批判的なスター10人が「十人の旗の会」を結成して脱退、そのひとりに彼女も加わり、撮影所のメンバーを大きく動かし、新東宝が生まれた。
少女から成熟した娘へ、そして大人の女性へ。時のうつろいと共に女優・高峰秀子の魅力はさまざまな作品で開花していく。
戦前、『愛の世界 山猫とみの話』(1943年)、『兵六夢物語』(1943年)の演出助手をやっていた市川崑は、彼女の家に下宿していたことがあり、彼が構成を担当したレビュー映画『東宝千一夜』(1947年)では中川一郎とタップダンスを披露。
さらに市川崑の監督デビュー作『花ひらく・眞知子より』(1948年)の主演も務めた。
名家のブルジョア娘で、しかし社会主義運動にのめりこみ、真っ直ぐに生きようとして懊悩する女子大生役である。以後、彼女がお手のものとする、真摯だからこそ不機嫌に人生と格闘するキャラクターのプロトタイプとも言える。
かと思えば、島耕二監督の歌謡映画『銀座カンカン娘』(1949年)では、灰田勝彦やブギウギ歌手として名声を博していた笠置シズ子と共演、高峰も主題歌「銀座カンカン娘」を陽気に唄いあげ、ビクターから出したレコードは大ヒットした。

谷崎潤一郎原作、阿部豊監督の『細雪』(1950年)では、四姉妹の末っ子の妙子役。姉に扮した花井蘭子、轟夕起子、山根寿子ら大女優をさしおいて、物語の実質的な主軸を任され、恋にアクティブな女性像を体現した。

『東京の合唱』以来の小津作品『宗方姉妹』(1950年)では田中絹代の妹役で、和服の田中、洋服の高峰というコントラストも鮮やかに、旧弊を打ち破ろうとするアプレゲールな娘の言動に血肉を通わせた。

この頃はすっかり新東宝の中核的存在になっていたが、『宗方姉妹』を最後に新東宝を辞め、フリーになることを選択。これで作品セレクトをセルフコントロール、高峰秀子の足跡は、ダイレクトに日本映画史の輝かしき勃興期と重なってゆく運びとなる。
パリ生活からの帰国
1951年、木下惠介監督の『カルメン故郷に帰る』で女優としてまたも大きく飛躍するも、日本を脱出し、約半年間、フランスはパリに渡って生活。帰国後、最初の作品が『朝の波紋』(1952年)だった。

監督は子役時代から付き合いの深い五所平之助。女の情感と強い自我を合わせ持つ貿易会社の敏腕秘書をしっかり自分のものにし、さらに『煙突の見える場所』(1953年)では街頭放送のアナウンサーという変わり種の職業でも好演。

ひとしきり現代性を象徴するような役が続いたが、森鴎外の名作、豊田四郎監督が映画化した『雁』(1953年)の舞台は明治中期。老夫を養うため、高利貸の妾宅に囲われているヒロインに身を投じ、帝国大の医学生に報れぬ想いを寄せる“日陰者の哀しさ”をしみじみと描きだした。これは高峰自身も大好きな一本とのこと。

助演での求道
さて、木下惠介監督の『二十四の瞳』(1954年)で国民的スターとなり、成瀬巳喜男監督の『浮雲』(1955年)でいわば演技派を極めた彼女だが、たとえ主役でなくても、なおも求道を続けた。


森繁久彌と共演、久松静児監督の『渡り鳥いつ帰る』(1955年)でアンモラルな私娼役に挑戦し、松本清張原作、野村芳太郎監督の『張込み』(1958年)では刑事に監視されている女。かつての恋人が逃走犯になり、見張られていることで生の輝きを増す、高峰にしか達成しえない女の実在感をスクリーンに刻んだ。


俳優・森繁久彌については、こちらでご紹介しています。
この野村芳太郎とは確認するまでもなく野村芳亭の息子で、古くからのファンは、デビュー作『母』のオカッパ頭の少女の“旅路”に積年の思いを馳せることだろう。
ヴェネチア国際映画祭でグランプリに輝いた『無法松の一生』(1958年)は、巨匠・稲垣浩の監督作。三船敏郎扮する、御存知暴れん坊の人力車夫・松五郎が純な気持ちをぶつける聖女、吉岡大尉夫人の慎ましさ、美しさを彼女は見事に立体化してみせた。

1960年代に入ると、並走してきた同志的な監督たちの製作体制が次第にままならぬものになっていき、日本映画自体の質的変容もあって、高峰の出演数はだんだんと減ってゆく。
そんななか、夫の松山善三がオリジナル脚本を記し、監督デビューを果たした『名もなく貧しく美しく』(1961年)は、二人の心根を映し出した一篇の詩であった。

聾唖者同士の夫婦の物語を、綺麗事に逃げずに繊細に紡ぎ、彼女は手話を完璧に体得して、全身全霊で映画を支えた。
さらに大正時代のハワイ農業移民団に材をとった『山河あり』(1962年)をはじめ、『ぶらりぶらぶら物語』(1962年)、『われ一粒の麦なれど』(1964年)、『六條ゆきやま紬』(1965年)と、松山善三と共に、人間のヒューマニズムの可能性を問う作品を連打。
これらには全て、キャストに小林桂樹の名が守護神のごとくクレジットされていた。

俳優・小林桂樹に関しては、こちらで紹介しています。
女優業に幕
1979年、木下惠介監督の『衝動殺人息子よ』で高峰秀子は、自ら女優業に幕をおろすのだが、その前に2本の有吉佐和子原作で、映画史にいつまでも輝き続ける傑作を残した。

ひとつは、増村保造監督の『華岡青洲の妻』(1967年)。大映スターの市川雷蔵、若尾文子を前にして、世界最初の全身麻酔による乳がん手術に成功した江戸時代の名医・青洲の母親役でエキセントリックかつセンシティブな人物像を造形。


俳優・市川雷蔵ついては、こちらで紹介しています。
もうひとつは森繁久彌主演、老人性痴呆の問題を扱った豊田四郎監督の『恍惚の人』(1973年)。こちらは徘徊老人となった夫の父を介護し、愛憎の果てに菩薩のまなざしを獲得してゆくような役柄。

美と醜、聖と俗、善と悪……人間世界の裏表、それら全てを彼女は、その生涯で、女優の業として表現してきたーー。
いや。断るまでもないだろう。ここに掲げてきた映画たちはほんの一部である。「忘れ難き高峰秀子」は、まだまだ尽きない。

キネマ旬報2011年4月上旬号掲載記事を改訂!